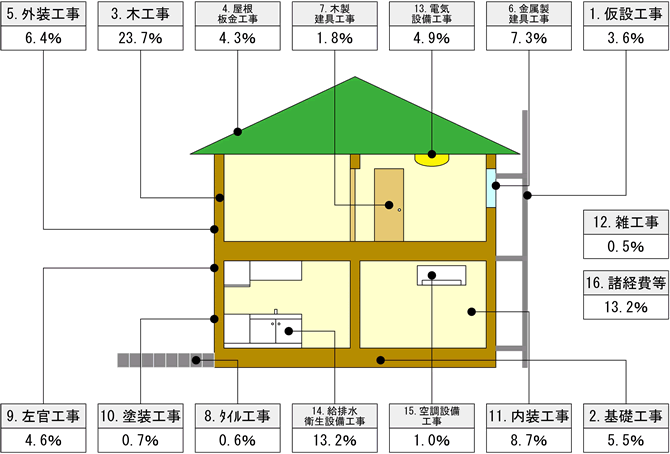家づくりの「心」を「かたち」に、具体例を交え心の家づくりを解説した一級建築士のアドバイスです。
予算オーバー!木工事をチェックしてみる
予算と建築工事費の一致は難しい
間取りや仕上げも決まり、いざ見積もりが上がってきたら予算オーバー・・・というのはよくある話です。おそらく家を建てた人のほとんどが経験しているかもしれません。それだけ予算と建築工事費が一致することは難しいのです。計画段階ではつい良い住まいをつくりたいと夢を膨らませてしまうからです。
予算オーバーの金額にもよりますが、どの箇所をコストダウンすれば良いのか迷うところです。一般的には仕上げ材や設備機器のグレードを下げます。しかし、グレードの下げ方に留意しないと、建物や内部空間はチープな印象になってしまうこともありますので、十分な配慮が必要になります。
工事費の割合をチェックしてみる
見積内容を検討するにあたって、一番始めにチェックするところは木工事のところです。次の一般的な木造2階建住宅の工事費の割合を見て下さい。
この中で最も大きな割合を占めているのが木工事(23.7%)だからです。
一般に設備工事費の中にある設備機器等はカタログに定価が表示されていますので、あとは掛け率を確認すればおおよその感じはつかめます。
しかし、木工事だけは全体を占める割合が高い割には曖昧で、工事内容をスルーしてしまう傾向があります。そのあたりをチェックしてみましょう。
まずは木工事でいちばん重要な大工職人の働き方です。大工職人の形態ですが、手間のとらえ方によって大きく「常用大工」と「手間請け大工」の2つに分けられます。
常用大工は1日当たりの手間代が決められており、人工(にんく)数による見積もり方法が用いられるのです。例えば、昔は坪当たり約5.5人工でした。人工とは作業量の単位で一坪つくるのに5.5人が必要ということです。
しかし、近年の住まいでは木材は工場でプレカットをしたのち、現場で組み立てるだけなので、作業量も減り、約3.0~3.5人工と下がっています。
一方、手間請け大工は建物全体、もしくは一部工事の報酬が既に決まっており、「床面積あたりの単価×延べ床面積」による見積もり方法が用いられます。なかには大工職人を社員として雇用している会社もあります。この場合は月給制になります。
このように報酬形態、雇用形態によっても見積り金額は変わってくるので、そのあたりも施工会社に訊いてみることです。
仕事の範囲
近年の木造住宅の殆どが工場でプレカットをしてきます。したがって、現場では多少の調整で組み立てることができることを先に述べました。さらには外壁のサイディングはサイディング業者、キッチンはキッチン屋さんといった具合に、専門施工業者の分業化が進んでいて、大工職人の仕事の範囲が狭まっているともいえます。そういった仕事の範囲を確かめることで、見積もりされる範囲が被っていないか、あるいは抜けていないかをチェックすることも大切です。
佐川旭のアドバイス
一般にコストを落とすには、
① 相見積もりをする
② 値引き交渉をする
③ 第三者に見積もりをチェックしてもらう
④ 建物の大きさを小さくする
⑤ グレードを下げる
などあります。
もちろん、これらの作業も大切な項目ですが、大工職人は着工から木工事終了まで現場に一番長く関わります。この長く関わる分、つい他業者が置いていったゴミやダンボールの片づけ、また、現場監督は一人で何棟も工事物件を持っているので、現場の大工さんに管理してもらうこともあるのです。そういった曖昧な部分に費用が加算されていないかを確認しておきましょう。
建築はどうしても専門的な用語や、無いものをつくっていくので想像しづらい面があります。その点においても仕事の「見える化」をしておくことで、見積り金額が適正かチェックすることができます。
「切妻」について
今月号から、建築用語の解説を設けました。楽しく読んで頂けるよう、わかりやすく説明します。今月は「切妻」についてです。
コストを抑えるのであれば、複雑な屋根の形にするより、切妻にすると抑えられます。でも、「切妻」って「妻を切る」と書くので、穏やかではありませんね。
これは「妻」を女性とだけ理解すると穏やかではなくなるのですが、住宅では棟の直角にあたる部分を「妻」といいます。(棟に平行な面が「平」と言います。)四角形の上部を鉛筆の先のように削るというか、切り取った状態が「切妻」ということです。

佐川 旭Akira Sagawa一級建築士
株式会社 佐川旭建築研究所 http://www.ie-o-tateru.com/
「時がつくるデザイン」を基本に据え、「つたえる」「つなぐ」をテーマに個人住宅や公共建築等の設計を手がける。また、講演や執筆などでも活躍中。著書に『間取りの教科書』(PHP研究所)他。