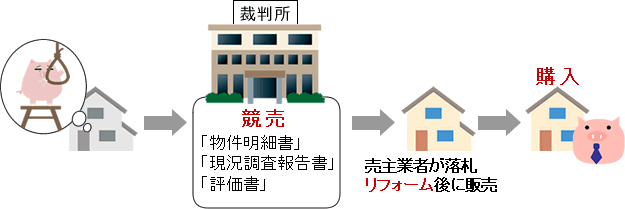不動産売買のトラブルを防ぐために判例等を踏まえ弁護士が解説したアドバイスです。
競売物件の説明義務を巡るトラブル
Q
私は、3か月前に、売主業者A社からリフォーム済の中古住宅を購入しました。
購入後に近所の方の話から判ったことですが、この住宅の元の所有者はBであり、今から約2年前にこの住宅内で自殺をしたようです。その後、この住宅は、競売開始決定がされ、売主業者A社が落札し、その後、リフォームを行い販売していたのです。
この住宅の競売資料である「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」(以下「競売資料」という)を後で確認したところ、確かに「Bの住宅内の自殺」を伺わせる「事故物件」の記載がありました。しかし、私がこの住宅を購入する際には、売主業者A社から「事故物件」に関する説明を全く受けておりません。もし、「事故物件」の説明を受けていれば、この住宅を購入しなかったと思います。私が、売主業者A社の担当者に、この点を問い質したところ、その担当者は、当時、多数の競売物件を担当していたので、競売資料の「事故物件」に関する記載に気が付かず、「Bの住宅内の自殺」の事実を知らなかったと述べています。又、この住宅は、落札後にリフォームした上で販売したのだから、従前の「事故物件」の事実は問題にならないと述べています。
私は、納得が行きません。売主業者A社に対し何らかの責任追及ができないものでしょうか?
A
この住宅には、「事故物件(Bの住宅内の自殺)」という嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥(隠れた瑕疵)が存在していたと考えることができます。
また、売主業者A社は、競売を経由したこの住宅の売買契約に際し、この住宅の競売資料に目を通し、重要事項の把握に務め、あなたに対し「事故物件」に関する内容の説明を行う義務があったと考えることができます。
従って、あなたは、売主業者A社に対し、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求、又は、「事故物件」に関する内容の説明を怠った過失(債務不履行、又は、不法行為)に基づく損害賠償請求を行う余地があります。
解説
1.事故物件(Bの住宅内の自殺)の事実
売買の目的物の瑕疵(民法570条)は、その目的物が通常保有する性質を欠いていることをいい、目的物に物理的欠陥がある場合だけでなく、目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥がある場合も含まれます。そして、不動産売買の目的物(住宅等)の心理的欠陥と言える為には、単に買主がその住宅等への居住を好まないだけでは足りず、通常一般人が買主の立場に置かれた場合に、住み心地の良さを欠き、居住の用に適さないと感じることに合理性があると判断される程度の欠陥であることが必要です(大阪高裁平成18年12月19日判決)。
こうした住宅の嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥は、一般的には、時間の経過やその住宅の消滅(解体・建直し)等により解消して行くことが考えられます。しかし、その住宅の嫌悪すべき歴史的背景の内容が、衝撃的なものである場合には、より長期間に亘り地域の住民の記憶に残り、解消したと考えることができない場合も考えられます。
本件の事故(住宅内のBの自殺)は、通常一般人がこの住宅の買主の立場に置かれた場合、住み心地の良さを欠き、居住の用に適さないと感じる嫌悪すべき歴史的背景の事実と言えます。しかも、本件の事故は、Bの自殺から2年経過したに過ぎず近所の住民の記憶に残っている事実から見ても、事故から2年の経過、及び、売主業者A社の住宅のリフォームだけでは、この住宅の嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥が解消したと考えることは困難と思います。従って、この住宅には隠れた瑕疵(心理的欠陥)が存在していると考えるべきでしょう。
この場合、あなたは、売主業者A社に対し、売主の瑕疵担保責任として、この住宅の心理的欠陥(隠れた瑕疵)を理由とする損害賠償を請求することが考えられます(民法570条)。
2.競売手続と「競売資料」
競売手続は、一般的には、次のような手順で行われます。
①債権者が、裁判所に対し住宅の差押、又は、抵当権者が抵当権の実行申立をすることで競売開始決定がされて競売手続が始まります。競売開始決定がされると、この住宅の登記簿(登記記録情報)に「差押」の登記がされます。従って、この住宅の登記簿(登記記録情報)を見ることで、この住宅が競売手続を経由した物件であることが確認できます。
②その後、裁判所は、執行官に対し、この住宅の調査を命じ、執行官は、この住宅の調査結果を「競売資料」にして裁判所に提出します。
「現況調査報告書」には、執行官が、この住宅に関して関係者や近所の住人等から聞き取り調査した内容などを記載します。従って、事故(住宅内のBの自殺)の情報が存在すれば、その情報も記載もされます。
又、「評価書」には、この住宅の評価額が記載されますが、その評価額の算出根拠の中には、その事故による減価の要因を考慮した市場性修正率などの記載も見られます。これらの記載内容を把握することで、この住宅が事故物件であることを認識することができます。
③裁判所は、これらの「競売資料」等を参考にして、この住宅の最低売却価格を定めて入札手続を実施します。
④そして、入札参加者は、事前に「競売資料」等を閲覧した上で、物件を把握し、価格を決めて入札を行います。そして、最高価格の入札者が裁判所の競落許可決定を受けて、代金を裁判所に納付しこの住宅を取得します。
このように競売参加者は、事前に「競売資料」等を閲覧しますので、もし、その中に事故物件に関する記載があれば、その住宅の事故物件の事実を認識することができるのです。
3.「競売資料」の概要の説明義務
売主業者A社は、競売物件を競落し転売を行うことを主たる業務としている宅地建物取引業者のようです。こうした売主業者A社には、この住宅を転売目的で落札した以上、転売先の買受人(あなた)に不測の損害を与えないよう、この住宅の「競売資料」に目を通し、重要事項の把握に務めるべき注意義務があります(重要事項の説明義務、東京地裁平成18年7月27日判決)。
売主業者A社の担当者が、事故物件に関する記載に気が付かず、「Bの住宅内の自殺」の事実を知らなかったとしても、売主業者A社は、この注意義務の違反(債務不履行、又は、不法行為)の責任を免れないと思われます。あなたは、売主業者A社に対し、債務不履行、又は、不法行為に基づく損害賠償請求を行なう余地があります。
4.損害額
この住宅が事故物件であることに伴う損害は、一般的には、この住宅の売買価格と事故物件であることを認識した上での市場価格との差額(価値減少)と考えられます。しかし、事故物件であることを認識した上での市場価格の算定は、事故内容の程度、事故からの時間の経過、取引に至るまでの経緯等様々な要素を考慮して行われます。そのため、具体的な物件ごとに判断が分かれるのが現実です。裁判実務では、その住宅の売買価格の3%~25%程度の価値減少を認めた例が見られます。
まとめ
近時、競売物件を落札後、リフォームや解体・建直しを行った住宅の販売が見受けられるようになりました。
競売を経由した物件(住宅)が、本件のように事故物件等の瑕疵を内在していることも考えられます。
競売物件を扱う業者は、「競売資料」を精査し、事故を含む様々な要素について把握し、その住宅の売買契約に際しては、買主に十分な説明を行うことに務めるべきです。一方、買主も、その住宅の登記簿(登記記録情報)を確認することで、競売を経由した物件であることを確認できますので、必ずそうした資料に基づく確認を行って下さい。
なお、競売を経由した物件を解体し建直した場合には、建直した住宅の登記簿(登記記録情報)では、その事実を確認できませんが、敷地の登記簿(登記記録情報)を確認することで競売を経由した物件であったことが確認できる場合もあります。
いずれにしても、事故物件の心理的欠陥(隠れた瑕疵)の存在は、様々な要素から判断せざるを得ないので、売買契約の前によく確認しておくことが必要でしょう。