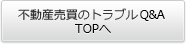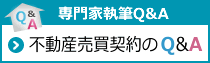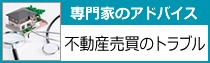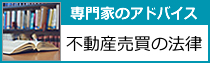安心・安全な不動産売買契約を締結するために不動産売買のトラブルが、どのような局面から生じているか、そのトラブルを防ぐには何を注意すれば良いのかを解りやすく解説しています。
戸建て住宅・マンションの売買
マイホームを購入しようと考えていますが、戸建て住宅とマンションとではどの様な違いがあるのでしょうか?
戸建て住宅とマンション(区分所有建物)は、建物の構造や権利形態が異なるため、売買の対象物や利用・管理上の制約等において違いが生じます。
1 戸建て住宅
(1)
売買の対象物
戸建て住宅の場合、売買の対象物は「地上建物」とその「敷地の所有権」です。なお、「地上建物」が「借地」上に建築されている場合には、「敷地の所有権」ではなく「借地の利用権(借地権)」を売買対象とすることになります。
この場合、借地権の売買(譲渡)には地主の承諾が必要ですので、売買契約締結前に借地契約の契約内容や地主の意向について確認する必要があります。売買契約締結前に地主の承諾が得られない場合には、地主の承諾を停止条件とした売買契約とするのが一般的です。
(2)
利用・管理上の制約
戸建て住宅の所有形態は、単独所有や親族間の共有の場合が多く、建物の利用・管理・処分は、所有者単独の意思決定、もしくは、共有者間の協議で決定できます。したがって、住宅内でのペットの飼育や楽器の演奏等は、近隣に迷惑をかけない限り、所有者・共有者の意思決定に従い自由に行うことができます。また、建物の建て替え・改修等も所有者(共有者)の意思で自由に行うことが出来ます。
2 マンション(区分所有建物)
(1)
売買の対象物
マンションは、一棟の建物の構造が「専有部分」(各住戸等)と「共用部分」(エントランス・エレベーター・階段等)に大きく分かれます。「専有部分」は、各区分所有者が所有(区分所有)し、「共用部分」は、区分所有者全員が定められた割合の持分で共有しています。又「敷地」は各区分所有者が定められた割合の持分で共有しています。なお、マンションが「借地」上に建築されている場合には、「借地の利用権(借地権等)」を各区分所有者が定められた割合で準共有しています。
従って、マンションの場合、売買の対象物は、「専有部分」の区分所有権と「共用部分」の共有持分及び「敷地」の共有持分又は「借地の利用権等」の準共有持分です。なお、これらの権利は一体として売買され、分離して売買をすることはできません。
(2)
利用・管理上の制約
ア
管理組合・管理規約等
マンションでは、区分所有者全員で構成される団体(多くは管理組合)が存在し、同団体がマンションの管理・利用に関するルールを管理規約や集会決議によって定めています。従って、マンションの利用に際しては、区分所有法等の関係法令、管理規約や集会決議の定めに従う必要があり、その内容によっては専有部分内でのペットの飼育や楽器の演奏等の利用が制限される場合があります。
また、建物の共用部分や敷地(含・利用権)は共有物であるため、その維持・管理・処分は、関係法令や管理規約等に従って行う必要があります。規約で別段の定めがない限り、①保存行為は各自単独、②管理行為及び軽微変更行為(変更行為のうち形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数による決議、③重大変更行為(変更行為のうち形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議、④処分行為は共有者全員の同意、⑤建替えは区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による決議が現行法上必要です(2025年9月末時点)。
イ
区分所有法改正(2026年4月施行予定)
老朽化したマンションの管理及び再生を円滑化する観点から、改正区分所有法が2025年5月25日に成立しました(2026年4月施行予定)。同改正法では、下記①共有部分の重大変更行為の決議や②建替え決議における多数決割合を一定の事由のもと緩和する規定の他、所在等不明区分所有者の頭数と議決権を多数決の母数から除外するしくみ、区分所有建物の管理特化した財産管理制度、建物の更新(リノベーション)決議、建物敷地売却等を可能とする新たな制度も追加されます。
①
共用部分の変更のうち形状又は効用の著しい変更を伴うものについて、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要となる原則は維持しつつ、(ⅰ)共用部分の設置・保存の瑕疵により権利侵害のおそれがある場合、(ⅱ)バリアフリー化のため必要な場合には、多数決割合が3分の2以上に緩和されます。
②
建替え決議について、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による決議が必要となるとの原則を維持しつつ、(ⅰ)耐震不足(ⅱ)火災による安全性の不足(ⅲ)外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ(ⅳ)給排水管等の腐食により著しく衛生上有害となるおそれ(ⅴ)バリアフリー基準への不適合、のいずれかの事由が認められる場合には多数決割合が4分の3以上に緩和されます。
ウ
修繕積立金・維持管理費
マンションは多数の区分所有者が共同で利用するため、共有部分や敷地などの維持管理の為に、区分所有者は修繕積立金や維持管理費等の負担をする義務があります。そのため、マンションの売買に際し、売主である前区分所有者が維持管理費を滞納していた場合には、買主は、マンションの管理組合に対し、その滞納維持管理費の支払い義務を承継しなければなりません。従って、売買契約に際して、維持管理費等の滞納の有無を調査確認する必要があります。
エ
管理規約等の事前確認
利用管理上のルールや維持管理状況等については、管理規約や総会議事録、重要事項調査報告書、長期修繕計画書等で確認することができます。管理規約や修繕計画等は、建物の管理状況により、変更決議が行われる可能性もあるため、最新の情報を取得し、マンション利用上の制約等について事前に確認することが大切です。
購入予定の戸建て住宅の敷地内には、塀や植栽があります。これらについて注意すべき点はありますか。
戸建て住宅の敷地内に存在する塀や植栽は、土地の「定着物」として、売買の目的物に含まれますが、以下の点に注意する必要があります。
1 塀
塀は、多くの場合、その境界線に沿って設置されています。通常、塀が敷地内に設置されている場合、敷地所有者が自己所有物として設置したものであり、隣地のプライバシーや日照権を侵害しない範囲で、建築基準法等の関係法規の制約のもと、自由に塀の修復・撤去等の行為を行うことができます。
一方、隣地との境界線上に設置されている場合には、隣地所有者との共有物と推定されます。境界線上に設置された塀が隣地所有者との共有物である場合には、隣地所有者と協議の上、共同の費用で維持管理することになります。
既存の塀を撤去し、隣地との境界線上に、隣地所有者との共有塀を設置する場合には、隣地所有者と協議により、塀の高さや材質等を決定し、共同の費用負担で設置することになります。共有塀について隣地所有者との間で協議が調わない場合には、民法の規定に従い、板塀又は竹垣その他これに類する材料で、かつ、高さ2mの塀を設置することになります。これより、良好な材料・高さを増すことを希望する場合には、それに要する費用を希望する側が負担することになります。塀の高さ・材料・形状は、隣地のプライバシー・日照等に大きく影響を与えるため、隣地所有者へ事前の説明を行うことがトラブル防止のために大切となります。
また、築年数の進んだ中古住宅の売買の場合、設置された塀が、いつ・誰によって設置されたのかが不明の場合や、敷地内に設置されていた塀が経年劣化や土圧等により隣地に一部越境している場合があります。塀の所有者が不明の場合、自分の意思だけで塀の改築や撤去をすることが出来ないことが想定されます。又、塀が隣地に越境している場合には越境部分を撤去する必要が生じます。このような状態の塀は、隣地とのトラブルに発展します。売買契約に際しては、境界線の位置、塀の所有者等について事前によく確認する必要があります。
2 植栽
敷地内の植栽は敷地所有者の所有物であり、根や枝が隣地に越境した場合、隣地の所有権を侵害しているとして、紛争に発展する場合があるため、適切に管理する必要があります。
植栽の根や枝が隣地に越境した場合、隣地所有者は植栽の所有者に対して、根や枝を切除することを請求することができます。また、越境している根については、隣地所有者が切除することができるとされていましたが、民法改正(2023年4月1日施行)により、越境している枝についても、隣地所有者が植栽の所有者に対し切除請求したにもかかわらず、相当期間内に切除しない等の一定の場合に、隣地所有者が切除することが認められるようになりました(民法233条)。これにより、越境した枝・根の双方について、隣地所有者が切除することができるようになりました。
隣地との境界付近に植栽がある場合には、隣地に越境しないよう定期的な管理を行う必要があるでしょう。