

「不動産価格・査定・鑑定評価等」について、不動産評価の仕組みを解説した不動産鑑定士のアドバイスです。
配偶者居住権の評価はできるのか
配偶者居住権とは
2018年(平成30年)7月6日に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました(同年7月13日公布)。この改正の施行日は、原則として2019年(令和元年)7月1日ですが、今月の表題としている、いわゆる配偶者居住権については、2020年(令和2年)4月1日に施行されます(法務省民事局:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)。
配偶者居住権の概要についても、法務省民事局のPDF(http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf)に解りやすい説明があります。
厚生労働省が発表している簡易生命表によれば、日本は、男女ともに平均寿命が毎年伸びている一方で、男女の平均寿命の差が6年あります。当職の感覚ですが、現在の高齢者夫婦では、夫の年齢よりも妻の年齢の方が低いことが多いのではないでしょうか。
そんな中、夫が先に亡くなり(相続開始。夫が被相続人)、残された妻(相続人)と子(相続人)で夫であり父たる被相続人の遺産を分割する際、妻が従前から住んでいた家を相続し…、というパターンが思い浮かびますが、法務省民事局のPDFの例のように相続財産のうちに現預金があればまだしも、無い場合には『家はあるが、生活資金がない』ということになりかねません。
そこで、相続人として残された配偶者がその後の生活に困ることのないように、今まで住んでいた家に居住しつづけることができる権利である『配偶者居住権』の制度が新設されました。
配偶者居住権は、次の要件で成立します。
① 配偶者が相続開始時に被相続人所有の家屋に居住していたこと。
② その家屋について、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈、死因贈与がされたこと。
そして、第三者に対しては、配偶者居住権の登記を行うことで対抗要件を備えることになります。
配偶者居住権の価値
遺産分割を行う場合には、全ての遺産の価値を把握しなければなりません。配偶者居住権はあくまで居住することができる権利であって、不動産の所有権ではありませんので、遺産の価値の大小は少なくとも
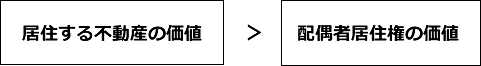
となります。配偶者居住権は土地には設定されず、建物にのみ設定されます。ただし、貸家借家と同じように、「建物だけを使うことができる」という契約に見えても、建物は土地がなければ存在しえませんし、建物利用者も土地の上に足を踏み入れなければ建物を使うことができません。したがって、配偶者居住権はあくまで建物にのみ設定されますが、土地所有者も現実には土地を自由に使用することはできなくなります。したがって、
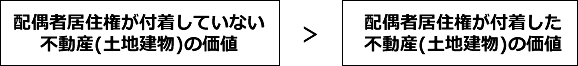
と言えます。一方で、配偶者居住権そのものは一身専属的な権利ですので、配偶者居住権を誰かに譲渡したり、貸したりすることはできません。すなわち、配偶者居住権には第三者市場が無いと言えるのですが、遺産分割では配偶者居住権も「相続財産」としてその額が必要になります。
不動産に関する権利の中には、一般的な市場性が無いが当事者間においてはなんらかの価値があるという場合があります。第三者に譲渡することができない権利の価値の判定は不動産鑑定士にとってとても悩ましい問題です。
相続税法上の配偶者居住権の価額
相続税額を把握するための配偶者居住権の価額計算方法は、相続税法を改正して定められました。
まず、配偶者居住権の価額は、
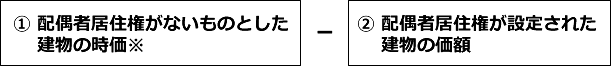
となっています。
※相続税法上の『時価』は、実際の市場価格ではなく、固定資産税評価額
②は、以下の式で求められることとなっています。
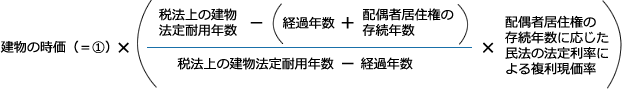
ここで、『配偶者居住権の存続年数』は、当事者が有期で期間を定めた場合には、その期間となります。では、『生涯に渡って』とされた場合はどうなるのでしょうか。
税法上は、厚生労働省の発表する簡易生命表の平均余命をもって、存続年数とされることになっています。
次に、配偶者居住権が設定されている建物の敷地である土地の価額は、
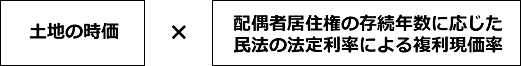
となっています。以前にも書きましたが、税法上の評価基準に基づく相続財産の評価は、あくまで課税のためのもので、評価基準を一律に定め課税の公平性を担保しようとするものです。ベースとなっている路線価や借地権割合は、第三者市場が考慮されてはいますが、路線価として表示されている価格は基準となる価格水準が実勢とは異なっています(公示価格の8割程度が一般的)し、個別の物件についての需要と供給といった市場は反映されません。したがって、相続税法上の評価額と不動産鑑定評価によって出された価額とは異なります。
配偶者居住権の鑑定評価における問題点と課題
さて、配偶者居住権の鑑定評価ですが、法律が施行される2020年4月に向けて、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会でも配偶者居住権の鑑定評価に関する実務指針を作成しようと動いています。このコラムを書いている2019年11月現在ではまだ正式には発表されていません。正確には、パブリックコメントの募集が締め切られた段階です。
遺産分割は、『法定相続分』で割合が決められていますが、当事者が法定相続分と違う割合で合意しても合意内容が優先されます。必ずしも法定相続分で決定する必要はありません。したがって、相続税法上の各評価額が必ずしも第三者市場を反映していないとしても、遺産分割のための各資産の評価額として、当事者が相続税法上の評価方法で求められた額で合意するのであれば、それはそれで有効な合意となります。しかし争訟になった場合には、やはり、税法上の時価ではなく、現実の市場を反映した時価:不動産鑑定評価が求められることになるでしょう。
理論的な配偶者居住権の鑑定評価の方法として、土地建物の価格を取引事例比較法等で求め、建物の残存耐用年数と配偶者居住権の存続期間を考慮した現在価値との差額をもって配偶者居住権の価額とする方法と、配偶者居住権がなければ得ることができたであろう賃料を想定し、その純収益の額の割引合計額をもって配偶者居住権の価額とする方法等が考えられています。割引期間は、期間が定められている場合にはその期間に応じた割引期間です。
悩ましいのは、配偶者居住権の存続年数が『生涯(終身)』とされた場合です。
生涯ということは、配偶者居住権を得た者が亡くなるまでの期間ということです。その期間は誰が判断するのでしょうか。現実(?)には、『神のみぞ知る』と言えます。相続税法上は割り切っていて、簡易生命表の平均余命をもって割引期間とするとされています。割り切らないと課税ができません。
しかし、不動産鑑定評価の場合には、不動産鑑定評価基準、価格等調査ガイドラインにより、そのような割り切りができません。
終身の場合には、相続発生時点で配偶者がいくつであっても、そこから亡くなる迄の期間を想定することになるわけです。収益還元法のDCF法で「投資家の投資期間を10年とする」ということと同列に考えるわけにはいかないと思います。平均余命よりも早く亡くなる方もおられますし、もっと長くお元気で過ごされる場合もあります。
ところで、不動産鑑定評価を行うにあたっては、想定上の条件を設けることができる場合があります。では、想定上の条件とすればいいのでは?と思われたかもしれません。不動産の鑑定評価で想定上の条件を設定する場合、鑑定評価額によって影響を受ける当事者に不利益を与えないために『実現性』が担保されている必要があります。いつかは確実に実現する、という意味では都市計画道路の計画よりも実現性は高いと言えますが、『いつ』という期間を決めることができなければ、評価上必要な割引期間を設定することができないのです。
それでは、仮に当事者が争っておらず、『終身の配偶者居住権を設定します。鑑定評価の計算上は終身の居住権の存続年数は簡易生命表を前提にしていいですよ』という合意があった場合はどうでしょうか。この合意を前提に想定上の条件〔居住権の存続期間は簡易生命表を前提とする〕を設定することはできないと考えます。そもそも簡易生命表を用いた計算式を当てはめるという部分については、不動産鑑定士でなくとも可能な作業です。この場合の不動産鑑定士の役割としては、その不動産の配偶者居住権が設定されていない場合の時価を求めること、その不動産に配偶者居住権が設定されるとした場合の、想定年毎の配偶者居住権の価格水準(この場合はコンサルティング)を提示する、ということになるのではないかと考えています。
しかし、裁判所をはじめとする法曹界からは、配偶者居住権の『鑑定評価』が必要な場合があると言われています。不動産鑑定士の業界でも期間を喫緊の課題として検討を重ねています。施行日は2020年4月です。何か進展があればまたお伝えしたいと思います。
ありがとうございました。








