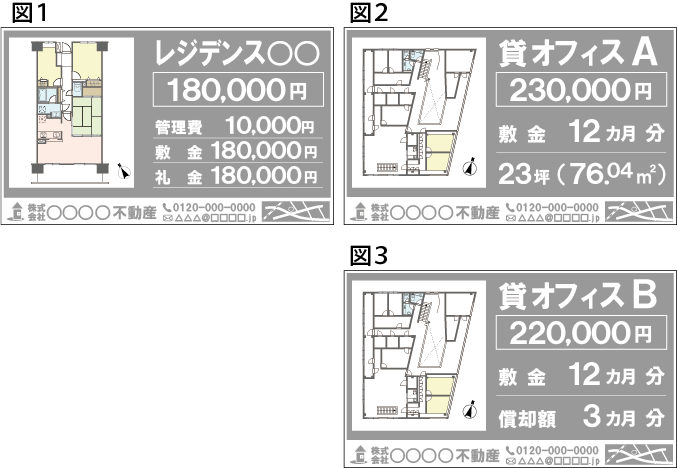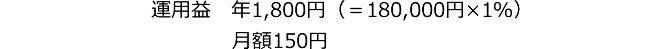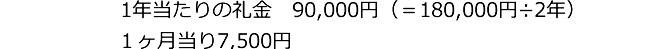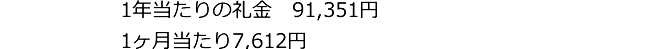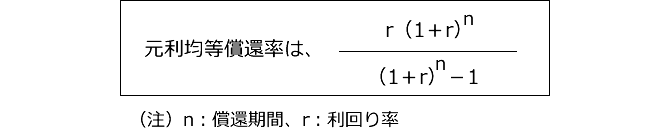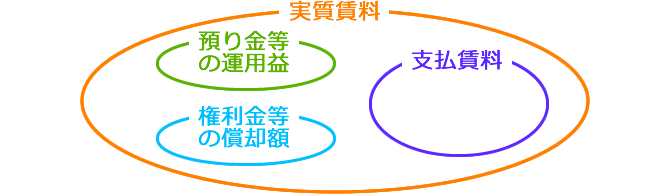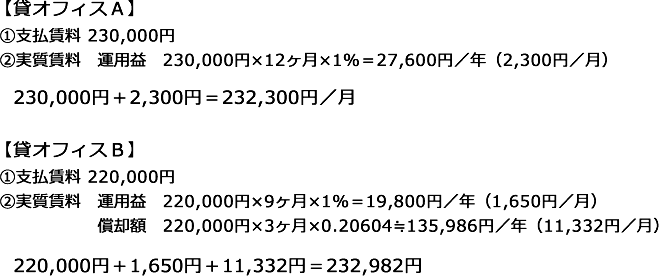「不動産価格・査定・鑑定評価等」について、不動産評価の仕組みを解説した不動産鑑定士のアドバイスです。
家賃の評価~評価の前に確認していること~
2019年最初のコラムは、「家賃の評価」についてです。
■家賃の評価の際、確認していること
家賃の評価を依頼された時には、次のようなことを確認しています。
(1)新規賃料か、継続賃料か
(2)支払賃料か、実質賃料か
(3)建物全体か建物の一部分か
(4)建物の種類(用途)
(5)価格時点(期間の期首)
■(1)新規賃料か継続賃料か
新規賃料と継続賃料については、2018年3月のコラムで詳しく書いています。簡単に言うと、①新規賃料は、これから新たに賃貸借を行う場合の賃料で、②継続賃料は、同じ借り主・貸し主のまま、賃料の額以外の契約内容を継続することを前提とした賃料です。
■(2)支払賃料か、実質賃料か
①支払賃料と②実質賃料
①支払賃料と②実質賃料については、2017年12月と2018年3月に触れていますが、おさらいすると、①支払賃料は、契約で決められた支払時期(毎月何日や毎年何月など)に借り主が貸し主に支払う賃料のことで、②実質賃料は、支払賃料とは別に、保証金、敷金、権利金、礼金などの名目で借り主から貸し主に払われるもの(以下、「保証金等」)の運用益や償却額を支払賃料に加えた額のことを言います。
賃貸マンションや賃貸事務所の広告を見てみましょう。
例えばレジデンス○○や貸オフィスの広告で、「このマンションやオフィスの家賃はいくらか?」と訊かれた場合、皆さんは通常、「マンションは180,000円、オフィスは230,000円」と答えるのではないでしょうか。この「180,000円」、「230,000円」が①支払賃料です。
マンションの敷金180,000円は、入居する時に借り主から貸し主に支払われ、将来借り主が退去するときには貸し主から返ってくるものです。つまり、賃貸借の契約期間中、貸し主に預けているのですが、預けているからといって、銀行預金のように利息がつく契約になっているものはほとんどみられません。しかし、貸し主からすると、借り主から預かっている間に敷金をなんらかの形で運用すれば、運用益を手に入れることができます。
上記マンションの例で、敷金を年1%で運用できたとすると、
そして、礼金は、借り主が退去するときに借り主に返還しなくてもいい性格のものです。したがって、貸し主は借り主が不動産を借りている期間に応じて、礼金を運用しつつ自由に使うことができます。
例えば、入居期間が2年間であれば、
という計算になります。
しかし、敷金と同様に運用することもできますので、180,000円を1%で運用することも考慮すると、
となります。ある額を運用しながら償却する時の1年当たりの償却額は、元本に元利均等償還率(年賦償還率とも言います)を乗じます(≒180,000円×0.50751)。
この敷金の運用益150円と礼金の償却額7,612円は、借り主から貸し主へ直接毎期支払われているものではありません。しかし、少なくとも毎月(毎期)支払っている額以外の金銭から発生しているものであり、借り主が貸し主に預けた金額を手元に残しておいたなら、借り主も同じ額の運用益や償却額が得られたはずのものです。そこで、これらも「実質的に賃料」という意味で、①の支払賃料にこれらの運用益、償却額を加算したものを②実質賃料と呼びます。
まれに、「支払賃料は借り主側からみた賃料、実質賃料は貸し主側からみた賃料」という説明を聞くことがありますが、そうではなく誰からみても支払賃料は支払賃料、実質賃料は実質賃料だと思います。
ところで、不動産鑑定評価基準によれば、不動産鑑定士が求める賃料は原則として「②実質賃料」となっています。①の支払賃料は求めることが「できる」となっています。
ある不動産の賃料を比べるとき、①支払賃料を比較するだけでは実質的な利益や負担を比較することができないからです。
上記の貸オフィスAとBを比較してみます。
広告の物件【貸オフィスA】では、月額230,000円、敷金12ヶ月となっています。
同じ広さの【貸オフィスB】は、月額220,000円、敷金12ヶ月、償却※3ヶ月です。
※「敷金」は、全額が預り金の場合と、一部返還しない額を含む場合があり、関東では敷金のうち借り主に返還しない額を「償却」と呼びますが、関西では「敷引」と呼ぶのが一般的です。
運用利回り 1%とし、入居期間5年、敷金のうち返還される部分は退去時まで無利息とします。
貸オフィスAと貸オフィスBでは、①支払賃料は、【貸オフィスA】>【貸オフィスB】ですが、②実質賃料は、【貸オフィスA】<【貸オフィスB】となっています。このように、①支払賃料だけで比較すると、賃借人も賃貸人も実質的に支払ったり受け取ったりしている額の比較ができないのです。
鑑定評価では「原則として実質賃料を求める」となっているため、注意していること
また、鑑定評価基準によれば、「保証金等の条件(何ヶ月分預かるのか、返還するときまで無利息で預かるのか否か、返還しない金額があるか否か等)が示されて、支払賃料を求めて欲しいといわれた場合には実質賃料と共に支払賃料を求めることができる」となっています。支払賃料の鑑定評価額とともに実質賃料も記載しなければなりません。
しかし、一般的には「月額(または年額)いくら支払うのか、保証金等は何ヶ月分払うのか」という点について分けて考えるのではないでしょうか。実際、保証金等の運用益や償却額を含む②実質賃料のみの鑑定評価依頼はほとんどありません。
新たに貸すために賃料の評価が必要となったが、保証金等の月数はまだ決めていない(後で決める)というようなケースがまれにあります。この場合は注意が必要です。
保証金等の契約内容が決まっていない場合、②実質賃料を求めることになります。鑑定評価額は『毎期支払う①支払賃料ではない』ということを依頼者の方によく理解していただかなければなりません。「月額(または年額)いくら支払うのか、保証金等は何ヶ月分払うのか」と考えるのが一般的ですので、「保証金等の契約内容が決まっていない場合の鑑定評価額は②実質賃料」ということを理解していただくのは案外大変です。そして、きちんと理解していただけていないと、「実質賃料は、保証金等の運用益及び償却額を含むもの」であるにも関わらず、「実質賃料として鑑定評価された額(月額)の何ヶ月分かを保証金として預かる、あるいは権利金として受け取る」という賃貸借契約を考えてしまうのです。
このコラムを読んでいただいた方は、このような契約だと、「運用益及び償却額を2重に受け取ってしまうことになる」ということがおわかりだと思います。契約自由の原則ですので、借り主・貸し主が相互に合意すればかまわないとも言えるのですが、鑑定評価書を取得していただく理由が各方面への説明資料であった場合には、設定された賃料の額が鑑定評価額から説明できないということになりかねませんので、①支払賃料と②実質賃料の違いを最初に丁寧に説明する必要があります。
■(3)、(4)については、2018年12月のコラムをご参照ください。
■(5)価格時点
価格時点は必ずしも「今」とは限りません。鑑定評価は将来の価格や賃料を評価することは原則としてできませんが、過去に遡って賃料を改定したい(特に調停や裁判など)場合等には、過去の時点の賃料を求めることになります。
(1)~(5)は全て確認する事項ですが、(1)から(5)の順番に確認しなければならないというものではなく、それぞれの確認の過程で行ったり来たりしながら確定することになります。
なかなか進みませんが、本年もよろしくお願い致します。