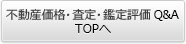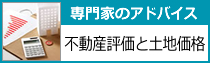不動産、特に土地は、目の前に示されている価格がなぜその価格になるのかがわかりにくいと思います。そのような、わかりにくい不動産の価格について、少しでも理解を深めていただけるように解説しています。
不動産の鑑定評価が有用な例
500㎡の土地だと、総額が大きくなりますので名声のある住宅地ではないような一般の住宅地では個人の買い手はなかなか現れないことが多いです。しかし、土地の分割に関して公法上の規制がないような場合で、土地を分割してそれぞれの区画に建物を建てることができるような場合には、分割後の区画あたりの単価を高くしても、総額の面から個人の買い手が多く見込めることがあります。また、建売住宅分譲を行おうとする不動産会社の場合には、原価に土地の仕入れ価額だけではなく販売建物の建築費や塀等の外構工事費などが含まれるので、建築費等で費用を調整することができるため、土地を多少高く仕入れても採算が合う場合があります。ただし、元の土地の道路への接面状況や形状、規模などによって異なりますし、利益幅を大きくするために、安い価格で提示されることもよくあります。
不動産開発業者は、完成した宅地(整地して道路等を配置し、区画を分けた後の宅地)の販売価格の総額を予測し、工事費用や道路等として使われるために分譲できない部分を差し引いたり、購入から分譲が完売するまでの期間なども計算した上で、価格を提示します。周辺の宅地として直ぐに使えるような土地と比較すれば、かなり安くなることが通常です。安くなる割合は、元の土地の道路への接面状況や形状、規模などによって異なります。客観的な価格を把握する必要がある場合は、不動産鑑定士に評価をご依頼下さい。
相続する資産に現預金が少なく、不動産が多い場合です。不動産を等価で均等分割する場合は同じ価値になるように建築法規等に留意し、分割計画をたてなければいけません。元の不動産の価格、分割後の不動産の価格が必要な場合は鑑定評価が有用です。
なお、登記面積が実際の面積と異なっている場合には、それが原因で後にもめることもありますので、土地家屋調査士等の専門家に依頼して測量を実施することが望ましいです。また、土地を分割する登記を行うことになった場合には、土地家屋調査士に分筆図面の作成を依頼する必要がありますが、その場合には基の全体の土地も測量する必要があります。
いずれにしても、土地の形状等が悪い場合など必ずしも等価の分割ができず、分割することにより、元の全体の価額よりも分割された土地価額の合計が低くなってしまうこともあります。
借地権と底地はそれぞれ独立して売買の対象となります。借地権は法的側面からみると、借地借家法(旧借地法を含む)によって最低存続期間が保証され、定期借地権を除き、契約期間が経過しても借地権設定者( 地主) に更新拒絶のための正当事由がない限り借地契約は更新されます。また第三者へ譲渡も可能であり、権利の強化、安定化が図られています。また、経済的側面からみると、土地の効用または利用価値が増大することによって地価が上昇しても、地代は地価の上昇ほどは値上げが困難なことから、低いままであることが多く、その様な場合には借地権者が経済的な利益(地価が高い場所を安く借りているという利益)を享受していることになります。借地権の価格は、こうした法的側面、経済的側面から生じている借地権者の利益に着目して、不動産取引市場において借地権の売買が一般化、慣行化していくことによって形成されてきたものです。なお、借地権が単独で取引の対象となっている地域もありますが、関西では、借地権が単独で取引の対象とされる慣習は殆どなく、借地権付建物として取引されています。
一方、底地は、前述したとおり、借地借家法により正当事由制度と法定更新制度が適用されますので、正当事由が認められない限り、借地契約を終了させることは事実上できず、自ら土地を自由に使用することができません。地代を受領する権利に相応する価格が中心となります。ただし、このほかに将来更新料などの一時金が見込まれる場合や借地権がなくなることによって土地が更地になって帰ってくる可能性が高い場合にはその価値が加味されます。
借地権、底地それぞれ固有の価格形成要因によって個別に価格が形成されるため、現実の不動産市場における借地権単独の価格と底地単独の価格の合計は、必ずしも更地の価格とは一致しません。借地権の価格と底地の価格は、更地の価格を単純に配分されるものではないのです。通常は、「更地価格>(借地権価格+底地価格)」となります。
ただし、地主と借地人とが共同して借地権と底地を一緒に第三者に売却する場合は、購入者(第三者)は更地化が可能になるため、更地の価格で売却できる可能性がでてきます。
国税庁が相続税を課税する場合に財産を評価する基準として財産評価基本通達があります。この財産評価基本通達では、借地権の価格は、更地価格(路線価)×借地権割合、この更地価格を1とすると、底地価格は1-借地権割合で求めます。すなわち、財産評価基本通達で算定すると、底地価格は更地価格から借地権価格を控除した残り全てということです。この借地権割合はあくまで課税の公平性、迅速な事務処理対応に主眼をおいて一律に定められているものです。
借地権割合は、更地価格に対する借地権価格の割合を指します。借地権が単独で取引の対象となっている地域では、更地価格に対する借地権価格の割合の相場が形成されている場合もありますが、必ずしも財産評価基本通達に基づく借地権割合と一致するとは限りませんので注意が必要です。また、借地権が単独で売買されることがない地域ではそもそも借地権割合の相場はありませんので、更地価格に借地権割合を乗じるという方法ができません。また、現実には不動産市場における借地権単独の価格と底地単独の価格の合計は、必ずしも更地の価格とは一致しません(上記【Q 相続により貸地(底地)を所有しています。借地人から第三者へその借地権を売却したいとの申し出がありましたが、地主の私が土地を手放してもいいのであれば、私の底地と借地権を一緒に売却しませんかとも提案がありました。その方が高く売れるとのことです。本当ですか?借地権と底地の価格とはどのようなものですか?】参照)。
相続税の額の把握のために財産評価基本通達による借地権割合を用いて土地価格を算定することや、売買両当事者がその割合を用いて算定した額を取引価格とすることに合意している場合は有用ですが、正確な価値を示しているとは言えないことに注意する必要があります。
いわゆる借地借家法第2条に規定される建物所有を目的とする賃貸借の場合(大部分がこれに該当します)は、賃借権を譲渡するにあたって土地所有者の承諾を得る必要があります。承諾なしに売却された場合には契約が解除できます(民法第612条)。
ただし、その譲渡が特に土地所有者の不利益にはならないにも関わらず土地所有者が譲渡を承諾しない場合、裁判所は土地所有者に代わって売買の許可を出す事ができます。
土地所有者は、財産上の給付(金銭の受領)を受けて、裁判所が決定した許可を受け入れる事になります。
一方、借地人が裁判所に賃借権の譲渡の許可を申し立てた際に、一定期間内に土地の所有者が自ら建物及び賃借権の買取等を申し立てる事が可能となります(借地借家法第19条)。
その結果、建物を買い取る事となりますが、買い取る際の価格としては建物の物理的な価格に借地権価格相当額が加算されます。
店舗建物の所有を目的とする借地権と思われます。まず、借地権の存在は必ずしも借地権価格の存在を意味するものではない点に注意が必要です。例えば、相当程度高額の地代を払って土地を借りている場合には、この借地権をお金を出してまで購入したいと考える人は少ない(いない)のが一般的です(一部希少価値のある土地を除く)。
①については地主に借地権を買い取ってもらうのは難しいと考えます。なぜなら、借地人の都合で勝手に土地を返却するのであって、当該事情は通常地主には関係ないからです。したがって、地主から建物を除去し更地で返還することが求められます。
②は第三者への売却自体は可能ですが、このことについて地主の承諾が必要となり、かつ、地主から名義書換料を要求される可能性が高くなります。
売却価格は、上記で述べたとおり、地代の金額(大小)により大きく左右されることになります。また、借地権価格は、当事者間の契約内容によって金額も大きく異なるため、専門家である不動産鑑定士に評価を依頼することをお勧めします。
契約の更新には「合意更新」と「法定更新」があります。前者は、当事者が更新するか否か、借地条件の見直しなどを話合い、合意によって更新すること言います。後者は、借地条件の改定について当事者で特に話し合いをしなくても法律によって借地契約が自動的に更新されることを指します。
更新料は、借地契約の期間が満了して更新時期を迎える際に、借地人から地主へ支払われる一時金で、その名目が「更新料」と呼ばれているものを指します。実は、更新料は明確な法的根拠がなく、借地契約時に「更新時における更新料支払いに関する特約」がある場合等を除いて、支払わなくても契約違反にはなりません。しかしながら、次のような理由で更新料の授受が行われていることがあります。
- ・地価上昇に対して地代は低く抑えられている傾向にあるので、契約期間中の地価上昇率と比較して上昇しなかった地代部分との差額一括払い
- ・地主の将来の更新拒絶を回避してスムーズに借地契約を更新するための一種の保険料的なもの
- ・単に慣行として払うべきものだと思っている等
更新料の支払額は、借地権価額の5%~10%、更地の価額の3%~8%くらいと言われていますが明確なきまりはありません。
住宅の場合、通常50年程度で更地で返還しなければなりませんので、子孫の代まで住む事はできなくなります。また、定期借地権の価格は更地価格に比べて安いですが、地代は払い続ける必要があります。さらに土地に対する権利が脆弱であるため、途中で転売しようにも、売れないもしくは価格が極端に安くなるリスクがあります。これらを不利益と考えるか否かは人それぞれですが、所有権の土地付建物をロ-ンで購入する事と比較して、余裕資金ができ、かつ敷地が広く、良質な住宅に居住できる事を重視するなら、不利益とは言えないかもしれません。
旧借地法もしくは現行の借地借家法の普通借地に該当する借地契約であれば、原則立ち退く必要はありません。土地所有者がどうしてもその土地が必要でかつ相当の対価(立ち退き料)を支払った場合(これらを正当事由という)は、立ち退きが認められる場合があるので、立ち退く際はいずれにしても相当の対価は請求できる可能性は高くなります。一概には言えませんが当該土地の借地権価格相当がその目安となります。
現実の不動産は同じ物がないため、本来一律には評価できるものではないのですが、相続税の申告にあたっての土地評価は、一律の基準で行われます。しかしあくまで課税する対象の時価に対して課税することが前提ですので、一律の基準を用いることでは時価から相当乖離した価格しか算定できないような強い個性を持つ土地の場合には、鑑定評価を行うことが有用な場合があります。
不動産鑑定士が行う鑑定評価上、厳密には「簡易鑑定」はありません。「価格等調査」と呼ばれるものがあります。価格等調査と鑑定評価では、算出される価格は異ならない場合が多いのですが、価格等調査の場合は、市場分析内容の簡略化、評価手法の一部省略等により価格を求める場合も多いため、正式な鑑定評価を取った場合とで評価額が異なる場合もあります。
よく聞かれる質問なのですが、どちらが得かとの結論はありません。購入した場合、ロ-ンが終わった定年後の生活は安心ですが、借り入れが多額の場合、ロ-ン支払中の生活は困窮する場合があります。一方、生涯賃貸を選択した場合、就労中の生活は一定の余裕があるかもしれませんが、定年後の年金生活中も賃料を支払う必要があるため、不安に思われるかもしれません。居住物件の条件が同等とした場合、購入の場合の金利を含めた支払総額と、金利なしの一生涯賃貸の場合の支払総額はほぼ変わらないといった試算結果もあります。従いまして、このQの答えとしては各人のライフスタイルに合わせて、購入、賃貸を選択すればよいとなるのです。
まずは買うタイミングを考える必要があります。第一に住宅ロ-ンを組む場合、金利が低いのはもちろんですが、将来の転売も視野に入れる場合には値下がりするリスクを考慮する必要があります。価格が値下がりするか否かは、誰しも判断に困るところですが、過去の不動産バブルの経験を踏まえ、色々な指標を注視することで推測する事は可能かもしれません。例えば
①前出の地価公示標準地、地価調査基準地、相続税路線価等公的指標の価格もしくは変動率の一定期間の推移
②不動産向け融資に対する残高の推移
③不動産取引利回りの推移
④株価(日経平均株価等)の推移、などの指標です。
①は時系列で連続した指標として用いることができます。例えば購入予定の不動産に近接する地価公示標準地等の直近10年間の価格が連続して上昇しており、まだまだ上昇する地域(高級住宅地、駅前商業地など)、不動産の種類(タワーマンション、都心収益物件など)もあるでしょうし、まったく上昇せず、逆に下落する地域(地方の商店街など)、不動産の種類(別荘地など)があるなど、画一的な判断はできませんが、トレンドを捉えることができます。
②は国内の総融資額残高の伸び以上に、不動産に対する融資額残高が増加すると、いわゆる総量規制が実施されるかもしれないとの予測が可能になります。これは1990年3月に当時の大蔵省から金融機関に対して行われた行政指導で、もともとバブル状態であった不動産市場がこの指導を契機にバブルが崩壊することになりました。
③は不動産投資家調査により日本不動産研究所*1が半年に一度、アセットマネージャーや開発デベロッパー、商業銀行などプロの投資家に向けた意識調査をしています。この指標も継続して公表されているもので、所在、種類毎の投資家の期待利回り等が公表されていいます。この利回りはヒアリングに基づくものですが、実際の取引でも参考にされており、不動産鑑定士の評価にも活用されるなど規範性の高い数値となっています。この利回りが数年にわたって低下している場合、不動産の取引価格は上昇傾向を示します。この利回りが国債の利回りと近接してきた場合には、バブルの予兆と警戒することができます。
④株価(日経平均株価等)の推移については、株価が高騰を続けた場合、一定のタイムラグはありますが、不動産価格も上昇する傾向にあるためです。したがって、相対的に情報が豊富で透明な市場を有している株価がバブル状態にあるとの兆候が出た場合、数年遅れかもしれませんが不動産価格もバブル状態になりつつあると予測することができます。
このように、不動産の価格は経済情勢と密接に連動しておりかつ複雑な要因が絡み合っているため、買い時を判断するためには常時様々な情報収集を行うことが欠かせません。買い時を次に検討が必要なのは、ご自身のライフスタイルに合わせた物件を探す事です。つまり、サラリ-マンの方で転勤も考えられる方は、転勤時も管理がし易く、場合によっては短期的な賃貸も可能なマンションを選択し、転勤のない自営のかたは管理・賃貸の観点ではなく、長期的な資産形成もしくは定年後の住環境をも重視して、環境良好な住宅地を選択する、などです。
以上のようにマイホ-ム購入は人生において最大の買い物であることは間違いないのですが、一方で、各人のライフスタイル等によりその選択枝は様々です。
2023年中までは、相続税対策として有効と言われていました。その理由としては、次のようなものを挙げることができます。通常、タワーマンションの販売価格や売買価格は、上階ほど高価となりますが、相続税評価額はそうではありません。マンションを構成する土地と建物は、土地は土地、建物は建物として評価額が計算されます。相続税の課税のための建物の評価額は固定資産税評価額がその評価額となっていました。この、建物の固定資産税評価額は、実際に売買される価格と異なり、建物の階層によって単価が変わることはなく、どの階であっても同じ単価を専有面積に乗じて決まっていたのです。しかし、2023年中までの相続税評価の方法では、相続税評価額が市場価格の半分以下となっているものが3分の1近くあったこと、タワーマンションの実際の販売価格や売買価格の単価は、下層階と上層階とは価格に大きな差が生じていることが多いということを、国税庁はサンプル調査によって把握し、居住用分譲マンションの相続税評価額の評価方法が2024年1月1日から変わることになりました。今度の改正では、土地も建物も上層階と下層階では上層階の方が価格は高くなります。
なお、2017年1月2日以降に新築の、高さ60m(概ね20階建)を越えるマンションは、建物の固定資産税の額が階層別専有床面積補正率を用いて計算されることになったため、固定資産税の額は下層階よりも上層階の方が高くなることになりました(例外あり)。しかしその差は最大10%程度ですし、また、相続税の課税上用いられていた建物の固定資産税評価額自体は変わっていなかったため、2023年中までは、上層階を購入することによる相続税の節税効果はないとまでは言えない状況でした。
また、マンションの敷地(土地)については、相続税評価額も固定資産税の課税のための評価額も、マンションの敷地全体の価格を土地の敷地権割合等で按分して各戸の評価額が決まることが一般的でした。しかし実際には、マンション等で区分された建物の専有部分は、敷地の上下の空間のどこかに位置しています。実際の市場では上層の方が下層よりも空間の価値は高くなっていますので、土地についても、下層階よりも上層階の方が、売買価格と課税上の評価額との開差が大きくなり、また同じ地価水準の地域であっても、階数が高く、総戸数が多いマンションほど各戸の土地の持分は小さくなり、土地の評価額も小さくなっていました。しかし、相続税評価額については、2024年1月1日から土地についても上層階は下層階よりも高い評価額となるように計算方法が変更になりました。鑑定評価で用いる階層別地価配分比率や階層別効用比率の試算方法と異なってはいますが、考え方を反映した計算方法となっています。
ただ、タワーマンションの多くは利便性の高いところに立地しており、賃貸需要も堅調ですので、賃貸することにより、貸家として相続税の評価額は下がる事になります。タワーマンションは、このように相続税評価の評価減が大きい上に、賃貸・売却もスムーズであることが一般的ですので、低リスクで運用益もある換金性の高い優良資産として、依然人気があります。
ただし、購入のタイミングなどから相続税の極端な節税が目的であると明らかな場合には、国税当局から、その相続財産の相続税評価額は原則的な額ではなく、購入価格等で計算すべしとされる場合や、国税庁が鑑定評価に基づく時価を把握し、その額が妥当と判断された判例が出ていますし、天井の高さや付帯設備の程度に応じて固定資産税が高くなることもありますので、注意が必要です。また、節税効果がより高いといわれていた高層階は、分譲時にはプレミアムから高値で販売されているため、転売時には大きく値下がりするが、中層階は分譲時からの値下がりが少ない(マーケットでは中層需要が高い)といった事もありえます。したがって、タワーマンションを購入する場合には、税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談のうえで相続税対策を行った後、実際に売買するときの値下がりリスクの有無も考慮する必要があります。