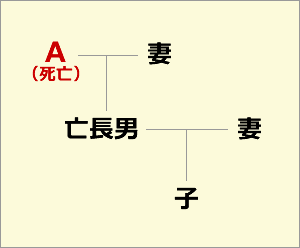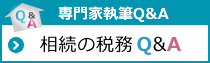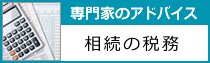相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。
遺言
遺言とは、人が自分の死後のことについて最終意思を一定の方式のもとで表示するものです。
遺言は一定の方式に従わなければならないと定められており、遺言の方式には、普通方式としての自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類があるほか、特別方式としての病気その他の理由で死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、船舶中の者の遺言、船舶の遭難により死亡の危急に迫った者の遺言があります。
自筆証書遺言をするには、遺言者がその全文と日付および氏名を自書(自分で書くこと)し、これに押印をしなければなりません。
自筆証書遺言の利点は、誰にも知られずに簡単に作成でき、費用もかからないことにありますが、方式不備による無効や偽造・紛失などの危険があります。
自筆証書の文章に訂正を行う場合には、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。
このように、自筆証書遺言には有効となるための方式が定められており、この方式に違反する遺言は原則として無効になります。しかし、遺言書の日付が平成27年6月31日などと存在しない日が記載されていたとしても、その程度の軽微な方式の瑕疵のみでは自筆証書遺言は無効とはならないと解されています。
上記のとおり、自筆証書遺言は、原則として遺言者がその全文と日付および氏名を自書しなければなりませんが、平成30年改正法により、自筆証書遺言に添付する財産目録だけは、自書しなくてもよいことになりました(平成31年1月13日施行)。これは、複数の不動産等、多くの財産を所有する人が自筆証書遺言を作成する場合、財産目録を自書しなければならないとすると、財産目録の作成に手間がかかり、簡単に作成できるという自筆証書遺言の利点が失われため、財産目録だけは自書しなくてもよいこととし、方式を緩和したものです。
ただし、自書しなくてもよいのは、あくまで財産目録だけであり、その他の部分は、全て自書しなくてはなりません。
具体的な方法としては、パソコンで財産目録を作ってプリントアウトする、第三者が代筆する、不動産の登記事項証明書を添付する、預貯金通帳等のコピーを添付するなどが考えられます。
また、財産目録を自書しなくてもよいとしたことから、偽造等を防止する必要があるため、改正法では、自筆証書遺言に添付する財産目録を自書で作成しない場合には、遺言者は、財産目録に用いた紙等の全て(一枚の紙等の表と裏に自書ではない記載がある場合には、その両面)に署名捺印をする必要があると定めています(具体的なイメージについては、法務省のHPにある画像を参照してください。)。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録を自書で作成しない場合でも、この財産目録を加除訂正する場合には、本文と同じ方法をとらなければなりません。
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを文章にまとめて公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
公証人は、法務大臣が任命する公務員で、裁判官や検察官を退官した人など長年法律関係の仕事をしていた人たちです。
公正証書遺言は、原則として、遺言者が公証役場に出かけて行き、公証役場で作成してもらいますが、遺言者が病気などのために公証役場に出かけることができないときは、公証人に自宅、病院、施設などに出張してもらい、公正証書遺言を作成してもらうこともできます。
公正証書遺言をするためには、証人2人が必要です。証人となってくれる人が思い当たらないときは、日当が必要ですが、公証役場で紹介してもらうこともできます。
公正証書遺言のメリットは、次のとおりです。
・
方式の不備で遺言が無効になるおそれがない。
・
内容的に適正な遺言が作成できる。
・
自筆証書遺言に比べて、遺言が無効と主張される可能性が少ない。
・
遺言が破棄されたり紛失したりするおそれがない。
・
家庭裁判所の検認手続が不要である。
・
体力が弱ったり病気のため自書が困難で自筆証書遺言を作成できないときでも作成してもらえる。
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま遺言が存在することのみを証明してもらう遺言です。
秘密証書遺言をするには、次の方式に従わなければなりません。
(1)
遺言者がその証書に署名押印すること。
(2)
秘密を守るため、その証書を封書に入れて証書と同じ印鑑で封印すること。
(3)
公証人・証人2人の前に封書を提出して、自己の遺言書であることと氏名・住所を述べること。
(4)
公証人が証書を提出した日付と遺言者の遺言書である旨の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人とともにこれに署名して印を押すこと。
自筆証書遺言と異なり、遺言者が遺言内容を自書する必要はありません。ワープロ打ちでもいいし、他人に書いてもらったものでもよいのです。
また、こうして作成された遺言書は公証役場で保管されるわけではなく、自分で保管します。
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容について秘密にしたまま、その存在のみを明らかにできることと、密封されたまま公開されないので、偽造や隠匿のおそれが少ないことです。
ただ、手続が面倒で、公証人に支払う費用もかかること、公証人は遺言書を保管してくれるわけではないことなどから、実際上はあまり利用されていません。
遺言を有効に行うことができるためには、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識することのできる能力を有することが必要です。これを遺言能力といいます。
民法は、15歳に達した者は遺言をすることができると定めています。したがって、未成年者であっても15歳に達していれば有効に遺言をすることができます。
契約などの一般の取引行為は原則として18歳以上でなければ行えないとされていることに比べて、ある程度低い能力でもよいとされているのです。
こうした遺言能力が備わっていたがどうかに関し、高齢者や精神障害者の行った遺言について、遺言能力がないとして無効ではないかがしばしば争われます。
遺言を行う時点で、高齢者や精神障害者の精神状態の程度がこの遺言能力を有していたといえるかどうかにより、遺言の有効無効が決まります。
成人であっても、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが困難な場合があります。このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するために成年後見制度というものがあります。
法定の成年後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、これらの保護を受ける人を、被後見人、被保佐人、被補助人といいます。
判断能力が欠けていることが通常の状態の人は被後見人となり、判断能力の著しく不十分な人は被保佐人となり、判断能力の不十分な人が被補助者となります。
Q 遺言を有効にするために必要とされる能力はどのようなものですか?で述べたように、遺言能力は取引上の行為能力(財産上の有利不利を理解する能力)よりも低い程度の能力で足りるとされています。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の行為能力を制限する民法の規定も遺言には適用されません。
したがって、遺言者が成年被後見人であっても、遺言時に遺言能力が回復していればその遺言は有効です。
ただし、成年被後見人の遺言については、その真意を確保するため、医師2人以上の立会いなど一定の手続が定められています。
民法は、次の場合の遺言は無効となると定めています。
(1)
遺言能力を欠く場合(民法961条・963条)
(2)
方式違反の遺言(民法960条・967条以下)
(3)
後見人の利益となる遺言(民法966条1項)
(4)
2人以上の者が同一の証書でした遺言(民法975条・共同遺言の禁止)
これ以外にも、不倫相手への遺贈などは、場合により公序良俗に反し無効とされることがあります。
遺言が効力を生じるのは遺言者の死後の法律関係です。そのため、遺言により法的効力が認められる範囲は一定の事項に限定されています。
1 遺言によってのみ認められる事項(必要的遺言事項)
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・相続分の指定・指定の委託
・遺産分割方法の指定・指定の委託
・遺産分割の禁止
・相続人相互の担保責任の指定
・遺言執行者の指定・指定の委託
(遺言執行者とは、遺言の内容を適正に実行させるために選任される者です。)
・遺贈の減殺の割合に関する指定
2 遺言によっても生前行為によってもできる事項(任意的記載事項)
・贈与
・一般財団法人に対する財産の拠出
・信託
・認知
・推定相続人の廃除・取消し
・生命保険金受取人の指定・変更
3 法律の定めはないが遺言の効力が認められる事項(有益的遺言事項)
・祭祀承継者の指定
・特別受益の持戻免除
4 遺言書に記載しても法的効力を生じないもの(無益的記載事項)
相続人への感謝・生前の思い出・希望など
遺言者は、いつでも遺言を撤回することができます。遺言を撤回するときは、「遺言の方式に従って」行わなければなりません。
また、次の場合は、遺言が撤回されたものとみなされます。
1
前の遺言と内容的に抵触する遺言があらたに作成された場合
たとえば、旧遺言では、「甲土地をAに相続させる」と書いていたのに、新遺言では「甲土地をBに相続させる」と書いていた場合、旧遺言は撤回されたものとされます。
2
遺言の内容とその生前の処分とが抵触する場合
たとえば、遺言では、「甲土地をAに相続させる」と書いていたのに、その後に甲土地をBに生前贈与したという場合は、遺言の内容と生前処分とが抵触しますから、遺言は撤回されたものとされます。
3
遺言者が故意に遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合
死後に自己の財産を誰に取得させるかを決めておくためには、通常は遺言を作成しますが、これとは別に死因贈与というものがあります。
死因贈与とは、「自分が死んだら家をあげる」など、贈与者の死亡を条件とする贈与契約です。
死因贈与は、無償で財産を第三者に与え、かつ死亡により効力が生じることから、その経済的意義は遺贈に類似します。そのため死因贈与には遺贈に関する規定が準用されます。
そこで、贈与者より先に受遺者(死因贈与を受けた者)が死亡したときは、遺贈と同様死因贈与の効力は失われます。また、死因贈与が書面によってなされても、贈与者はいつでもこれを取り消すことができますし、死因贈与の目的物を贈与者が生前に他の者に譲渡したときは、死因贈与は撤回されたことになります。
しかし、遺贈が遺言者の遺言という単独の行為であるのに対し、死因贈与は贈与者の意思だけでなく相手方の受諾を要件とする契約行為であるという違いがあります。そこから、次のような違いが生じます。
1
死因贈与には遺言における方式に関する厳格な定めは準用されません。
したがって、必ずしも書面による必要はありません。また、自筆証書遺言の場合と異なり、たとえば全文を自筆で記載していなくとも有効となります。ここから、遺言書としてはその方式に関する規定に反し無効と考えられる場合でも、これを死因贈与契約とみて有効と認められることがあります。
2
死因贈与は遺贈と異なり契約ですから、民法の遺言能力に関する規定は適用されません。
つまり、死因贈与を有効に行うためには、遺言の場合の遺言能力では足りず、通常の契約の場合に求められる行為能力が必要となります。
死因贈与は、遺贈のような厳格な方式による必要がないため、全文を自筆で記載する必要がなく、公正証書遺言のような費用や立会人といった負担もありません。また、相続による財産の取得とみなされて贈与税ではなく相続税が課税されるというメリットもあります。
しかし他方で、贈与者に行為能力があったかどうか、本当に本人の意思に基づいて死因贈与がなされたか疑われることもあることに注意が必要です。
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者やこれを発見した者は、遺言者の死亡を知った後に遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立会のうえで開封しなければならないことになっています。
検認の申立てがなされると、家庭裁判所から申立人と相続人に対して検認期日が通知されます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各自の自由で、全相続人がそろわなくとも検認手続は行われます。
検認期日には、家庭裁判所が遺言の方式に関する事実を調査したうえで、当該遺言書をコピーして遺言書検認調書というものが作成されます。検認が終われば遺言書は提出者に返還されます。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
このように、遺言書の検認は、遺言書の状態を確定してその現状を明確にするものに過ぎませんので、検認をしたかどうかは、遺言の有効・無効とは関係がありません。
遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与える行為です。
遺贈の効力は、遺言者の死後に生じる点で、死因贈与と類似しますが、死因贈与は生前に贈与者と受贈者との契約によって行われる点で遺贈と異なります。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、「甲不動産をYに遺贈する」というように、特定の具体的な財産を無償で与えるものをいいます。これに対し、包括遺贈とは、「財産の全部をAに遺贈する」「遺言者は財産の全部をAとCに2分の1ずつの割合で遺贈する」などのように、財産を特定することなく相続財産の全部またはその一部を一定の割合で遺贈するものです。
特定遺贈の目的財産に対する権利は、遺言者の死亡と同時に、受遺者に移転します(包括遺贈と異なり、債務は引き継がれません)。
受遺者は、移転された所有権に基づいて、目的物を自分に引き渡すよう請求し、目的物が不動産であれば所有権移転登記をするよう請求することができます。
そこで、Yは、Xの法定相続人に対し、Y名義への甲不動産の所有権移転登記を請求することができますし、甲不動産を占有している者に対し、甲不動産を明け渡して自分に引き渡すよう請求することができます。
また、特定遺贈された財産は相続財産から除かれますので、遺産分割協議を行うにあたっては、甲不動産は相続財産の範囲から除いて残りの相続財産のみを分割することになります。
包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになります。
つまり、包括遺贈がなされると、包括遺贈を受けた受遺者は、相続財産上の権利義務を当然に取得するため、新たに受遺分の相続人が現れたという関係になります。したがって、他に相続人や包括受遺者がいる場合は、これらの者と共同相続したことになります。
この共有関係を解消するには遺産分割の手続による必要があります。また、包括遺贈についても遺留分減殺請求の対象となります。
包括受遺者は、相続人と同様に、遺贈を放棄したり、単純承認したり、限定承認することができます。ただし、包括受遺者であっても受遺者であることに変わりはないので、相続人と異なり、遺留分を有しません。また、代襲相続は発生せず、遺言の効力発生時に受遺者が存在しなければ、遺言の包括遺贈に関する条項は失効します。
実際の遺言では、「甲土地をAに相続させる」という表現がよく使われます。
その理由は、主として、不動産登記手続について、遺贈の場合には他の共同相続人と共同で申請しなければならないのに対し、「相続させる」遺言の場合には相続と同じく単独で申請できるというメリットがあるためです。
これは、「相続させる」旨の遺言の性質は、被相続人が相続財産の分割の方法を定めた遺言であり、このため、遺産分割の協議や審判を経ることなく、遺言の効力発生と同時に当然に分割の効力が生じると考えられているからです。
「甲土地をAに相続させる」という遺言であれば、遺言の効力発生と同時に、Aが甲土地の所有権を取得することになり、Aは遺言書を添付して単独で自分の名義に登記を変更することができます。
「相続させる」旨の遺言の条項は、その遺言により、特定の相続財産や全部の相続財産を受けることとされた推定相続人が遺言者の死亡前に死亡した場合は、遺言者が推定相続人の代襲者に相続財産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、失効します。
したがって、遺言者が、万一、相続財産を相続させようとした者が自分より先に死亡した場合には他の者に相続財産を受け取らせようと考える場合には、遺言書にその旨を記載することが必要です。
たとえば設問のような場合には、長男が遺言者より先に死亡した場合には、長男が受けるべき相続財産を長男の子に相続させる旨の遺言(補充遺言といわれます)をしたり、あるいは長男の死亡後に長男の子に相続させる旨の新たな遺言をすべきことになります。