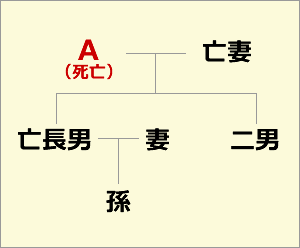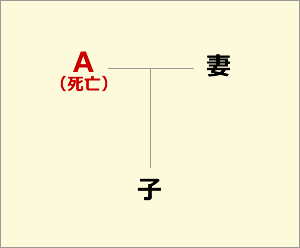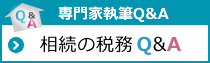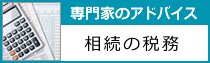相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。
寄与分
寄与分とは、共同相続人のうちで、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした者があるときに、その貢献をした者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させるもので、共同相続人間の不公平を是正するための制度です。
たとえば、子の1人が長年にわたって高齢の親の介護にあたり、介護のための出費を抑えることにより親の財産が減少せずにすんだという事情があるときに、親の相続において、各相続人が単純に法定相続分に従って相続財産を分割すると、親の財産の維持に貢献してきた相続人とその他の相続人との間に実質的な不公平が生まれてしまいます。
寄与分はこのような不公平を是正するために民法によって認められるものです。
寄与分がある場合の具体的な相続分の計算方法は、相続財産から寄与分を控除したものを相続分算定の際の基礎財産として各相続人の相続分を算定したうえで、寄与者にはあらかじめ控除された寄与分を加えたものを相続分とします。
寄与分を請求することのできる者は、民法上、相続人に限られています。
したがって、相続人の妻や子など相続人以外の者の行為については、本来、寄与分は認められないことになります。
しかし、実務上、たとえば相続人である長男に代わって、その妻が被相続人の家業に無報酬で従事し、財産の維持形成に特別な貢献をしたような場合には、妻の寄与を相続人の寄与と一体と評価することによって、間接的に寄与を認めています。
また、代襲相続があった場合には、代襲相続人は、被代襲者に代わって被代襲者の相続分を受け継ぎますから、被代襲者が生存していたとすれば主張できたはずの寄与分を主張することができます。
たとえば、Aには長男と二男の2人の子供がおり、長男は生前Aの家業に無報酬で従事し、Aの財産の維持形成に特別な貢献をしましたが、Aより先に死亡し、その後、Aが死亡したとします。また、Aの妻は、Aより先に亡くなっており、長男には、子供がいます。この場合、Aの相続人は、二男と長男の子(代襲相続人)のみであり、長男の子は、長男の寄与行為に基づく寄与分を主張することができます。
寄与分が認められる要件は、次の3つです。
1 相続人自身の寄与行為があること。
2 その寄与行為が「特別の寄与」と評価することができること。
3 寄与行為によって、被相続人の相続財産が維持または増加したこと。
つまり、相続人の行為によって、被相続人の積極財産の減少や債務など消極財産の増加が阻止され、または積極財産の増加や債務など消極財産の減少という結果がもたらされることが必要です。
民法は寄与分が認められる寄与の種類として、(1)被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、(2)被相続人の療養看護のほかに、(3)その他の方法による寄与、を定めています。したがって、寄与の態様には様々なものがありうることになります。
たとえば被相続人の事業を手伝っていた場合(家業従事型)、被相続人に金銭を贈与したような場合(金銭等出資型)、扶養義務がない者による被相続人の扶養(扶養型)、病気療養中の被相続人を看護していた場合(療養看護型)、被相続人の財産を管理していた場合(財産管理型)などの類型があります。
裁判例でも、労務の提供や財産上の給付、療養看護以外にも、被相続人である夫がその名義で不動産を購入した際に妻がかなりの財産を提供していた場合や被相続人が所有する土地の売却に際して、相続人が借家人の立退交渉や売買契約の締結などを担当して売買価格の増加に貢献した場合などを寄与と認めたものがあります。
親子間の扶養義務や夫婦間の協力義務といった被相続人と相続人の身分関係によって通常期待されるような程度の貢献では足りず、ある程度大きな貢献が必要となります。
たとえば、相続人が病気療養中の被相続人の療養介護に従事したという場合でも、ただ単に被相続人と同居して家事の援助を行っているにすぎない場合には寄与分が認められる可能性は低いです。これに対して、相続人が介助に従事した結果、職業付添者の費用の支払いを免れたというような場合は、寄与分が認められるでしょう。
寄与分が認められるかどうか、認められる場合にその額がいくらになるかは、相続人の協議によって決定されます。
この協議は、遺産分割協議の中で行われることが多いですが、寄与分についてのみ独立して協議することもできます。
協議が整わない場合または協議ができない場合は、家庭裁判所に申し立てて決定してもらうことになります。家庭裁判所は寄与の時期、方法および程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を決定します。
寄与者の相続分は次のように算定されます。
(1)
みなし相続財産を決定する
被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から、決定された寄与分の価額を控除した財産を相続財産とみなします(みなし相続財産)。
(2)
一応の相続分を算出する
みなし相続財産の価額に各相続人の相続分を乗じて、各相続人の一応の相続分を算定します。
(3)
具体的相続分の算定
一応の相続分に寄与分を加えて寄与者の相続分を算定します。
これを具体例でみます。
被相続人Aが5,000万円の財産を残して死亡し、相続人が妻と子の2人とします。子には寄与分600万円が認められる場合の妻と子の相続分は次のとおりとなります。
(1)
みなし相続財産
5,000万円-600万円=4,400万円
(2)
一応の相続分
妻 4,400万円×1/2=2,200万円
子 4,400万円×1/2=2,200万円
(3)
具体的相続分
妻 2,200万円
子 2,200万円+600万円=2,800万円
生前贈与を受けている相続人であっても、さらに寄与分を主張することは可能でしょうか?
寄与した相続人が被相続人から生前贈与を受ける等により寄与相当分が報われていると評価できる場合には、生前贈与を特別受益の持戻しの対象とはしないかわりに、その限度で寄与分の請求は認められません。その場合には、被相続人と寄与した相続人との間で実質的に貢献に対する精算が行われているといえるからです。
これに対し、生前贈与が寄与と対価関係になかったり、あるいは生前贈与分だけでは寄与に対する評価として十分とは認められないときは、別途寄与分が認められる余地があります。
裁判例でも、寄与分の評価額から寄与した相続人が被相続人から生前贈与を受けていた価額を差し引いた残額を相続における寄与分として認めたものがあります。
家業従事型の寄与分が認められるか否かは、被相続人との身分関係、労務を提供するに至った事情、労務提供の時期と期間、報酬の有無、労務の提供により財産の維持または増加があったといえるか否かなどの諸事情を総合的に考慮して判断されます。
たとえば夫の営む農業や自営業を夫婦が協力して行った場合は、妻の家業従事は夫婦の協力扶助義務の範囲を超えるものと評価でき、寄与分が認められる可能性があります。
財産給付の内容が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待されるような程度の貢献を超える財産上の給付であることが必要です。
たとえば、相続人が被相続人に対して不動産を贈与したり、無償で使用させていたりした場合や、被相続人である夫がその名義で不動産を購入するに際して、妻が自己の得た収入を提供した場合は、寄与分が認められる可能性が高いといえます。
相続人が被相続人を療養看護したために、それによって被相続人が看護してくれる人を雇うための費用の支出を免れ、相続財産が維持または増加したという場合に認められます。
療養看護型の「特別の寄与」に該当するかどうかは、相続人がどのような看護を行ったかということだけではなく、被相続人がどのような病状にあり、どのような療養看護を必要としていたか、という点が重要なポイントとなり、次のような点が考慮されます。
(1)
療養看護の必要性
被相続人が療養看護を必要とする病状であったことと、近親者による療養看護が必要であったこと、の双方が必要です。寄与分が認められるためには、被相続人が要介護2以上の状態であることが必要といわれています。
したがって、病状が重篤でも、完全看護の病院に入院していたというような場合は、基本的に寄与分は認められません。
(2)
特別の貢献
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献であることです。
したがって、被相続人の病状と療養看護した期間が問題となります。
(3)
無償性
療養看護が無報酬または通常の介護報酬に比べて著しく少額の報酬で行われたことが必要です。被相続人から寄与行為の対価として金品を渡されている場合には、寄与分は認められません。
(4)
継続性
療養看護が相当期間継続していることが必要です。
その期間に明確な基準があるわけではありませんが、1年以上継続しているような場合は認められやすいでしょう。
身体的にも経済的にも扶養の必要がある被相続人に対して、相続人が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えた扶養を行った場合には、寄与分が認められる場合があります。
扶養の態様としては、(1)相続人またはその親族が被相続人を現実に引き取って扶養する場合、(2)相続人が扶養料を負担する場合があります。
たとえば、被相続人は、生前、稼働することができず無収入であったため、妻が就業して長期間にわたりその収入で夫婦の生計を支え、これにより相続財産が維持されたというような場合には、配偶者に期待される協力扶助の程度を超えていると評価されて寄与分の主張が認められる可能性が高いでしょう。
これに対して、少額の仕送りをしていたにすぎない場合には、寄与分が認められないことも少なくありません。
相続人が被相続人の財産を管理することによって、その財産の維持形成に寄与した場合に寄与分が認められます。
たとえば、被相続人の賃貸不動産を管理することにより管理費用の支出を免れた場合や、被相続人所有の土地の売却に際し、その土地の借地人との立退交渉や土地の売買契約の締結に尽力したことにより土地の売却価格を増加させたといえる場合には、寄与分が認められる可能性が高いでしょう。
民法の改正によって、相続人以外の者にも、寄与分の請求が認められることになったと聞きましたが、どういう場合に認められますか。
平成30年改正法の施行前の民法では、寄与分の制度の対象は相続人に限られていました。
このため、被相続人の息子の嫁など相続人でない者が、被相続人を療養看護して、その結果として被相続人の財産の維持・増加に寄与したという場合でも、遺産分割の手続で寄与分を主張することは認められませんでした。
この結果に対しては、従来から、生前に被相続人の世話などを一切しなかった相続人が遺産の分配を受けられるのに対し、一生懸命無償で療養看護等の寄与をしたものがまったく報われないのは不公平だという批判がありました。
そこで平成30年改正法は、相続人ではない被相続人の親族(「特別寄与者」といいます)の貢献に報いるために、特別の寄与の制度を設けることとしました。
これにより、被相続人の療養看護等の貢献をした者は、相続人に対して金銭請求(「特別寄与料」といいます)をすることができることになりました。
特別寄与者としての資格があるのは、相続人ではない親族です。相続人にはもともと寄与分が認められているため、特別寄与者には含まれません。
「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。「姻族」とは、婚姻関係によって生じる親族関係のことで、配偶者の血族と血族の配偶者の2種類があります。
相続放棄をした者、民法891条の相続欠格事由にあたる者、廃除によって相続権を失った者は「特別寄与者」から除かれます。
特別寄与料の額はどのように算定されますか。
特別寄与料の支払については、当事者間の協議によって決められます。
協議が整わないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
この請求の申立てがあると、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めることになります。
ただし、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の額から遺贈の額を控除した残額を超えることはできないものとされています。
また、特別寄与者が家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができる期間は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内で、相続開始の時から1年以内と定められています。
このように請求期間が制限されたのは、相続人としては、自分が特別寄与料を支払わなければならないのか、支払わなければならないとするならその額はいくらかということを把握できなければ、遺産分割の協議を成立させることに不安を抱くことになり、相続をめぐる紛争が長期化するおそれがあることが懸念されたためです。