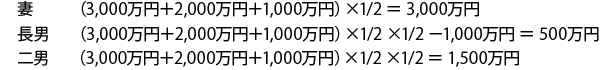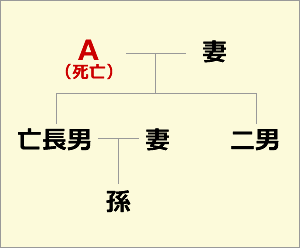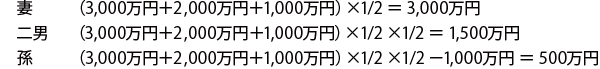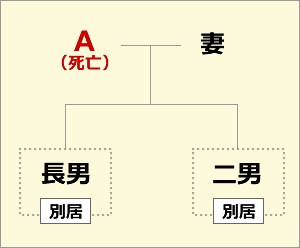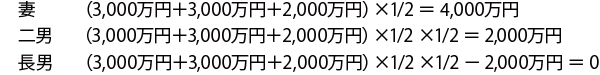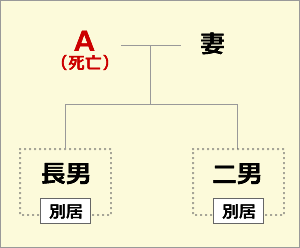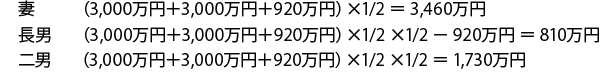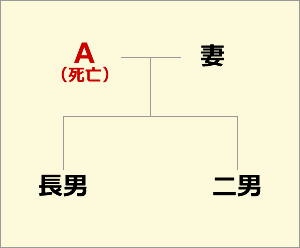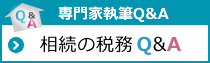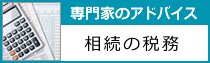相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。
特別受益
特別受益とは何ですか。また、持ち戻しや、みなし相続財産の意味を教えてください。
特別受益とは、遺贈(遺言によって、遺言者の財産を無償で譲渡すること)や相続人に対する一定の条件を満たす生前贈与をいいます。
このような遺贈や生前贈与を考慮せずに、残った相続財産だけを法定相続分に応じて分割すると、相続人に不公平が生じます。そこで、民法は、この特別受益を次のように取り扱います。
まず、特別受益にあたる生前贈与があった場合、この生前贈与額は、相続分算定に当たって相続財産の総額に算入されます。この取り扱いを、「持ち戻し」と言います。
また、相続開始時に被相続人が持っていた相続財産額に、特別受益に当たる生前贈与額を加算した計算上の相続財産を、「みなし相続財産」とします。このみなし相続財産を基礎として、遺産分割を行うことになります。
たとえば、妻と長男及び長女という2人の子供がいるAが亡くなり、Aの相続財産が、自宅土地建物(評価額3,000万円)と預貯金2,000万円であったとします。この場合、Aが生前に自宅建設資金として1,000万円を長男に贈与していたとすると、相続分算定に当たって長男が生前贈与を受けた1,000万円は持ち戻され、相続財産総額に算入されます。これによって算出されるみなし相続財産6,000万円を基礎に遺産分割を行います。
このケースにおける各相続人の相続分は、次のような金額となります。
〈税法との関係〉
民法上、特別受益となる生前贈与に時間的な制限はなく、例えば20年以上前の生前贈与であっても、特別受益の条件を満たせば、相続分算定に当たって相続財産の総額に参入しなければなりません。
これに対して、相続税の申告においては、「相続開始前3年以内の贈与財産」が、贈与を受けた者の相続税の課税価格に加算されます。
特別受益には、どのようなものがありますか。
特別受益となるのは、遺贈(遺言によって、遺言者の財産を無償で譲渡すること)や相続人に対する一定の条件を満たす生前贈与です。
遺贈は、その目的に関わりなく特別受益となりますが、生前贈与は、「婚姻又は養子縁組のための贈与」と「生計の資本として贈与」が特別受益となります。
「婚姻又は養子縁組のための贈与」には、一般的には、婚姻や養子縁組の際の持参金や支度金が該当しますが、結納金や結婚式の費用は該当しないと言われています。おそらく、前者は後者と比べて多額であり、また、一度に費消してしまうものではないからと思われます。
また、「生計の資本としての贈与」には、自宅建設資金、営業資金、土地や借地権の贈与など、相続人のその後の生活の基礎として役立つような財産の給付が該当します。学費も、私立大学の医学部の入学金や学費など、高額なものはこれに該当します。
これに対して、入学祝い、新築祝い、出産祝いなど、少額の金員の贈与は、生計の資本としての贈与には該当しません。
被相続人が特定の相続人を受取人として、保険金額が相続財産総額の2倍にあたるような生命保険契約を締結し、保険料の支払いも完了していた場合、この保険金は特別受益に当たりますか。
Q 生命保険の取扱いで説明しましたように、生命保険金は相続財産とは扱われませんので、原則として特定の相続人が受け取った生命保険金は特別受益には当たりません。
しかし、設問のように生命保険金が極めて高額であるなど、生命保険金を特別受益とせずに遺産分割を行うと、生命保険を受け取った相続人と他の相続人との間に特別受益制度の趣旨に照らし到底是認できないような著しい不公平が生じるような特別の場合は、生命保険金を特別受益に準じて持ち戻しの対象とするとするのが、最高裁判所の判例です。
過去の裁判例においては、特定の相続人が受け取った生命保険金が相続開始時の相続財産の総額の6割を超えるような事案で、生命保険金を特別受益に準じて持ち戻しの対象としています。
Aには、妻と2人の息子がいましたが、長男はすでに亡くなっています。長男には、子供がいます。
Aが亡くなりました。Aの相続財産は、自宅土地建物(評価額3,000万円)と預貯金2,000万円ですが、Aは長男の生前、長男に自宅建築資金1,000万円を贈与していました。この場合、各相続人の具体的相続分はどうなりますか。
また、逆に、Aが、長男の生前、孫に留学資金1,000万円を贈与していた場合はどうですか。
設問のケースでは、妻、二男及び長男の子(孫)が相続人となります。
孫は、父がAから自宅建築資金1,000万円の生前贈与を受けていますので、この生前贈与を持ち戻すことになります。
従って、各相続人の相続分は、次のとおりとなります。
これに対して、Aが、長男の生前、孫に留学資金1,000万円を贈与した場合は、原則として相続人以外の者に対する生前贈与は特別受益とはなりませんので、孫はこの生前贈与を持ち戻す必要はないとするのが一般的です。
ただし、Aの孫に対する生前贈与が、名義上孫に対して行われただけで、実質的には長男への贈与であると認められるような事情があるときは、長男への特別受益として取り扱うことになります。
Aには、妻と長男及び二男の2人の息子がいますが、2人の息子は既に独立し、A及び妻とは別の場所で生活しています。
Aが亡くなりました。Aの相続財産は、自宅土地建物(評価額3,000万円)と預貯金3,000万円ですが、Aは40年前に長男に土地(当時の時価500万円)を贈与していました。この場合、各相続人の具体的相続分はどうなりますか。
Aには、妻と長男及び二男の2人の息子がいますが、2人の息子は既に独立し、A及び妻とは別の場所で生活しています。
Aが亡くなりました。Aの相続財産は、自宅土地建物(評価額3,000万円)と預貯金3,000万円ですが、Aは40年前に長男に自宅建築資金300万円を贈与していました。この場合、各相続人の具体的相続分はどうなりますか。
金銭の生前贈与があったときは、原則として貨幣価値の変動を考慮します。
設問のケースでは、Aが40年前に長男に贈与した300万円を相続開始時の貨幣価値に換算して計算します。
具体的には、消費者物価指数を参考にして換算を行うのが一般的です。たとえば、Aが亡くなったのが平成22年(2010年)であるとすると、その40年前は昭和45年(1970年)となります。平成22年の消費者物価指数を100とすると、昭和40年の消費者物価指数は32.6です。
そこで、昭和45年に贈与された300万円を、消費者物価指数を利用して平成22年の貨幣価値に換算すると、約920万円となります。
300万円 ÷ 32.6 × 100 = 920万円
この920万円を持ち戻して各相続人の相続分を計算すると、次のようになります。
特別受益証明書(相続分不存在証明書)とは、相続財産の中の不動産を特定の相続人が取得する場合に、相続による所有権移転登記を簡単に行うために、他の相続人が作成する文書です。
具体的には、不動産を取得しない他の相続人が、「私は被相続人より民法第903条1項所定の贈与を既に受けており、被相続人の死亡による相続については相続する相続分が存在せず同条第2項に該当する者に相違ないことを証明します。」と書かれた文書に署名捺印し、印鑑登録証明書を添付するものです。
たとえば、妻と長男及び二男の2人の息子がいるAが亡くなり、Aの相続財産が、自宅土地建物(評価額3,000万円)だけだとしましょう。
相続人間の話し合いで、自宅土地建物を妻が取得することになった場合、妻がこの土地建物について相続による所有権移転登記をするには、原則として3人の署名捺印のある遺産分割協議書を法務局に提出することになりますが、他の方法として、長男と二男の署名捺印のある特別受益証明書(相続分不存在証明書)を提出するという方法も認められています。
特別受益があるときは、相続開始時に被相続人が持っていた相続財産に特別受益にあたる生前贈与額を加え(これを「持戻し」といいます。)、その合計額を相続財産とみなして(みなし相続財産)、各相続人の相続分を算定するのが原則です。
持ち戻し免除の意思表示とは、被相続人が特別受益の持ち戻しをしなくてよいことを表明する意思表示です。
被相続人は、自分の相続財産をどのように配分するか自由に決めてよいのですから、被相続人が、特定の相続人への生前贈与や遺贈を、その人の特別の取り分として確保してやり、持ち戻しをさせないという意思を明らかにした場合は、その意思を尊重しなければなりません。このため、持ち戻し免除の意思表示があったときは、持ち戻しをしないことになります。
持ち戻し免除の意思表示は、生前贈与については、どのような方式で行っても構いません。また、明示の意思表示でも黙示の意思表示でもよく、生前贈与時の諸事情から、被相続人が、特定の相続人に相続分以外に特別の取り分を与える意思があったと認められる場合には、持ち戻し免除の黙示の意思表示があったものと認められます。
これに対して、遺贈については、持ち戻し免除の意思表示は、遺言書に記載されていなければならないとするのが支配的な見解です。
民法改正によって、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与は、持ち戻し免除の意思表示があったと推定されることになったと聞きましたが、それはどのようなものですか。
平成30年改正法は、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、配偶者に対して、居住用の建物またはその敷地を遺贈・贈与したときは、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するという規定を新たに設けました。
20年以上の長期の婚姻生活を送ってきた夫婦の一方(たとえば夫)が、他方の配偶者(たとえば妻)に居住用の不動産を贈与したり遺贈したりする目的は、それまでの夫婦としての貢献に報いるということと、老後の生活を保障することにあるのが通常だと思われます。
せっかくそのような目的で贈与したのに、相続が開始して遺産分割を行うときに、居住用不動産の贈与は特別受益にあたるとして、配偶者の相続分からその価格を控除して遺産の取り分を減少させるようなことは、贈与した被相続人は望んでいないことが多いと考えられます。
そのため、新法は、①婚姻期間が20年以上の夫婦間で、②居住用の建物または敷地について遺贈または贈与したときは、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定することとしたのです。これにより、配偶者への居住用の土地または建物の贈与や遺贈について、特別受益と扱うことなく遺産の取り分が計算されることになります。
ただし、あくまで持ち戻し免除の意思が推定されるにすぎませんので、被相続人が持ち戻しを免除するつもりなどなかったことが証明されれば、推定が覆り、持ち戻しを求められることになります。