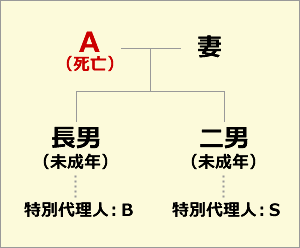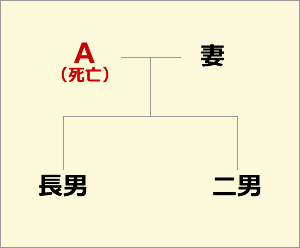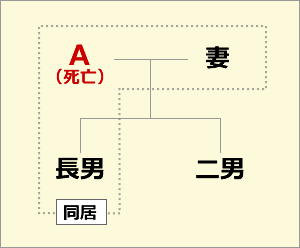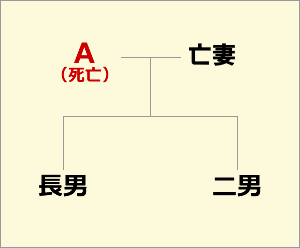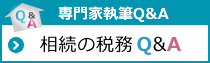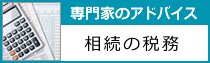相続についての法律制度の中には、民法と相続税法の相続財産を巡る取扱に違いがある等、理解するのは難しいものとなっていますが、基本的な知識を手軽に得ることができるように解りやすく解説しています。
遺産分割協議の前に
解決しなければならない問題
私の夫が亡くなりました。私には 長男、二男という2人の息子がいます。長男は17歳、二男は13歳です。
私は、長男及び二男の親権者として2人を代理して、私が相続財産を全部取得する遺産分割を成立させましたが、利益相反があるので、この遺産分割は無効だと言われました。利益相反とは何ですか。また、どうすれば有効な遺産分割ができますか。
長男と二男は未成年者ですので、財産についての行為は、親権者である母親が長男や二男を代理して行うのが原則です。
遺産分割協議も、この財産についての行為ですので、母親が長男や二男を代理して行うことができるように思えます。
しかし、この場合、母親自身も相続人ですから、母親がたくさん相続財産をもらえば、長男や二男がもらう相続財産は少なくなりますので、母親と長男及び二男とは、利害が対立します。これを、利益相反と言います。つまり、父親の遺産分割において、母親と長男及び二男とは利益相反の関係にあります。このような利益相反の場合に、母親が長男及び二男の親権者として2人を代理して遺産分割協議をすると、母親に有利な内容の遺産分割となる恐れがあります。
そこで、利益相反の場合は、家庭裁判所に申立てをして、長男と二男それぞれのために、特別代理人を選任してもらわなければなりません。特別代理人は、長男と二男それぞれのために1人選ばれますので、たとえば、長男にはBさん、二男にはSさんが選ばれます。そして、母親は、このBさん及びSさんと遺産分割協議をすることになります。
私は、一回離婚しており、前の夫との間に長男、二男という2人の息子がいます。長男も二男も未成年者ですので、離婚の際に私が長男、二男の親権者となりました。
この度、前の夫が亡くなりましたので、私が長男及び二男の親権者として2人を代理して遺産分割を成立させましたが、利益相反があるので、この遺産分割は無効だと言われました。
この場合も利益相反になりますか。利益相反になる場合、私はどうすればいいですか。
この場合、母親は相続人ではないですから、母親と長男及び二男との利益が相反することはありません。しかし、長男と二男は、そのどちらか一方がたくさん相続財産をもらえば、他方がもらう相続財産は少なくなりますので、長男と二男とは、利益相反の関係にあります。
このような場合は、母親は、長男と二男のどちらかの代理はできますが、両方の代理はできません。そこで、母親は、家庭裁判所に申立てをして、長男と二男のどちらか1人のために、特別代理人を選任してもらわなければなりません。
相続人の1人が認知症で判断能力がない場合、遺産分割協議をするにはどうしたらよいですか。
相続人の1人が認知症で判断能力がない場合、この相続人と協議をして遺産分割を成立させても、遺産分割は無効となります。このような場合には、家庭裁判所に、認知症の方の法定後見開始の申立てをし、成年後見人を選任してもらい、この成年後見人と遺産分割協議をすることになります。
法定後見開始の申立は、認知症で判断能力のない相続人の方の住所地を管轄している家庭裁判所に申立てをすることができます。申立ての仕方や必要な書類については、この家庭裁判所に相談するとよいでしょう。
相続人の1人が行方不明の場合、遺産分割協議をするにはどうしたらよいですか。
遺産分割は、相続人全員が合意しなければ成立しませんので、相続人の中に行方不明の方がいる場合、そのままでは遺産分割協議はできません。
このような場合には、家庭裁判所に、行方不明の方の不在者財産管理人選任の申立てをして、不在者財産管理人を選任してもらい、この不在者財産管理人と遺産分割協議をすることになります。
不在者財産管理人選任の申立ては、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄している家庭裁判所に申立てをすることができます。住所地とは、不在者が生活の本拠としていた場所であり、居所地とは、生活の本拠とは言えないが不在者が相当期間継続して居住していた場所です。申立ての仕方や必要な書類については、この家庭裁判所に相談するとよいでしょう。
Aは結婚したことがなく、子供もいません。また、Aの両親は亡くなっており、二男、三男及び四男の兄弟3人がいましたが、3人とも亡くなっています。戸籍を調べても、兄弟3人に子供がいた記載はありません。この場合、相続財産はどうなりますか。
Aには、配偶者も子供もおらず、また、両親も亡くなっているので、本来は二男、三男及び四男の兄弟3人が相続人となります。しかし、この3人の兄弟も亡くなっており、さらに、この3人の兄弟には子供がいませんので、Aには相続人がいない可能性が高いことになります。
このように、相続人がいるかいないか不明な場合、そのまま放置すると相続財産は宙に浮いてしまい、相続財産について法律上の利害関係がある人は困ってしまいます。
そこで、相続人がいるかいないか不明な場合、相続財産の利害関係人は、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。相続財産の利害関係人とは、たとえば、Aにお金を貸していた人、相続人ではないがAの遺言によってAの財産をもらえることになっている人、生前Aと同居してAの生活の面倒を見たため、相続財産の分与を求めたい人などです。
相続財産清算人選任の申立は、相続開始地(Aの最終の住所地)を管轄している家庭裁判所に申立てをすることができます。申立ての仕方や必要な書類については、この家庭裁判所に相談するとよいでしょう。
相続財産清算人の職務は、相続財産の管理、相続人の捜索、相続財産の清算です。分かりやすく言えば、相続財産清算人、Aの相続人を捜索する手続きを取り、Aにお金を貸していた人に相続財産の中からお金を返し、Aの遺言によってAの財産をもらえることになっている人にその財産を渡し、さらに、特別縁故者に相続財産を分与する旨の家庭裁判所の審判があったときは、その特別縁故者に対し分与された相続財産を引き渡します。
これらの作業の後にAの相続財産に残りがあるときは、残りの相続財産は、国のものとなります。
ただし、相続人が存在し、相続を承認したときは、その時点で、相続財産清算人の権限はなくなり、相続人に相続財産を引き渡すことになります。この後は、通常の相続の場合と同じですが、相続財産清算人がそれまでに行っていた行為の効力は失われません。
令和3年の民法改正前は、相続財産の保存を目的として選任された者も相続財産の清算を目的として選任された者も「相続財産管理人」と称されていましたが、改正法は、両者の目的が違うということで、相続財産の保存を目的とする者を「相続財産管理人」、清算を目的とする者を「相続財産清算人」と呼ぶこととしました。
ここでとりあげるのは、前者の相続財産管理人についてです。
令和3年改正民法は、相続人に放置されて荒廃してしまった土地などについて、相続財産管理制度を利用して適切に管理したいという必要から、相続財産管理について次のとおり定めました。
1
相続財産管理人選任の申立ては、相続開始後であればいつでもすることができることとしました。
ただし、相続人間で遺産分割が完了した後などは、もはや相続財産というものがなくなっていることになるので、相続財産管理人の選任を申し立てることはできません。また、相続財産清算人が選任されているときは、清算人は相続財産の保存の権限ももっているため、相続財産管理人は不要です。
2
相続財産管理人が選任されるのは、相続財産の保存のため必要な場合です。
相続財産に属する不動産が荒廃したり物が腐敗したりしているのに、相続人がこれを放置して保存行為をしないため適切に管理する必要があるといった場合が想定されています。
3
相続財産管理人の権限は、保存行為と目的物の性質を変えない範囲での利用・改良行為に限られます。これを超えて目的物を売却など処分するには裁判所の許可を得たうえで行わなければなりません。
相続財産管理人の選任を申し立てる例としては、次のようなケースがあります。
1
被相続人の成年後見人であった者が、その職務として、管理人(または清算人)に相続財産の引継を行うケース
2
被相続人の特別の縁故を主張する者が相続財産の分与を請求しようとするケース
3
相続放棄をした者が、相続財産の管理義務を免れるために、管理人(または清算人)に相続財産の引継を行うケース
4
被相続人の債権者が債権回収を図るため競売等により物件の売却を求めるケース
5
相続財産に属する土地が荒廃しているが、相続人が遠方に住んでいるなどのため土地の管理がなされていないが、利害関係人がその土地について必要な保存行為をしたいと考えるケース
Q 相続人の存否が不明な場合で説明しましたように、相続人がいるかいないか不明な場合、家庭裁判所は、相続財産に法律上の利害関係を有する人の申立てにより、相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人は、相続財産の管理、相続人の捜索、相続財産の清算を行います。相続人捜索は、具体的には、官報に相続権を主張する者は一定期間(6か月以上)内に申し出るように記載する方法で行われますが、この期間が終了してから3か月以内であれば、特別縁故者は、家庭裁判所に相続財産の分与を申し出ることができます。
特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた者(たとえば内縁の妻、養子縁組届をしていないが事実上養子として生活していた者)、被相続人の療養看護に努めた者、その他相続権はないが被相続人と特別の縁故関係にあった者(被相続人の生活費の支援をした者など)です。
特別縁故者が、家庭裁判所に対して相続財産の分与の申出をした場合、家庭裁判所は、相続財産を分与すべきかどうか判断(審判)します。特別縁故者に相続財産を分与する旨の家庭裁判所の審判があったときは、相続財産管理人は、その特別縁故者に対し分与された相続財産を引き渡します。
ただし、相続人が存在し、相続を承認したときは、特別縁故者への相続財産の分与はありません。
Aには、妻と長男、二男という2人の息子がいます。
Aが亡くなり、Aの財産の全部を長男に取得させるという自筆証書遺言が見つかりました。しかし、Aは、亡くなる数年前から認知症で有料老人ホームに入っており、遺言を作ったとされる時期も、同じ有料老人ホームにいました。このため、妻や二男は、この遺言書の有効性について疑問があります。この場合、どうすればよいのでしょうか。
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作成する遺言です。
自筆証書遺言に限らず、遺言をするには、遺言をしようとする者に遺言の内容を理解し、その遺言の結果、自分の相続財産がどうなるかを認識できる能力(これを、遺言能力といいます。)があることが必要です。
遺言は、通常の取引行為ではありませんので、取引行為で要求される能力より低い能力でも行えるとされています。そこで、民法は、遺言について、15歳に達した者は遺言をすることができると定めています。
このように、遺言能力は、一般の取引行為で必要となる能力よりもある程度低い能力で足りますので、たとえ遺言者が遺言の際に認知症であっても、相当認知症が進み、かなり理解力や認識力が低下していないと、遺言能力がないということにはなりません。
そこで、妻や二男は、まず自筆証書遺言作成時のAの精神能力を確認するため、Aの介護認定記録、診療録、入居していた老人ホームの業務日誌などを収集し、Aの遺言能力の有無を確認する必要があります。
もしAの認知症が相当進んでおり、遺言能力がなかったと認められるときは、妻や二男は、自分を原告とし、長男を被告として遺言無効確認訴訟を提起することになります。
この遺言無効確認の訴えは、家庭裁判所ではなく地方裁判所が管轄する事件ですので、地方裁判所に訴えを提起しなければなりません。
また、遺言無効確認請求訴訟は、理論的に遺産分割協議の前提問題となりますので、遺言無効確認請求訴訟が解決するまで、遺産分割調停を進めることはできませんので注意してください。
Aには、妻と長男、二男という2人の息子がいます。
Aが亡くなりました。Aの相続財産は、実家の土地建物ですが、A及び妻と実家で同居していた長男は、「実家の建物の登記名義は Aになっているが、建物の建築資金は自分が出したので、建物はAのものではなく、自分の所有だ。」と主張しています。この場合、どうすればよいのでしょうか。
遺産分割協議の際に、最初に問題となるのが、相続財産に属する財産の範囲です。どの財産が相続財産なのかが決まらなければ、どう分けるかを話し合うことができないからです。
このケースの場合、長男は、登記上A名義となっている実家の建物について、自分が建築資金を出したから自分の所有だと主張しています。確かに長男が建物の建築資金を出していれば、たとえ登記上の所有名義がAとなっていても、長男の所有と認められる場合もあります。
これに対して、妻及び二男は実家の建物はAの相続財産であると主張するでしょうから、Aの相続財産の範囲について相続人間に対立があり、このままでは相続財産の範囲が確定できません。
このような場合、長男は、実家の建物について、自分を原告とし、妻及び二男を被告として、所有権確認訴訟あるいは所有権移転登記手続請求訴訟を提起することができます。また、逆に、妻及び二男は、実家の建物について、自分を原告とし、長男を被告として、遺産確認請求訴訟を提起することができます。
どちらの訴訟も、家庭裁判所ではなく地方裁判所が管轄する事件ですので、地方裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
また、これらの訴訟は、理論的に遺産分割協議の前提問題となりますので、これらの訴訟が解決するまで、遺産分割調停を進めることはできませんので注意してください。
被相続人Aには、長男と二男の2人の息子がいます。Aが亡くなり、相続開始時に存在していた遺産は、甲銀行の預金4,000万円だけでしたが、長男は、Aの生前からAの預金を事実上管理しており、Aの死後に1,000万円を甲銀行の預金から引き出していました。遺産分割はまだ終了しておらず、二男は、長男が引き出した1,000万円も遺産に含めるべきだと主張しています。この場合、長男と二男はそれぞれいくらの遺産を取得することになりますか。
従来の実務では、遺産分割という手続は、遺産分割の時点で実際に存在する財産を共同相続人の間で分配するものだという考え方をしていました。そこで、共同相続人の1人が、相続開始後、遺産分割前に遺産の一部を処分した場合は、その処分された財産を除いた残された遺産を基準に遺産分割を行うとされていました。
ただし、例外的に、遺産分割の当事者全員が同意すれば、処分された財産を含めて遺産分割を行うことも可能とされていました。
しかし、このような考え方だと、当事者全員の合意のない限り、勝手に遺産を処分した者の取得額が他の相続人より多額となり、不公平が生じるという問題がありました。
設例の場合だと、長男が同意しない限り、長男が引き出した遺産分割の時点で存在していない1,000万円は遺産分割の対象となりません。したがって、遺産分割時に存在する遺産3,000万円を1,500万円ずつ分けることになります。なお、長男がAの死後に引き出した1,000万円について、二男は、法定相続分に従って500万円の損害賠償または不当利得返還の請求ができることになりますが、そのために訴訟を起こす必要が生じ、訴訟をしても全額回収できるとは限らないといった不公平が生じます。
そこで平成30年改正法は、共同相続人全員の同意によって、遺産分割前に処分された財産も遺産分割の対象財産にできることを明記し、さらに、共同相続人の1人が遺産分割前に財産を処分した場合は、その処分をした共同相続人の同意を得ることは不要とすることによって、遺産分割の調整を容易にしました。
設問のケースでは、長男が引き出した1,000万円も、長男の同意がなくても、遺産分割の対象財産にできることになります。
その結果、相続財産は、預金3,000万円+長男が引き出した1,000万円=4,000万円となり、2,000万円となり、現存する3,000万円から二男が2,000万円(4,000万円×1/2)を取得することにより、公平な遺産分割が実現されます。
〈税法との関係〉
このように、被相続人の死後に払い戻された預金は、原則として遺産分割の対象となりませんが、相続税の申告における課税価格の計算では、相続開始時の預金額を算入しますので、被相続人の死後に払い戻された預金額も算入されることになります。