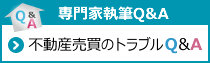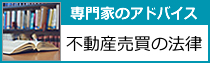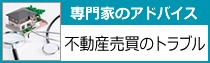初めて不動産の売買契約を締結される方が売買契約書をご覧になった際などに参考にして頂けるよう、分かりやすい言葉、一般的に使われている言葉で、法律の基本的な事項を解説しています。
売買契約の意義、成立時期
売主が「土地や建物などの財産権」を買主に移転することを約束し、これに対して買主がその代金を支払う約束をする契約のことを「売買契約」といいます。
交換される「財産権」と「代金」とは対価としての関係に立ちますので、売買契約がもつこの性質を「有償」契約といいます。
「売買」といっても、取引の具体的態様によってさまざまな種類のものがあります。「不動産」のように一般に特定物(その物の個性に着目して特定された物)として取引されるものから、「動産」のようにしばしば不特定物(種類に着目して取引の対象とされた物で、種類が同じであれば対象が特定されない物)として取引されるもの(動産も特定物として取引されることもあります)までいろいろあります(「不動産」について、【Q 不動産とは何ですか。】参照)。
また、当事者・目的物の種類・取引の場所などに応じて異なった取引慣行があり、それらが売買契約の解釈に当たって考慮されることもあります。
「売買契約書」とは、売買契約の成立を証する書面のことをいいます。
民法によれば、一般的に「売買契約」は、口頭による合意だけで成立します。売ろう・買おうという売主・買主の意思表示の合致があると売買契約が成立します。これを「諾成契約」と呼びます。
したがって、売買契約の成立のために「売買契約書」などの書面が不可欠というものではありません。
しかしながら、通常の動産とは異なり、不動産は高価で重要な財産ですので、単なる口約束ではなく、慎重に、契約条件などを記載し、契約内容を明らかにした「売買契約書」を作成することが重要です。実際の不動産取引では、通常、売買契約書が作成されます。
売買契約は、売ろう・買おうという売主と買主の意思が合致し合意した時点で成立します。もっとも、不動産などの重要な財産の売買では「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認め、この時点で売買契約が成立したと考えるべき場合が多いと言われています。それは、細目にわたる条件などをさらに詰めて交渉を重ね、正式な売買契約書を作成することが予定されている段階では、正式な売買契約書を作成するまでは売主・買主双方にとって、確定的な売買の意思はまだ表示されていないと考えられるからです。
不動産売買の実務において、正式な売買契約書を作成する前の段階で、買主・売主がそれぞれの意思を書面に記載したものを取り交わすことがあります。買主が作成するものを「購入申込書(買付証明書)」といい、売主が作成するものを「売渡承諾書」といいます。
これらの書面には、売買金額や支払時期などが記載されていて、そのような書面を相手方に交付するため、売買契約は既に成立したと主張され、紛争になることがあります。
しかしながら、これらの書面は通常、その後正式な売買契約書を作成することを予定していますし、売主・買主の売却意思・購入意思を明確にし、売買の交渉をスムーズにするためのものであると考えられます。したがって、まだ売買契約書を作成する前の交渉段階であって、「購入申込書(買付証明書)」や「売渡承諾書」の書面を交付しただけでは契約が成立したとみるのは困難であると言われています。
不動産などの重要な財産の売買では、正式な「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認めるべき場合が多く、この時点で売買契約が成立すると考えられます(【Q 売買契約はいつ成立するのですか。】参照)。
そうすると、正式な売買契約書を締結する前であれば、売買契約が成立していないので、いつでも中止して良いのでしょうか。
結論を申し上げれば、交渉過程であっても、相手に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果相手が費用の支出等を行った場合には、その信頼を裏切った当事者は相手方が被った損害を賠償する責任を負うことがあり得ます。契約が成立することを期待して何度も交渉していれば、売主・買主が互いに誠実に契約の成立に努めるべき「信義則上の義務」を負います。この「信義則上の義務」に正当な理由なく違反した場合には損害賠償を負う可能性があります。