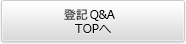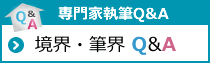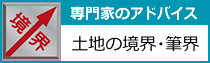不動産登記は、不動産に関連する法律行為には欠かせないものです。日頃一般の皆様が疑問に思われていること、また、登記手続きをする際に誰しもがぶつかると思われる疑問について解説しています。
財産分与登記
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与による所有権移転登記(名義変更)を行うことになります。
「財産分与」は夫婦の離婚問題などでよく取り上げられる言葉ですが、離婚する際や離婚後に財産を分けることをいいます。
離婚における財産分与については、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算する「清算的財産分与」、離婚後の一方の当事者の扶養のための「扶養的財産分与」、離婚の慰謝料としての「慰謝料的財産分与」の3種類があるとされています。
一方の当事者の経済的地位が危うい状況になる場合にその保護を図る「扶養的財産分与」精神的苦痛に対する「慰謝料的財産分与」も当然検討・加味されるべきものですが、裁判となっても認められるかどうか分からないという問題があります。実際には「清算的財産分与」についての検討が中心となるのではないでしょうか。
夫婦は協力し合って一定の財産を形成します。それら財産の名義が夫婦のどちらかになっていたとしても実際は夫婦で協力して得たものですから実質は夫婦共有の財産であるということになります。そういった財産は財産形成の貢献度に応じて公平に分け与えられるべきものといえます。
離婚後、財産分与について当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。申立ては離婚から2年以内にする必要があります。
調停手続きでは、夫婦が協力して得た財産や夫婦双方の貢献の度合い等について双方から事情を聴いたりした上で解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたり、合意ができる様に話し合いを進めていきます。
話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続きが開始されます。裁判官が、必要な審理を行った上一切の事情を考慮して審判をすることになります。
なお、話し合いをしている間や調停中に、一方当事者が勝手に不動産を処分したり預貯金・現金等の財産を隠匿したりすることがあるかもしれません。この様な一方当事者による財産の処分や隠匿等の恐れがある場合、これを阻止するために裁判所に「仮差押え」の申し立てを行うという方法があります。申立てにより不動産には仮差押の登記がなされ、預貯金については凍結されることになります。
ただ、仮差押え行うためには、対象財産の特定することや保全の必要性についての裁判所での事情説明等、一般の方からすれば手続きは難しいかもしれません。また、財産の差し押さえは相手方の感情を強く刺激することにもなり、話し合い、調停が難航する事態になる可能性もあります。自分一人では進めずに弁護士に相談されるのが良いでしょう。
登記の申請は、財産分与を受けた人(登記権利者)と財産分与をした人(登記義務者)の共同申請によってなされるのが原則です。財産分与をした人が登記申請に協力しない場合は調停調書、審判書等を提出することにより、財産分与を受ける方(登記権利者)が単独で登記申請できます。
下記の書類が必要となります。
1 財産分与をしたことを証する書面(協議書等)
2 財産分与をした人(登記義務者)が所持している土地・建物の登記済証または登記識別情報
3 財産分与をした人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
4 財産分与を受けた人(登記権利者)の住民票
5 財産分与をした人及び財産分与を受けた人の委任状(代理人(司法書士)が申請する場合)
6 離婚の記載のある戸籍謄本
7 不動産の固定資産評価証明書
登記申請の際に添付する必要があるものですが、登記の際に納める登録免許税を計算するのにも必要です。法務局によっては固定資産税の納税通知書や固定資産名寄帳のコピーで対応してもらえるところもあります。登録免許税を計算するだけならお手元の納税通知書を用いて行うことができます。
下記の費用があります。
1 国に納める登録免許税
固定資産の評価額の1,000分の20の登録免許税がかかります。評価額は役所で取得できる固定資産の評価証明書に記載されていますが、お手元の固定資産税納税通知書にも不動産の評価額が記載されています。
2 司法書士に対する報酬
司法書士に協議書等の書類の作成や、財産分与登記を依頼した場合の司法書士に対する報酬。これは不動産の数や評価額等によって変わります。
3 その他郵便代等
不動産を売却してもローンが残ってしまうような場合は、夫婦の一方がローンを支払いながら住み続けるという形が一般的だと思います(不動産を売却してローンを完済し、それでも利益が出る様な場合は売却してその利益を夫婦で分けるという簡単な方法も取れることになります)。
不動産をどのように財産分与するかはうまく公平になるように調整・協議して決定していくことになりますが妻であるあなたが不動産に住み続けたいという場合、大きく分けて次の3つのパターンが考えられます。
1 不動産の名義と住宅ローンの債務者を夫のままで妻が居住する
この場合、不動産の所有権は夫のままで、住宅ローンも引き続き夫が支払い、妻が不動産に住み続けます。この方法だと夫が住宅ローンの支払いを滞らせた場合に最悪のケースでは立退きを迫られることになる等のリスクがあります。なお、話し合いにより無償で住むことにするか、夫に家賃を支払っていくという方法も考えられます。
2 不動産名義を妻に変更し、債務者を夫のままとする
住宅ローンは夫が引き続き支払い、所有権を妻に移転するケースです。3でも述べますが債務者を妻に変更することは妻に安定した収入がないと非常に難しいため、ローンの返済は夫がそのまま行っていく、という形になります。所有者を変更することについても銀行が了承するかどうかは不明ですのでローンの契約内容を確認して銀行に相談する必要があるでしょう。なお、話し合いにより夫から支払われる養育費を減額することや、他の財産を多めに夫に渡す等調整することも考えられます。また、債務者は夫のままですので1のケースと同様、夫が支払いを滞らせるというリスクはあります。
3 不動産の名義と金融機関の債務者を妻にする
この場合、名義も債務者も妻に変更され、実際に居住している者が住宅ローンを払っていくことになり、最も違和感のない良い方法のように思われるかもしれません。しかし、債務者を妻に変更するためには、妻が安定した職業(正社員である等)に就いているか、経済力があるか等金融機関の審査がありますので難しい方法と言えるでしょう。
なお、銀行の住宅ローンの契約書には、債務者である夫が居住することが住宅ローンの条件となっていることがほとんどであると思います。上記いずれの方法を取るにしても当初の契約と居住者が異なることになりますので銀行が了承する必要があります。必ず事前に銀行に相談しましょう。