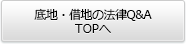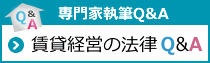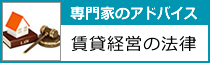底地・借地の法律で悩んでいる方、これから定期借地権等で土地を貸そうと検討している方、借りようとしている方に知っていただきたい底地・借地に関する法律のポイントをまとめています。
用法違反、建替え(増改築禁止特約・建替承諾)
基本的には地主と借主との間の信頼関係を破壊したものとして契約を解除することができると考えられ、損害が生じた場合には賠償を請求することができると考えられます。
土地を屋外駐車場にする目的でお貸しになったとのことですので、普通に考えますと建物を建てることを契約の目的とされていなかったのではないかと思われます。そうしますと、建物を建ててしまった借地人が契約に違反していることは明らかであるといえます。
もっとも、賃貸借契約は、地主と借主との間の信頼関係に基づく継続的な契約関係ですから、契約違反の程度が著しくなく、信頼関係を破壊したものといえない場合には解除は認められないものとされています(【Q地代を確実に払ってもらいたいので、1か月でも支払いが遅れたら即解除できるようにしたいのですが、可能ですか。】参照)。なお、2017年民法改正により「(相当の期間を定めて履行の催告期間内に履行がないときは解除することができる、という明文に続き)ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」とも明文化されています【改正後の民541条但書】)。
では、設問のケースはどうでしょうか。借地借家法という法律が参考になります。
建物の所有を目的とする土地の賃貸借の場合、借地借家法が適用されることになりますが、建物の所有を目的としない土地の賃貸借の場合、借地借家法は適用されませんので、民法が適用されることになります(【Q他人に土地を貸すと借地権が発生するのですか。】参照)。したがって、契約で期間を定めている場合にはその期間が満了すると契約は終了します(これに対し、建物所有を目的とする借地契約の場合には更新拒絶の正当事由が必要であることにつき【Q借地契約の期間が満了するので、更新せず、土地を返してほしいのですが、借地人は土地を使い続けたいと言っています。土地を返してもらうことはできますか。】参照)。期間を定めていない場合には、地主が解約を申し入れた日から1年後に賃貸借が終了します(これに対し、建物所有を目的とする借地契約の場合には地主による解約申入れが認められないことにつき【Q借地契約の期間の途中に、借地人から解約を申し入れられましたが、応じる義務はあるのですか。逆に、地主の方から解約を申し入れることはできますか。】参照)。また、土地の所有者が変わった場合には、借主は新たな所有者に対して賃貸借契約の存在を主張することができなくなります(これに対し、建物所有を目的とする借地契約の場合には借地権の登記又は借地上の建物の登記により借地権を第三者に対応できることにつき【Q土地を購入したのですが、その土地上に建物を建てて住んでいる借地人がいました。新しい地主は、借地人に対して土地の明渡しを求めることはできますか。】参照)。
このように、建物を所有する目的で土地を貸した場合と、それ以外の目的で貸した場合では、借地借家法の適用があるかどうかという非常に大きな違いが生じることになります。以上からしますと、屋外駐車場にする目的で土地を借りており建物を建てる契約にはなっていなかったのに、借地人が建物を建ててしまったことは、地主と借主との信頼関係を大きく破壊するものといえるでしょう。
そこで、基本的には、設問のケースでは契約を解除することができるものと考えられますし、損害が生じた場合にはその賠償を請求することができるでしょう。
もっとも、借地人が建物を建てたにもかかわらず、地主がこれを放置していたり、あるいは地代の値上げを請求したりしますと、暗黙のうちに地主が建物の建築を容認してしまったとして、賃貸借が建物の所有を目的とするものに変わったと認められてしまうこともあり得ます。
そこで、地主としては、日頃から現地を確認しておくとともに、建物を建築したのを知った場合には、直ちに契約を解除する通知を出しておくべきです。
また、建築の途中で事実を知った場合には、建築の中止を求めるなどの措置をとっておくことが必要ですし、場合によっては、裁判所に対し、仮に建築工事の続行を禁止するよう申し立てることも必要でしょう(仮処分といいます。普通に裁判所に建築工事の続行を禁止するように訴訟を起こすこともできますが、その審理をしている間に建築工事が続行されてしまうおそれがありますので、裁判所が建築工事を仮に禁止する手続です。)。
一般に土地賃貸借契約が建物所有を目的とするものであっても、借地人が地主に対し一定期間内に建物を建築することを特に約束したり、地主が借地人の建築する建物について一定の時期までに財産上の権利を取得したりすることが合意されている等の事情がある場合を別にすれば、借地人が借地契約上の債務として相当期間内に建物を建築すべき義務を負うものではありません。したがって、建物を建てずに空き地にしたままであったとしても、借地契約を解除することはできません。
これに対し、駐車場として利用していた場合は、建物を建築する目的で土地を貸したにもかかわらず、それ以外の目的で使用することは、合意された目的以外の用途に使用しないという借地人の債務に違反していることとなります。
ただし、地主と借地人の間の信頼関係の上に成り立っている賃貸借契約においては、地主と借地人との間の信頼関係が破壊されていない場合には解除は認められないものとされています(【Q地代を確実に払ってもらいたいので、1か月でも支払いが遅れたら即解除できるようにしたいのですが、可能ですか。】参照)。
建物所有目的であるにかかわらず駐車場として利用していたことを理由に借地契約を解除し明渡しを求めたという事案で、借地人は整地した以外には土地に変更を加えずに駐車場として使用していること、借地人が駐車場として使用していることを知りながら地主は解除の意思表示をするまで異議を述べなかったことなどを理由に、いまだ地主と借主との間の信頼関係が破壊されたとはいえないとして、解除を認めなかったという裁判例があります。
建物の種類等を制限する借地条件を設定することができます。借地条件に違反したことにより地主と借地人との間の信頼関係が破壊されたと認められる場合には、借地契約を解除することができます。
借地人は建物を所有しています。所有者は所有する物をどのように使用し処分するかの自由を有しています。そのため、借地人が借地上にどのような種類や構造の建物を建てるかも、借地人の自由に任されているようにも思えます。
しかし、どのような種類や構造の建物が建つのかは、建物の存続期間、地代額、建物買取額などの点から、地主にとっても大きな利害があるところです。そのため、借地契約で、借地上に借地人が建てる建物の種類、構造、規模又は用途などについて制限することも可能とされています。
したがって、借地人が建物の種類などを制限した契約と異なる種類や構造の建物を建ててしまった場合には、契約違反となり、借地契約の解除の問題が生じてきます。
もっとも、賃貸借契約の解除は、地主と借地人との間の信頼関係が破壊されていない場合には認められないものとされています(【Q地代を確実に払ってもらいたいので、1か月でも支払いが遅れたら即解除できるようにしたいのですが、可能ですか。】参照)。
信頼関係が破壊されたかについては、個別の事案ごとに、約束の内容や違反の程度など諸般の事情を総合的に考慮して決められることになるでしょう。
なお、借地人から、建物の種類、構造などを制限する契約(借地条件)を変更するように協議を求められることも予想されます。協議が整わない場合には、借地人は、裁判所に対し、事情の変更を理由に、借地条件を変更するように申立てを行うことが認められています。
具体的には、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間の協議が整わないときに、当事者の申立てにより裁判所が借地条件を変更することができるとされています(【Q借地人は、土地上に木造二階建ての建物を建築し、その建物を住居として使用しています。しかし、借地人は、土地上の建物を鉄筋コンクリート三階建てのものに建て替え、1階を店舗とし、2階を住居として賃貸し、3階に借地人自身が居住するつもりのようです。どのように対応すればよいですか。】参照)。その際、裁判所は、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。
見解が分かれており、特約が無効とされる可能性もあることに注意が必要です。
借地借家法では、同法が定める借地条件の変更等の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは無効とされています(借地法でも同様の規定がありました)。
抵当権は、抵当権を設定した者がそのまま目的物を使用収益することを認めるものですから、借地人は建物に抵当権を設定したとしてもそのまま使用することができますので、借地の使用関係には何ら変わりはありません。
したがって、借地人は、原則として自由に借地上の建物に抵当権を設定することができます(【Q借地人(賃借人)が、借地上に所有する建物に抵当権を設定する場合、地主の承諾は必要になりますか。】参照)。
そうすると、抵当権の設定を禁止する特約は、借地人が建物に抵当権を設定し、金員を借りられる利益を予め放棄させる点で建物の使用収益を制限するものであり、借地人に不利なものとして無効であるとも考えられます。借地法下の事例ですが、同様の考え方をして特約を無効とした裁判例があります。
他方で、裁判例のなかには、賃貸人の不利益を防止するために土地上の建物に担保物権を設定することを制限する内容の特約を締結することに合理性があることや、賃貸人の承諾を得ないで抵当権等を設定した場合でも、これが賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない事情がある場合には、解除権の行使が制限されると解することが可能であり、特約の効力自体を否定しなければ、賃借人の利益が著しく害されるとまでは認められないことなどを指摘したうえで、特約の効力を否定しなかったものがあります。
このように、借地上の建物に抵当権を設定することを禁止する特約が有効かどうかは争いがあり、地主としては、このような特約が無効とされる可能性があることに注意しておく必要があるでしょう。
借地人の行為により地主と借地人との間の信頼関係が破壊されたと認められる場合には、借地契約を解除することができます。
土地の形状変更にも色々な場合があります。
例えば、建物所有を目的とする借地契約の目的となった土地が傾斜地であった場合には、借地人が土地を整地して建物を建築する約束があると考えられることが多いでしょう。
また、土地を盛土したり土留めを設けたりした場合には、土地の利用価値を高めることになるでしょうから、信頼関係が破壊されるような形状変更とはいえないと考えられます。
逆に、土地の形状変更の結果、価値を著しく減少させたり、土地の復旧を不可能にするような損害を与えた場合には、信頼関係が破壊されたとして解除が認められることになると考えられます。
なお、土地の形状を変更してはならないという特約も、土地の形状変更の態様によっては土地の価値を著しく減少させたりするおそれがあるため、合理性が認められる限り、有効であると考えられています。
参考までに、地下駐車場を作るために土地の掘削を行ったという事案に関する裁判例を挙げておきます。
この事案では、借地人の行った掘削工事が土地のほぼ全域にわたって地面を深さ2メートル以上まで掘り下げて大量の土を搬出するという大規模なものであったため、湧水が生じ、近隣にも支障が生ずるといった事態を招いていました。また、土地を埋戻しても地盤が軟弱化してしまって建物建築には一定の補強が必要とされる程に土地の形質に影響を及ぼしていました。裁判所は、土地所有者と異なり、借地人には自ずから利用の態様に制限を伴うことが当然であり、地主の承諾のない限りこのような土地の形状を著しく変更することは許されないとして、解除を認めました。
借地人の行った掘削工事は、土地の価値を著しく減少させ、土地の復旧を不可能にするような損害を与えるものといえますから、解除が認められたのも頷けるところです。
地主は越境されてしまっている側の土地の所有者でもあるわけですから、所有権に基づいて建物の越境部分の除去や越境された土地の明渡しを求めることができます。
では、越境を理由として、契約を解除し借地自体の明渡しを求めることはできるでしょうか。
借地人は、借地契約で定められた目的や用法に従って目的物を使用しなければなりませんので、借地契約の対象となっている土地(借地)について、用法の契約違反があれば、解除の理由となり得るところです(ただし、信頼関係が破壊されていない場合には解除が認められないことになります。【Q屋外駐車場にする目的で土地を貸したのですが、借地人が建物を建ててしまいました。契約を解除したり、損害賠償請求をすることはできますか。】 【Q建物を建築する目的で土地を貸していたのに、借地人が建物を建てずに空き地にしたままです。借地契約を解除できますか。借地人が駐車場として利用していた場合はどうでしょう。】参照)。
設問の事案で問題となっているのは、借地契約の対象となっていない土地への越境であり、直ちに借地の用法に違反があったとはいえないようにも思われます。
しかし、越境は他人の土地所有権への侵害であり、不法行為ともなりうる行為です。また、借地と地主側の土地上の建物が極めて近接していて、借地人所有の建物の越境が地主の建物の使用に非常に大きな支障を及ぼすような場合には、用法違反に当たる可能性が高いといえます。また、越境部分の除去が可能であり、地主が求めているのにこれに応じない場合など、借地契約関係上の信頼関係が破壊されており借地契約の解除が認められる余地もあると考えられます。借地契約を解除できるかを判断するにあたっては、それぞれの土地上の建物の位置関係、越境している建物による地主の土地への影響、越境の経緯などをよく検討する必要があります。