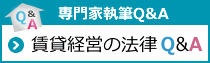底地・借地の法律で悩んでいる方、これから定期借地権等で土地を貸そうと検討している方、借りようとしている方に知っていただきたい底地・借地に関する法律のポイントをまとめています。
地代、敷金・権利金
地代の金額については、原則として当事者が自由に決めることができます(契約自由の原則)。とはいっても、地主としては、なるべく高い地代にしたいでしょうし、反面、高く設定しすぎると借り手がいなくなりますので、相当な金額を把握しておきたいところではあります。
新規地代の評価には次のような方法があり、厳密な評価額を得るには不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する必要があります。
対象不動産について、価格時点における基礎価格を求め、これに期待利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して地代を求める方法です。
その名のとおり、周辺の新規の借地契約の地代の額を比較して地代を求める方法です。新規の借地契約の地代金額について、確かな情報を数多く入手できた場合には、算定金額の信頼性は高いものとなりますが、情報の入手が難しい場合も多いと思われます。
収益分析法とは、一般の企業経営に基づく総収益を分析して対象不動産が一定期間に生み出すであろうと期待される純収益を求め、これに必要諸経費等を加算して地代を求める方法です。
地代の額が、諸般の事情から不相当に低くなった場合には、地主は借地人に対し地代の増額を請求することができます。
考慮されるべき諸般の事情としては、土地に対する公租公課の増額や土地の価格の上昇などの経済事情の変動があります。また、周辺の同じような土地の地代の額と比較して極めて低いなどの事情も考慮されますが、契約の期間、内容、土地の位置及び地形、権利金などの有無や多寡など、個別の事情により補正が必要となる場合がほとんどです。
ただし、当事者間に一定の期間は地代を増額しないという特約がある場合には、増額請求は認められません。
もっとも、「一定の期間」がかなり長期間とされているような場合に、特約当時には予測できないほど経済的事情が激変し、従前の地代を維持するのが著しく公平に反するような場合もあります。そのような場合には、事情変更の原則が適用されて、特約の効力は失われ、増額請求も認められると考えられています(なお、手続について【Q建物所有者に貸している土地の地代を値上げするためには、どのような手続をとればよいのですか。】参照)。
地主としては、まずは、借地人に対し「相当であると考える金額」に地代を増額したいとの請求をすることになります。増額請求をした日にちが後々問題となる可能性もありますので、内容証明・配達証明の郵便で送るべきでしょう。借地人が増額請求を受け入れたり、増額請求をきっかけとして話し合いとなって、金額がまとまれば、地代の増額が認められるということになります。
借地人が増額請求を承服せず、話し合いでもまとまらなければ、地主は、裁判所での手続をとらざるを得ないことになりますが、まずは、民事調停の申立をしなければなりません(調停前置主義)。民事調停とは裁判所が間に入って話合いによる解決を模索する手続ですが、当事者間に合意が成立する見込みがない場合であっても、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があるときは、調停委員会は、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができ、調停が成立したものとみなされます。
調停が成立しない場合には、訴訟を提起することになりますが、継続する借地契約の地代として適正な金額を算定する方法としては、次のようなものがあります。
従前の地代に地価・物価等の上昇率を乗じて算定する方法です。
底地価格に期待利回りを乗じ、これに必要経費を加えて算定する方法です。
近隣の類似の土地の地代の相場と比較して算定する方法です。
経済的価値に応じた適正地代と実際に支払われている地代との差額を地主と借地人とで配分することにより算定する方法です。
固定資産税と都市計画税の合計額の2倍ないし3倍と算定する方法です。
訴訟実務では、裁判官は、不動産鑑定士の鑑定意見を参考にして、これら複数の方法による金額を比較勘案し、契約の経緯や個別の事情などを考慮して地代額を算定するという総合方式によることが一般的となっています。
地代の額が、諸般の事情の変更から不相当に高くなった場合には、借地人は地主に対し地代の減額を請求することができます。不相当に高くなったかどうかを判断する際に、考慮される諸般の事情としては、借地借家法上は、土地に対する公租公課の減額や土地の価格の下落などの経済事情の変動、周辺の同じような土地の地代の額と比較して高い状況などの例が挙げられています。また、判例によれば、賃料額決定の際に重要な要素として考慮された事情も含まれるとされています。
地下鉄の駅の場所の計画変更により、その土地の価格が大幅に下落したり、それに伴って公租公課が減額となったといった事情が認められたりして、現在の地代が不相当に高額となったといえるのであれば、減額請求も認められると考えられます。
しかし、そのような土地の価格や公租公課の変動といった事情も特になく、単なる借地人の見込み違いであって、地下鉄の駅の場所の計画が賃料額決定の重要な要素とされていなかった場合など、地代が不相当に高額となったとはいえない場合には、減額請求は認められないと考えられます。
地主(借地権設定者)が借地人に対して地代の値上げを要求することは自由であり、交渉の結果、借地人が値上げに応じれば地代は増額されます。
この交渉において、もし借地契約のなかに借地上の建物の増改築を禁止する旨の特約(増改築禁止特約)がある場合には、地主側から、「改築を承諾する代わりに、地代の値上げに応じてもらいたい」と申し出るなど、改築の承諾を交渉材料にすることが考えられます(増改築禁止特約がある場合、原則として、借地人は地主の承諾なく借地上の建物を改築することができません。)。
なお、地主が改築を承諾しない場合、借地人には、裁判所に申し立てて、地主の承諾に代わる許可を得て改築をするという手段があることに注意が必要です。この裁判において、裁判所は、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができるとされています(これにより地主の被る不利益が填補されることが期待されています。)。(【Q借地人が地主への連絡もなく、借地上の建物を増築しようとしています。これに対して地主として何か主張できますか。借地人から借地上の建物を増築することへの承諾を求められた場合には、どうすればよいですか。】参照)。
地代については当事者が自由に合意することができますので、借地契約の中で、一定期間経過後は地代を一定割合増額するとの取り決めをしておくことも可能です。例えば、借地人が借地上に大規模な商業施設を建設して営業する目的を有している場合に、施設完成までは地代を低額におさえ、施設完成時点である程度増額し、営業が軌道に乗ると思われる時期に再度増額するといった特約は、合理性も認められ有効であると考えられます。
ただし、当初は合理性が認められるような増額特約であっても、増額の基準を定めるにあたって基礎となっていた事情が失われ、土地に対する公租公課の減額や土地の価格の下落などの経済事情の変動、あるいは、周辺の同じような土地の地代の額と比較して極めて高い状況となるなど、特約を維持することが不相当である場合には、もはや特約を自動的に適用して増額の効果を生じさせることはできないと考えられています。例えば、土地の価格が上がり続けるであろうと考えられていたバブル時代に合意された「3年ごとに10%ずつ地代を増額する。」といった特約は、バブルの崩壊により基礎となっていた事情が失われ、もはや不相当になっており、その効力は消失しているものと考えられます。
一般に、契約は債務の不履行があれば、相当期間を定めて催告し相当期間内に履行がなければ解除することができます。
しかし、借地契約は、1回限りの履行がなされる契約と異なり、継続的に借地人が土地を使用収益する点に特徴があります。そして、地主と借地人は、お互いの信頼関係に基づく関係にあるので、1回の債務不履行があったからといって、直ちに契約関係が消滅するような結果を認めるべきではなく、信頼関係が破壊される程度に至って初めて契約の解除が認められると考えられています(信頼関係破壊の理論)。
仮に、1か月分でも地代の支払いが遅れたら催告なしに契約を解除することができるという特約を入れていたとしても、1か月分の支払いの遅れだけでは、まだ信頼関係が破壊されているとまではいえませんので、契約の解除は認められないと考えられます。
信頼関係が破壊されたといえるかは、地代滞納の期間や借地人の態度、支払遅延にやむを得ない事情があるかなど、様々な事情を斟酌して判断されることになります。
なお、信頼関係の破壊が著しい場合には、地主は催告することなく契約を解除することができると解されていますが、その判断には微妙な点も含まれていますので、解除の効力を発生させるためには、相当期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合に解除するという手順を踏んだ方が確実といえるでしょう。
支払いが滞っている地代を取り立てる基本的な方法は、訴訟を提起して判決を取得し、その判決に基づいて借地人の財産を差押えて強制執行の手続をとることです。ただし、訴訟手続では、証拠をそろえて提出する必要があり、相手方を呼び出して反論がないかを確認しなければならず、手間や時間もかかります。
この点、同じ裁判所での手続ではありますが、「支払督促」という手続があります。この手続は、申立ての際に証拠を付ける必要はなく、訴訟に比べ費用(印紙代)も少なくて済みます。裁判所は、申立書の内容を審査し(債務者である借地人を呼び出して意見を確認等することは行われません)、理由があると認めれば、支払督促を借地人に送ります。送達から2週間以内に異議申立がなければ、地主の申立により、再度、仮執行宣言を付した支払督促を送ります。これにより、地主は借地人に対し強制執行をすることが可能となります(適法な異議申立てがあると、通常の訴訟に手続が移行します)。仮執行宣言を付した支払督促が送られた後、借地人から2週間以内に異議申立がなかった場合には、支払督促は確定判決と同一の効力を有することになり、内容を争うことができなくなります(適法な異議申立てがあった場合には、やはり通常の訴訟に手続が移行します)。
さらに、借地契約を公正証書にしておき、その中に「金銭債務の履行を怠った場合は、直ちに強制執行に服する。」旨を記載しておけば、金銭債権については、裁判等の手続を経なくても強制執行をすることが可能となります。
また、訴訟手続をとった場合、判決が出るまでにはある程度時間がかかります。そのため、その間に借地人の財産が処分されてしまう可能性もあります。そこで、訴訟を提起する前に、借地人による財産の処分や弁済の受領の効力を否定することができる仮差押えの手続をとっておくことが効果的です。仮差押えをしておけば、確定判決を得たあとに、仮差押えをした財産について、そのまま強制執行することができます。借地人に対しては、借地上の建物や建物賃借人に対する家賃債権、家賃が振り込まれる銀行口座などについて仮差押えをしておくことが考えられます。
地主には、地代債権をより確実に支払ってもらえるよう、借地人が保有している一定の財産について、法律上、「先取特権」が与えられています。「先取特権」とは、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることが法律上当然できる権利です。
まず、地主には、民法により、借地や借地上の建物に備え付けられた動産等について、「先取特権」が与えられています。
また、借地権の登記がされている場合、借地借家法により、地主は、借地上にある借地人の建物について、弁済期にある地代債権の最後の2年分について「先取特権」を有するとされています。ただし、この「先取特権」は、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権や、地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には劣後します。
地代の不払を理由として、地主が借地契約を解除するためには、原則として、相当な期間を定めて債務者に対して支払を催告し、その期間が経過した後に解除の意思表示をすることが必要です。解除の意思表示が借地人に到達するまでは、契約関係は存続していますので、その時までになされた弁済は有効です。
したがって、催告期間経過後であったとしても、解除の意思表示が到達する前に地代が支払われたのであれば、地主は、もはや契約を解除することはできなくなります。
問題となるのは、相当な期間を定めて催告するのと同時に、期間内に支払がない場合には借地契約を解除する意思表示もしていた場合です。
理論的には、催告期間内に支払がなければ、期間満了と同時に解除の効果が発生し、契約関係が消滅することになります。その後に地代が支払われたとしても、地代弁済の効力は生じないことになります。
ただし、催告期間が相当であるかは、客観的で絶対的な期間が決まっているわけではなく、相対的な判断です。また、支払が催告期間経過後であったとしても、支払いまでの期間がそれほど長くないのであれば、当事者間の信頼関係が破壊されたとまではいえないこともあり得ます。期間経過後2、3日以内に支払をしたのであれば、信義則または権利濫用の法理を用いて、解除を認めないとの結論も十分考えられるところです。
なお、2017年民法改正により「(相当の期間を定めて履行の催告期間内に履行がないときは解除することができる、との定めに続いて)ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」とも明文化されていることにも留意してください【改正後民541条但書】)。
敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます。借地契約締結にあたり敷金が交付された場合、敷金は契約が終了し土地の明け渡しがなされた後で借地人に返還されることになります。敷金には特別な合意がないかぎり、利息は付かないというのが一般的な取扱いです。借地人に地代の不払等債務の不履行がなければ、全額返還されますが、地代不払いや原状回復の不履行がある場合には、不払い分や原状回復費用を差し引いた上で、借地人に返還されることになります。借地人が地代を滞納している場合には、地主は催告をした上で借地契約を解除し、未払地代等を敷金から充当することもできます。また、不払い額や損害額が敷金を超える場合には、その差額をさらに請求することも可能です。
敷金は、契約終了時に清算されることを予定して交付される金銭ですので、契約の継続中に地代の不払があったとしても、自動的に敷金が充当されることにはなりませんし、借地人からも滞納額に充当するよう要求することはできません(地主が未払地代の支払いに充てることは可能です)。
したがって、地主は、未払の地代を相当期間内に支払うよう催告をし、それでも支払いがなされないのであれば、借地契約を解除することができます(【Q地代の支払いが滞っていたので、期間を定めて支払を催告したのですが、期間経過後に地代を支払ってきました。借地契約を解除することはできないのですか。】 【Q借地人が借地契約を守ってくれません。借地契約を解除することはできますか。】 【Q地代を確実に払ってもらいたいので、1か月でも支払いが遅れたら即解除できるようにしたいのですが、可能ですか。】参照)。
土地の所有者が借地人に土地を賃貸し、借地人が賃貸借について対抗要件を備えている場合に、所有者が土地を譲渡してその所有権が移転したときは、原則として新所有者は賃貸人としての地位を当然に承継します。この場合、敷金の返還債務も新所有者に承継されますので、新所有者が所定の時期に借地人に対して敷金を返還することになります。
敷金は原則として旧借地人に対して返すことになります。
借地権付建物の譲渡などにより借地人が変わった場合、敷金は地主と新借地人との間には当然には引き継がれないものと解されています。したがって、何らの取り決めもない場合には、旧借地人は地主に対して敷金の返還を請求できることになります。
引き継ぎを否定する理由としては、旧借地人の差し入れた敷金をもって将来新借地人が新たに負担するかもしれない債務までも担保しなければならないものと解することは、敷金交付者にその予期に反して不利益を被らせる結果となり相当でないことが挙げられています。
反面、地主は敷金という担保を失うことになり不都合ではないかとの指摘もありますが、地主としては、借地権の譲渡に承諾を与えるときに、新借地人が新たに敷金を差し入れることを条件とすることが可能であり、地主の利益が不当に損なわれるわけではないと考えられています。
ただし、借地権譲渡の条件について地主との間で話がまとまらなければ、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可の裁判を求めることができますが、その許可がなされる際に、同額の敷金を差し入れることが条件とされる保証はありません。そこで、地主としては、あらかじめ借地人との間で、借地権を譲渡する際には敷金返還請求権もともに譲渡しなければならないとか、新借地人が敷金を差し入れるまでは、旧借地人の敷金をもって新借地人の債務を担保するといった特約を締結しておくことが望ましいといえます。
なお、2017年民法改正により、賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき、その時点で敷金返還債務が生ずると明文化されました(改正後の民622条の2第1項)。
借地契約が締結される際に借地人から地主に交付されるまとまった金銭であり、借地契約終了の際に借地人に返還されることが予定されていないものを「権利金」と呼んでいます。権利金がどのような性質や効力を有するかは、当事者がどのような趣旨で権利金を授受したのか、によって判断されることになります。ただし、当事者の意図がはっきりしない場合も多く、そのような場合には、当事者の意図を客観的・合理的な基準によって解釈することになりますが、概ね、次の3つのいずれかに当てはまると考えられます。
借地権が設定されるとそれだけ土地所有権の実質的な内容が制約を受けることになりますが、この制約の対価として交付がなされる権利金のことをいいます。権利金が設定の対価として交付されたのであれば、当事者は借地権により強い権利を与える趣旨であるとの解釈が可能な場合もあると考えられています。
定期に支払われるべき地代について、本来であれば高額となるところを低額に抑えるために、地代の一部前払いの趣旨で交付される権利金のことをいいます。かかる権利金の交付は、地代の値上げ率を緩和する役割をもっているともいわれています。
借地の所在地が営業地などとして、他の土地に比べすぐれている場合に、そのような場所的利益に対する対価として交付される権利金のことをいいます。近隣に有名な観光施設があり店舗営業に好都合であるようなケースが典型例ですが、その施設が廃止され場所的利益が失われた場合には、権利金の一部返還を求められることも考えられます。