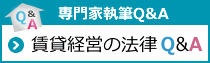底地・借地の法律で悩んでいる方、これから定期借地権等で土地を貸そうと検討している方、借りようとしている方に知っていただきたい底地・借地に関する法律のポイントをまとめています。
底地・借地の入門
「借地」と「底地」を理解していただくためには、まず「借地」とはなにかを御理解いただくことが大事です。以下、できるだけわかりやすく述べていきましょう。
あなたが、何も建物が建っていない更地の状態の土地を所有しているとします。あなたは、その土地の完全な所有権をもっているとしますと、その土地を自分で使ってもよいですし、人に貸してもいいです。貸す場合にも、建物をご自分で建ててから、建物を人に貸すこともできますし、建物はご自分では建てず、あなたは土地だけ貸して、あとはその借主が建物を建てて所有し、居住することもできます。
以上のように、完全な所有権を有している更地状態の土地をあなたが所有していれば、あなたはご自分の好きなようにその土地を利用できます。当然ですね。
あなたが完全な土地所有権を有しているとして、「あなたが自ら使う」のではなく、「他の人に貸す」ことにしたとしましょう。土地を他の人に貸して、その人が自分で建物を建てることをあなたが認めるわけです。この場合、「他の人に貸す」と言葉では一言でいえるわけですが、法律的には、いろいろな場合があります。例えば、土地の貸主と借主との間で建物所有のための「使用貸借契約」を結ぶ場合もあれば、建物所有のための「賃貸借契約」を結ぶ場合もあります。また、建物所有目的のための「地上権設定契約」を結ぶ場合もあります。日本の民法において、前者の「使用貸借契約」や「賃貸借契約」は、いわゆる「債権」として位置づけられているものですが、後者の「地上権設定契約」は「物権」と位置づけられています。契約がどれであるかによって、地主と借主との権利義務関係がかなり違ってくるのです。
いわゆる「ただで(無償で)」貸し借りをする「債権」の契約をいいます。ここでいう「ただ(無償)」ですが、お金の授受が全くないことを指すことは当然ですが、若干(例えば、固定資産税レベル)の金員の授受のみがある場合にも、実質的には「ただで」と評価され、使用貸借契約とされる場合もあります。
そして、「使用貸借契約」だと評価された場合、一般的には、「使用貸借契約」には次のような性質があると言われています。一般的には、と申しますのは、当事者間で別の合意をすれば、その合意が優先するという面があるからです。
具体的にみていきましょう。
「使用貸借契約」とは、当事者の一方(貸主)がある物を引き渡すことを約し、相手方(借主)がその受け取った物について無償で使用収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって成立する契約と規定されています(2017年民法改正後の593条)。
使用貸借契約の場合、貸主は、借主の使用収益を妨げないという消極的義務を負うにとどまり、土地の土盛りをするなどの使用収益をさせるべき積極的義務は負いません。
他方、借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければなりません(2017年民法改正後の594条1項)。借主は、契約の趣旨に照らし善良な管理者の注意をもって目的物を保存する義務も負っています(2017年民法改正後の400条「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」)。
また、使用貸借契約の借主は、貸主の承諾なく第三者に使わせてはいけません。
使用貸借契約の終了については、①使用貸借の期間を定めたときは、期間満了により終了し、②使用貸借の期間を定めなかった場合で使用及び収益の目的を定めたときは、その目的に従い使用及び収益を終えることにより終了し、さらに③借主の死亡によって終了します(2017年民法改正後の597条)。以上は、それが生じれば当然に使用貸借が終了するものですが、2017年民法改正の598条は、当事者の意思表示によって使用貸借を終了させる行為を使用貸借の「解除」と位置付けた上で、解除原因を定めています。④貸主は、「当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合で使用及び収益の目的を定めた」ときは、その目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除ができます。⑤当事者が「使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかった」ときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができます。⑥借主は、いつでも契約の解除ができます。
以上のほかにも、借主の使用収益義務違反による解除もあります(2017年民法改正後の594条3項)。
以上の「解除」によっても使用貸借は終了します。
使用貸借契約が終了したときの借主の「附属物の収去義務」や「原状回復義務」は、2017年民法改正後の599条が定めています。借主が借用物を受け取った後に借用物に附属させた物について、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負いますが、附属物を分離できない場合や附属物の分離に過分の費用を要する場合は、貸主は収去義務の履行を請求することはできません(改正後599条1項)。また、借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負います(改正後599条3項)。
以上が使用貸借契約の特徴です。
次に「賃貸借契約」です。いわゆる「賃料(地代)を払って(有償で)」貸し借りをする「債権」の契約をいいます。
「賃貸借契約」とは、当事者の一方(貸主)が、ある物の使用及び収益を相手方(借主)にさせることを約し、相手方がこれに対して、「その賃料を支払うこと」及び「引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還すること」を約することによって成立する契約と規定されています(2017年民法改正後の601条)。
この賃貸借契約は、当事者間で、いくらで「貸す・借りる」等の合意がなされただけで、引渡しがなくても「契約成立」します。これを「諾成契約」といいます。
賃貸借契約による借地の場合、貸主は、目的物の土地を借主に引渡し、必要があれば土地の修繕をなし、第三者により借主の使用収益が妨げられたときには妨害を排除するなど、借主(借地権者)に対し、使用収益をさせるべき積極的義務を負います(【Q地主は、賃貸借契約を締結して、その土地を借地人に引き渡した後も、借地人に対して何か義務を負うのですか。】参照)。
他方、借主は、貸主に対し、地代(賃料)を支払う義務を負い、宅地としての土地使用収益にあたっては、契約又はその目的物の性質によって定まった用法を遵守し、善良なる管理者の注意をもって宅地を保管する義務を負います。
賃貸借契約の場合も、借主は、貸主に無断で、借地権を譲渡したり、転貸してはなりません。
なお、2017年民法改正により、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときか、②急迫の事情があるときには、賃借人は目的物の修繕をすることができると定められました(改正後の民607条の2)。
建物を建てるために地主に地上権を設定してもらうという方法もあります。「賃貸借契約」も「使用貸借契約」も、いずれも「債権」であるのに対し、「地上権」は「物権」です。地上権設定により、借主(地上権者)は、建物を所有するために土地を直接支配する権利(物権)を有することになります。
地上権は、物権であり、借主は、この権利を貸主の承諾なしに譲渡したり担保に供したりすることができます。また、地上権者は、利用を妨害する者に対してその除去を求める物権的請求権をもちます。
また、地上権者である借主は、地上権の登記をするよう請求する権利が認められています。債権である賃貸借契約の場合は認められていません。
地上権の場合、地上権設定時あるいは途中で地代を支払うべき義務を負うのが一般的ですが、無償であっても地上権は認められます。
以上、「使用貸借」「賃貸借」「地上権」を説明して参りましたが、いよいよ本題の「借地」の話に入ります。
いわゆる借地権が発生するとは、「借地借家法の適用がある借地権」のことをいいます。そして、「借地借家法の適用がある借地権」とは、「建物所有を目的とする賃借権(賃貸借契約)」または「建物所有を目的とする地上権」を言います。以上の定義から明らかなように、建物所有を目的とする「使用貸借契約」を締結しても、これは「借地借家法の適用がある借地権」とはいえません。
したがって、借地権には、「地上権(物権)」の場合と「賃借権(債権)」の場合があるわけですが、実際上は、「地上権」が設定されることはまれで、多くは「賃借権」です。
その理由として、貸主が借主に対し借地権を設定し、そのうえで同土地上に借主が建物を築造し所有している場合を考えてみましょう。
借地権が「地上権」の場合ですと、借主が貸主へ土地に地上権設定登記をするよう請求してきたときはこれを拒むことができませんが、借地権が「賃借権」の場合ですと登記を拒むことができます。
また、借主が築造した建物を第三者に譲渡する場合、原則として借地権の譲渡を伴います(【Q借地人が借地上に所有する建物を第三者に「譲渡」することは、借地権の譲渡や転貸に当たるのですか。地主の承諾は必要になるのですか。】参照)。借地権が「地上権」の場合、貸主の承諾を要しませんが、借地権が「賃借権」の場合ですと、譲渡には、貸主の承諾を得なければなりません。
以上のように、貸主からしますと、「地上権」たる借地権を設定した貸主(地主)は、借地人の登記請求を拒否できませんし、借地上の建物を地上権たる借地権が、自己(貸主)の承諾なく、自由に譲渡されることによって、自己の所有地を見知らぬ人に利用されることになるため、そのような「地上権」を設定することを避けたほうがよい、「賃借権」を設定したほうがよい、という考えになるのです。
いわゆる「底地」とは、借地権付の土地の所有権のことをいいます。「土地の完全な所有権」から「借地権」を除いたものが「底地」というイメージです。言い換えますと、「借地権」に「底地権」を加えて、「土地の完全な所有権」になる、ということです。
いわゆる借地権とは、「借地借家法の適用がある借地権」のことをいいます。そして、「借地借家法の適用がある借地権」とは、建物所有を目的とする賃借権または地上権を言います。
以上の定義からすると、建物所有以外の目的であったり、建物所有目的であっても「使用貸借契約」である場合は「借地借家法の適用がある借地権」にはあたりません(使用貸借契約につき【Q借地・底地とは何ですか。】参照)。
建物所有以外の目的の賃貸や「使用貸借契約」であっても、権利が全く発生しないわけではありませんので、あとは言葉の問題になりますが、いわゆる「借地権」と表現する場合は、「借地借家法の適用がある借地権」を指すのが一般です。その場合のポイントは大きくわけて2つあって、1つは、「建物所有目的」でなければならないこと、もう1つは、「賃借権又は地上権」であって、「使用貸借契約」の場合は含まれない、ということです。
したがって、「他人に土地を貸す」というだけでは「借地権」が発生するとはいえず、「建物の所有目的」があるか、「貸し方」(「借り方」)が「賃借権又は地上権」かによって「借地権」が発生するかが判断されます。
「借地借家法の適用がある借地権」、すなわち「借地権」が発生するためには、単に「土地を貸す」だけでは不足です。「借地権」が発生するためには、1つは、「建物所有目的」でなければなりません。さらに、もう1つは、「賃借権又は地上権」でなければなりません。いくら「建物所有目的」があっても、「使用貸借契約」からは「借地権」は生じないということです(【Q他人に土地を貸すと借地権が発生するのですか。】参照)。
「ただで貸す」場合は、2つあります。ひとつは、「債権」を発生させる「使用貸借契約」に基づき、ただ(無償)で貸す場合です。もう1つは、「地上権」という「物権」を設定し、ただ(無償)で貸す場合です。
そして、前者の「使用貸借契約」であれば、「借地権」は発生しませんが、後者の「地上権」の場合は「建物所有目的」があれば「借地権」が発生します。
後者のような強い「地上権(物権)」設定契約があったといえるためには、そのような内容が記載された契約書が存在したり、登記があるとか、その他の諸事情が必要と考えられます。
親族間においては、契約書などが存在しないことが珍しくありません。しかしながら、将来の紛争を避けるためにも、きちんと契約書を交わしておくことが重要です。
借地借家法は、「借地権」を「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義しています。
「建物の所有を目的」とするとは、「主たる目的」がその土地に建物を築造し所有することにある場合を意味します。
これに対して、建物の築造・所有が、借地使用の「従たる目的」の場合は、「建物の所有を目的」とするとはいえず、借地借家法の適用はありません。
以下、具体例として、判例の考え方をつかんでおきましょう。
ゴルフ練習場についての判例として、ゴルフ練習場として使用する目的でされた土地の賃貸借は、その主たる目的は、特段の事情がない限り、土地自体をゴルフ練習場として直接利用することにあったと解すべきであって、たとえ当初からその土地上にゴルフ練習場の経営に必要な事務所用等の建物を築造、所有することを計画していたとしても、それはその土地使用の従たる目的にすぎなかったといわなければならないとして、「建物の所有を目的とする」賃貸借であることを否定した判例があります。
自動車教習場についての判例として、「契約当事者は単に自動車運転教習コースのみならず、自動車学校経営に必要な建物所有をも主たる目的として本件賃貸借契約を締結したことが明らかであり、かつ、自動車学校の運営上、運転技術の実地練習のための教習コースとして相当規模の土地が必要であると同時に、交通法規等を教習するための校舎、事務室等の建物が不可欠であり、その両者が一体となってはじめて自動車学校経営の目的を達しうるのである」として、建物の所有の目的とする賃貸借であることを認めた判例があります。
駐車場としての借地については、空き地を平面駐車場として賃借する場合には、「建物の所有を目的」とするものとはいえないと考えられます。このような駐車場の入口に車両管理等のための事務所を所有しても、特別のことがなければ、その建物所有は付属的なもので借地の主たる目的ではないと認定されることが多いと考えられます。
いわゆる借地権が発生するとは、「借地借家法の適用がある借地権」のことをいいます。そして、「借地借家法の適用がある借地権」とは、「建物所有を目的とする賃借権」または「建物所有を目的とする地上権」をいいます。建物所有を目的とする「使用貸借権」は「借地借家法の適用がある借地権」とはいえません(【Q他人に土地を貸すと借地権が発生するのですか。】参照)。
以上のことからも明らかなように、(1)いわゆる「借地権」とは、「(土地)賃借権」の場合か「地上権」の場合かのどちらかであり、「借地権」とはそれらを包含する概念であること、(2)さらに、単なる「(土地)賃借権」とか「地上権」では不足であり、それが「建物所有目的」であることが必要で、「建物所有目的」が認められることで、はじめて「借地権」と評価されることが重要です。
借地借家法のもとにおいて、普通の借地権の存続期間は30年以上であり、期間満了時に借地人が契約の更新を請求したり、または、土地の使用を継続していますと、貸地人に更新拒絶の正当事由がない限り、借地契約はさらに更新されることになります(【Q借地契約の期間について、どのようなルールがありますか。】 【Q借地契約の期間が満了するので、更新せず、土地を返してほしいのですが、借地人は土地を使い続けたいと言っています。土地を返してもらうことはできますか。】参照)。
以前の旧借地法のころから、「いったん土地を貸したら返ってこない」などと言われており、土地所有者に対し、借地契約の更新により半永久的に土地を貸さなければならないという不安を発生させ、結果として、貸地をすることを控えるという実態がありました。
そこで、一定の借地期間が経過すれば契約は更新されずに借地権も消滅するという形態の借地権、いわゆる3種類の「定期借地権」が平成3年の借地借家法により新たに立法化されました(【Q一般定期借地権とは何ですか。】 【Q事業用定期借地権設定契約とは何ですか。】 【Q建物譲渡特約付借地権とは何ですか。】参照)。
以上のとおり「普通の借地権」はもちろんのこと、「定期借地権」であっても契約期間は最も短くて10年であり、建物を建てる人に土地を貸す、というのは、その借地人と相当長い関係となることを意味します。
信頼している人に貸すのであり「その人は、自分(貸主)が返して欲しいといえば、すぐ返してくれるだろう」という「甘い期待」は厳禁です。いったん貸してしまうとなかなか返ってくることはないと考えておくべきです。
さらに、借地人が、将来、資力不足で地代の不払いなどを起こさないか、さらに、借地利用について地主らに迷惑をかけたりしないか、契約違反や債務不履行などを起こさないか、ある意味、「見込み」とならざるを得ないとしても、検討が必要となりましょう。
「普通の借地権」の設定において、必ずしも契約書が必須とされているわけではありませんが、やはり将来の紛争予防のためには、契約書を締結しておくべきです。
「借地権割合」は、更地価格に対する「借地権価格」の割合をいいます。
借地権のついている土地の底地の価格は、借地権の価格よりかなり低いことが珍しくありませんが、逆に、借地権は、大きな財産的価値を有します。また、借地権も当然、相続の際には課税の対象となります。
財産の評価をするために、標準的な借地権割合を公示するものとして、路線価図に記載されている借地権割合があります。この路線価図や評価倍率表は、国税庁のホームページで閲覧することができます。
一般に地価が高い地域ほど借地権割合は高くなり、東京の商業地では、80%~90%というところもあります。
ただし、個々の借地における借地権割合は、借地契約の内容によって異なるため、路線価図などの借地権割合は参考として考えておいた方がよいでしょう。
「借地権価格」とは、借地権の有する価値のことを意味します。借地権価格については、更地価格に借地権割合(相続税路線価図に表示されている借地権割合)を乗じることによって概算できますが、より厳密な価格が必要な場合等には、不動産鑑定士に依頼して鑑定評価をしてもらう必要があります。
「定期借地権」のうち、例えば、「事業用定期借地権」は公正証書を作成しなければならない、とか、「一般定期借地権」は「公正証書等の書面」で特約されることが必要で、必ずしも、公正証書によらずとも、書面で締結する必要がある、などと言われているものはありますが、「普通の借地権」については、「契約書」は必ずしも必要ではありません。
しかしながら、契約内容を明確化し、将来の紛争を防止するためには、「契約書」を交わすことをお勧めします。
「借地契約書」は、市販のものを購入することもできますし、インターネットなどで入手することも可能です。
しかしながら、それらのものは、あくまで、書式、あるいは、雛形であったり、あるいは、地主あるいは借主のどちらかの立場を有利にするために標準の契約書から変更されている可能性もあります。
「市販のもの」「インターネットに掲載されているもの」を全て信用するよりは、弁護士などに相談して、より有利な内容の借地契約書の作成を依頼することも重要です。
「公正証書」とは、公証人という法律の専門家が証書として作成した文書をいいます。
「公証役場」というものが全国各地に設置されており、そこに「公証人」がおられます。
皆様のお近くにある「公証役場」を確認してみてください。「公証人」に公正証書の作成を依頼することができます。なお、公正証書の作成には、公証人手数料令という法令に定められた手数料を支払う必要があります。
契約を公正証書で締結することにより、(1)公証人という法律の専門家によって契約内容が明確化されることで、紛争の防止となる、というメリットが考えられます。(2)さらに、大きなメリットとしては、未払いの地代など「金銭」を支払えという地主の請求に関しては、この公正証書に「強制執行認諾条項(~の金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した、という条項)」をいれておけば、裁判をいちから起こすことなく、裁判の判決がなくても、公正証書に基づいて強制執行(差押え)をすることができる、ということです。「建物を明け渡せ」というような「金銭以外」の請求内容は、公正証書に記載されていても強制執行力は認められず、いちから裁判を提起する必要がありますが、「金銭を支払え」という請求の点に限っては、裁判を提起することなく強制執行でき、大きなメリットとなります。
なお、事業用定期借地権設定契約については、必ず、公正証書によって締結しなければならないと法律で定められています(【Q事業用定期借地権設定契約とは何ですか。】参照)。
平成3年に制定された借地借家法(平成4年8月1日施行)は、明治から大正時代に制定されました「建物ノ保護ニ関スル法律」・「借地法」・「借家法」の3つの法律(漢字以外の部分がカタカナで表記されていました)をひらがな表記で1つの法律にしたものです。
借地借家法のもとにおいても、普通の借地権の存続期間は30年以上であり、期間満了時に借地人が契約の更新を請求したり、または、期間満了後に土地の使用を継続したりしていますと、貸地人に更新拒絶の正当事由がない限り、借地契約はさらに更新されることになります(【Q借地契約の期間について、どのようなルールがありますか。】 【Q借地契約の更新手続を行うのを忘れていた場合、借地契約の期間はどうなりますか。なお、借地人は、借地上に建物を建築して所有し、契約期間満了後も土地の使用を継続しています。また借地契約には契約期間満了時に自動更新する旨の特約はありませんし、借地人から契約更新の申入れはありませんでした。】 【Q借地契約の期間が満了するので、更新せず、土地を返してほしいのですが、借地人は土地を使い続けたいと言っています。土地を返してもらうことはできますか。】参照)。
以上のことから、「いったん土地を貸したら返ってこない」などと言われており、土地所有者に対し、借地契約の更新により半永久的に土地を貸さなければならないという不安を発生させ、結果として、貸地をすることを控えるという実態がありました。
こうした背景から、(1)一定の借地期間が経過すれば契約は更新されずに借地権も消滅するという形態の定期借地権(一般定期借地権)と、(2)事業用借地権と、さらに(3)一定の借地期間後に借地人が借地上建物を地主(貸地人)に譲渡することにより借地権が消滅するという形態の建物譲渡特約付借地権を、新しく立法化しました。この(1)一般定期借地権、(2)事業用借地権、(3)建物譲渡特約付借地権の3つを総称して定期借地権といいます(【Q事業用定期借地権設定契約とは何ですか。】 【Q建物譲渡特約付借地権とは何ですか。】参照)。
ここでは、一般定期借地権を説明します。
一般定期借地権とは、(1)借地権の存続期間は50年以上で、(2)借地の目的には、建物所有を目的とする限り制限がありませんが、(3)契約の更新がないこと(更新の請求や土地の使用の継続によるものを含みます。)、(4)借地上の建物を再築しても借地期間は延長されないこと、(5)借地人が建物の買取りの請求をしないこと、(6)以上の(3)~(5)の3つの特約を公正証書等の書面で行うことによって定められる「定期借地権」です。
以前の旧借地法のもとでは、(3)~(5)の3つの特約は、いずれも借地人に不利な特約として借地法上は無効とされていましたが、平成3年の借地借家法で認められた一般定期借地権については、この特約が有効とされることになりました。
この「一般定期借地権」においては、借地契約は更新されることなく終了し、土地は原則として更地で返還されることになります。
この「一般定期借地権」は、もっとも活用されており、戸建住宅や居住用マンションに活用されています。
上記の3つの特約は、「公正証書による等書面によってしなければならない」と定められており、書面であれば必ずしも公正証書によらなくてもよいとされていますが、証拠能力の高い公正証書によることが望ましいところです。
なお、法律改正により、上記の3つの特約を電磁的記録によって行うことも認められるようになりました(書面によってなされたものとみなされます)。
平成3年成立の借地借家法で「定期借地権」が定められた経緯は、「一般定期借地権」のところで述べたとおりです(【Q一般定期借地権とは何ですか。】参照)。
ここでは、「定期借地権」のなかの「事業用定期借地権」について述べます。
「事業用定期借地権」とは、(1)借地権の存続期間を10年以上50年未満として、(2)借地の目的に制限があって、もっぱら(専ら)事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有に限定される契約であって、(3)契約の更新がなく、(4)借地上の建物を再築しても借地期間は延長されず、(5)借地人に建物買取請求権がない、ことが認められる「定期借地権」です(なお、厳密には、事業用定期借地権等には借地借家法23条1項による場合と同条2項による場合があります。)。
事業用定期借地権設定契約は、必ず「公正証書」でしなければなりません。他の要件をみたしていても、公正証書の要件を満たさないものは「事業用定期借地権」ではありません。注意が必要です(【Q借地契約を公正証書で締結するとどのようなメリットがありますか。】参照)。
事業用定期借地権設定契約は、もっぱら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的とすることに限定されるため、人の居住目的の住宅マンション・社宅等には利用できません。また、「もっぱら」というのは、建物を「全て」事業用に用いるという意味ですので、一個の建物の一部を事業用に使い、かつ別の一部を居住用に用いる場合は認められません。
平成3年成立の借地借家法で「定期借地権」が定められた経緯は、「一般定期借地権」のところで述べたとおりです(【Q一般定期借地権とは何ですか。】参照)。
ここでは、「定期借地権」の中の「建物譲渡特約付借地権」について述べます。
「建物譲渡特約付借地権」とは、借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地人から借地上の建物を買い取ることを約束した借地権です。借地権を設定する際に、借地権を消滅させるため、30年以上経過した日に相当の対価で借地上の建物を地主に譲渡する特約を結ぶことで、この借地権が設定されます。
建物譲渡特約付借地権であることは、一般定期借地権や事業用定期借地権の場合と異なり、不動産登記の登記事項とはされていません。そのために、建物譲渡特約を交わした地主は、当初の借地人である建物所有者から所有権を承継する第三者に対抗するために、建物所有権移転請求権を保全する仮登記を経由して本登記の登記順位を保全することが必要です。
建物譲渡特約付借地権を設定する場合は、特に、書面による必要はなく、口頭でも可能とされます。しかしながら、将来の紛争を回避するためにも、書面による契約書をつくることが望ましいことは言うまでもありません。
「自己借地権」とは、「地主(貸地人)自らが借地人となる場合の借地権」のことです。たとえば、あなたが、ご自分の所有土地の上に、友人と共同で建物を築造し、これを共有するとします。この場合、この土地について、あなたが貸地人で、借地人があなたと友人という借地契約を締結しても、これまでは、あなたの借地権は成立しないものと考えられてきました。
その理由は、民法の定める「混同」の原則にありました。「混同」とは、併存させておく必要のない2個の法律上の地位(この場合は、貸地人の地位と借地人の地位)が同一人に帰属することで消滅する、という考えです。
そのため、所有者は、その所有物の上に自己のための地上権や賃借権など使用収益を目的とする権利を設定することができず、第三者のために設定した権利も取得すればその権利は消滅する、とされていたのです。
そこで、借地借家法では、混同の原則に反する一般的な「自己借地権」ではなく、制限的な「自己借地権」を新しく設けて、不便に対応することにしたのです。
地主(土地所有者)は、他の者と借地権を準共有(所有権以外の権利を2人以上の者が共有すること)する場合に限り、自ら借地人となることができるとしたのです。
「自己借地権」は、居住用マンションその他区分所有建物の敷地利用権などに用いることが可能です。
借地権を利用権とする区分所有建物(マンション)を分譲する際に、最初に買主が現れた段階で、その買主と自己とを借地権者として借地権を設定することができます。
以上のように、土地所有者は、他人とともに設定する場合に限り、自己の土地に借地権を設定することができます。これを「自己借地権」といいます。
あなたがひとつの土地を所有されているとして、その土地を、AとBの2人が借りたい、すなわち、借地させてほしい、と求めてきたとします。
貸主はあなた1人で、借地人がAとBの2人の場合、どのようなことが問題となるでしょうか。
貸主として、一番気になるところは、地代の支払であることは言うまでもありません。借地契約をした後に、残念なことに、地代の不払いという事態が発生した場合、貸主であるあなたは、Aに全額請求できるでしょうか。Bにも全額請求できるでしょうか。あるいは、Aには地代の半額、Bにも地代の半額しか請求できないでしょうか。
この点については、判例は、地代(賃料債務)は不可分債務になるという考え方をとっており(なお、学説では、改正民法のもとでは、連帯債務になるという考え方が多くなっているとされています。)、あなたは、A1人に対して全額請求することもできますし、B1人に対して全額請求することもできます。ABに対して同時に、もしくは順次に、全部または一部の請求をすることができます(なお、Aからも全部、Bからも全部、という2倍を取得することは当然できません)。
地代を支払え、ということは、それぞれに対し全額請求できますが、地代を支払わないAとBに対し、地代の不払いを理由とする解除通知を出す場合、さらには、解除の前段階として必要とされる「相当の期間をもって催告」する通知を出す場合、あなたは、AかBのどちらかに行えばよいのでしょうか。
結論としては、これらの場合、あなたは、AとBの両方を相手に通知を出さなければならないとされています。借地人が1人であれば、その人に対してのみ通知を出せばよかったわけですが、借地人が複数になると、手続に余計な負担が発生することになります。注意が必要です。