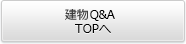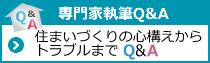建物の構造や工法、耐震、シックハウス、建物保証、太陽光発電、リフォーム、建物診断、メンテナンス、地盤沈下、インスペクション等、建物に関する知識を解説しています。
建築(新築)の基礎知識
結論からいうと、一概に最も良い構造と工法を決めることはできません。なぜなら、住宅を建築する立地、建築費用、求める建物性能によって答えが変わってくるからです。
建物と一言でいっても、住宅、店舗、公共用建物、オフィスビル等さまざまな用途や種類があります。ここでは住宅のカテゴリーに絞って分かりやすく説明します。住宅は一戸建てと集合住宅(マンション、アパート、長屋)に区分できます。
一戸建てというと、木造2階建て、または平屋建てというイメージを持たれると思います。国民的テレビアニメ番組の「サザエさん」や「ちびまる子ちゃん」の自宅は平屋建て、「ドラえもん」では木造2階建てです。ただ、最近、都心部では木造3階建ての住宅もよく見かけるようになっています。
次に集合住宅というと、2階建ての低層マンションから、最近話題の30階以上の超高層マンションなどがあります。アパートというと木造2階建てを思い浮かべる方がほとんどではないでしょうか。
建物の構造を大別すると、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などがあります。簡単にいうと、「何を主な材料として建築するのか」ということです。工法には、木造軸組(じくぐみ)工法、2×4(ツーバイフォー)工法、木質系プレハブ工法、鉄骨系プレハブ工法などがあります。鉄筋コンクリート造では、ラーメン工法、壁式工法、プレキャストコンクリート工法などがあります。それぞれの構造にメリットやデメリットがあり、建築工事にかかる期間や金額も異なります。ちなみに総務省統計で日本国内における住宅を構造別にみると、木造は3,011万戸で住宅全体の57.8%、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの非木造は2,199万戸で42.2%になっています。
※構造別統計データについては以下を参考
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/pdf/nihon02-1.pdf
構造や工法によって、耐用年数、耐火性、耐震性、遮音性、増改築のしやすさなどに違いがでますが、最終的には個別の住宅によって最適な条件は異なります。木造だから弱い、鉄筋コンクリート造だから強いとは一概には言えないのです。間取りによっても、施工したときの工夫の有無によっても、特性は変わります。そのため、構造、工法の傾向を把握したうえで個別の住宅について判断することが大事です。
結論としては、「ベタ基礎であれば安心」とは一概には言えません。なぜなら、地盤の強さによって最適な基礎は変わってきますし、ベタ基礎でも形状、鉄筋の太さや間隔も異なることがあるからです。地盤調査の結果を踏まえてコストと効果を見極めたうえで、基礎を選択することが重要です。
建物の「基礎」は読んで字のごとく、建物の上物を支え、重さを地面に伝える役割を持っています。そのため、基礎に不具合があると、耐震性にも影響しますし、建物そのものの寿命にも影響します。基礎は簡単にはやり直しができない部分であり、一度コンクリートを打設すると基礎の中の鉄筋の状態も確認できません。そのために特に施工時には注意を払う必要があります。
建物の基礎について簡潔に説明すると、木造一戸建ての場合、主に布基礎とベタ基礎があります。布基礎というのは、逆T字型の断面形状の鉄筋コンクリートが連続した基礎のことです。それに対してベタ基礎とは、床下部分(底板)一面も鉄筋コンクリートになっている基礎のことです。以前は、布基礎の建物が一般的だったのですが、1990年代からは布基礎よりも軟弱地盤に強く、シロアリ対策、防湿対策にもなるベタ基礎を採用するケースが主流になってきています。布基礎、ベタ基礎以外にも深基礎などの基礎工法もあります。基礎の立ち上がりの厚みについては築年数が古いと120㎜、現在では150㎜程度が多くなってきています。基礎の立ち上がりの高さについては、40㎝以上が一般的です。
住宅を建築する際には、設計と建築確認申請を事前に行う必要があります。ここでは、「着工してから完成するまで」のスケジュールという意味で解説します。
建築工事の流れとしては、基礎工事で建物の基礎を造り、次に上棟工事で柱や梁などの建物の骨組みを組み上げていきます。棟上げ(むねあげ)ともいいます。続いて、屋根、外壁、防水工事で建物の外側部分の施工を行い、給排水設備、電気設備などの工事を行います。最後に内装工事で室内の仕上げを行います。イメージとしては、土台、骨組み、屋根外壁、室内、という流れとなります。
着工→基礎工事→上棟工事→屋根、外壁、防水工事→給排水設備、電気設備工事→内装工事
※おおまかな流れであり、実際はより細かい工程があります。
工事期間としては、建物の規模や工法によって建築期間は異なりますので一概には言えませんが、延床面積30坪程度の2階建てを木造軸組工法で建築する場合、着工してから完成まで3〜4か月間程度が一般的です。ハウスメーカーの中にはプレハブ工法を採用して工期短縮を図り、3か月程度で竣工(しゅんこう)できる会社もあります。
鉄筋コンクリート造のマンションなどでは、建物規模も大きくなりますので、工事期間は一戸建てよりも長くなります。あくまでも一般的な目安としてですが、1フロアにつき1か月、12階建てマンションであれば12か月程度はかかると言われています。
上記の工事期間については、あくまでも目安であり、実際には天候不良で工事ができないこともありますし、施工上のトラブルや近隣住民の方からのクレームなど予定外の問題が発生したことによって工事期間が長くなることもあるのでご注意ください。
設計図面は建物の仕様や構造、特に目視では分からない部分について記録された貴重な資料です。紛失しないように大切に保管しておく必要があります。建物図面がない場合には、基本的には目視か、一部を解体しなければ壁の中がどうなっているのかは分かりません。
建築前につくられた図面のことを設計図面、建物が完成(竣工)した後に当初の設計図面から変更した箇所を反映させた図面を竣工図面といいます。マンションの場合には、建物が完成してから竣工図面を作成することが多いのですが、一戸建ての場合には、建物が完成してから竣工図面を作成することは希です。そのため、実際の建物と設計図面が違っていることがあるので注意が必要です。
設計図面は実際の建物を見ただけでは分からない貴重な情報の宝庫です。一戸建てでいえば、基礎の厚みや深さはどれくらいあるのか、コンクリート強度はどれくらいなのか、どの部分に配管が通っているのか、地盤調査の結果どのような対策をしているのか、設備の仕様やグレードはどうなのか、耐震性はどのレベルなのか等を把握することができます。マンションの場合にも、支持層となる地盤までの深さや杭の長さや種類、コンクリート強度や、建物の工法、間取り変更のしやすさや、上下階の音の響きやすさなどを調べることができます。「建物について詳しく知ったうえで住宅を買いたい」というときには、設計図面や竣工図面はとても役に立ちますので有効に利用することをおすすめします。
平成30年4月1日より宅建業法が改正され、取引する際に交わす売買契約書、重要事項説明書に建物に関する情報を記載することになりました。具体的には、売買契約書には建物状況調査の実施の有無を記載し、重要事項説明書には建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況などを説明することになりました。
さらに、令和6年4月1日には、建物状況調査に係る改正宅地建物取引業法施行規則等が施行されました。
今回の改正では、標準媒介契約約款が改正され、建物状況調査の記載について、建物状況調査を実施する者のあっせんを「無」とする場合における理由の記載欄を設けるとともに、トラブル回避の観点から、建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと等)について明記されました。
今までは建物に関する資料の有無についての説明はされないことが多かったので、大きな転換と言えます。法令順守している建物、維持管理を適切にしている建物が評価されやすくなってきているといえます。
建築確認とは、「建築する建物が建築基準法等の関係法規に適合しているかを建築前に審査すること」をいいます。もう少し詳しくいうと、建築確認申請を行い、建築主事や確認審査機関による建築計画の審査を行い、『建築確認済』を取得する行政行為のことをさします。
建物の用途地域や建ぺい率、容積率を定めている都市計画法や、建物の構造や耐震性などを定めた建築基準法等の関係法規が守られているかどうかを確認しています。
建築確認がなければ、無秩序に住宅が建築されてしまうからです。例えば、建築確認がなければ、2階建ての戸建てが立ち並ぶ地域に50階建ての超高層マンションが建築されてしまったり、小学校の隣に危険な薬品の取り扱いのある工場施設が建築されてしまったりする可能性があります。そうなると、いろいろな人に迷惑がかかります。建物の構造についても、基準が決まっていなければ、震度3でも倒壊してしまう危険があったり、燃えやすい材料が使われていたりすると火事が起きたときに住む人の命を危険にさらしてしまうことになります。場合によっては、建物の倒壊や火災によって周りの建物を巻き込んだ事故となることも考えられます。そのような事態を防止するため、建築確認によって建築する住宅について審査をしているのです。
最近では少なくなりましたが、建築確認を取得しないで住宅を建築しているケースもあります。例えば、住宅を建築する際には最低限2mの接道が必要ですが、対象敷地について接道がどこにもない場合、建築確認を取得せずに住宅を建築してしまっているのです。このような建物は違反建築物といって、金融機関からの融資を受けることができません。
建築主事である行政と民間の審査機関が建築確認を行っています。以前は行政のみが建築確認を担っていましたが、平成12年からは国から認定を受けた民間の審査機関でも建築確認を行うことができるようになりました。ただし、行政であろうと民間の審査機関であろうと、審査内容は基本的には異なることはありません。もし、審査内容が異なってしまったら、平等ではなくなってしまうためです。
『検査済』がないからといって、建物構造に問題がある物件とは一概には言えませんが、融資が受けにくい、基準を守られた建物かどうかわからないというリスクがあります。
『検査済』とは、建築確認を取得した行政や民間の審査機関によって、建築工事完了後の検査(完了検査)を受けていることをいいます。完了検査では、建築確認申請時の図面どおりに造られているか、チェックを行います。検査の結果、検査済証が発行されるので第三者に対しても「建築工事完了後の検査を受けていること」の証拠になります。建築基準法では、完了検査を受ける必要があると定められています。
「『検査済』がない」とは、つまり、「建築時に完了検査を受けていない」ということになります。なぜ完了検査を受けないのかというと、間取りを変更したり、容積率の上限を超えて延床面積を増やしたりして建築確認取得時の図面からなんらかの変更をしており、そのまま完了検査を受けても合格することができない場合などが考えられます。このような物件は、建築確認取得時の図面と実物の建物とではなんらかの差異があるケースが多いです。いくら建築確認を行っていても、完了検査を受けていなければ厳密には基準を守られているかどうかは分かりません。
建築確認が必要な建物は、工事を完了した日から4日以内に、建築主事の検査を申請しなければならないと建築基準法第7条によって決まっています。したがって、『検査済』がない物件は法律違反となります。
国土交通省のデータによると、平成12年度には新築物件のうち4割程度しか『検査済』を取得していなかったのですが、平成23年度の時点では約9割が『検査済』を取得しています。現在、新築する物件で『検査済』を取得しないというのは相当レアケースといえるでしょう。以前は『検査済』の取得に対する意識が施工業者も低く、住宅ローンを利用する際にも『検査済』は不要とする金融機関が多かったのですが、現在は検査済証がない融資は受けられないのが現状です。新築物件において検査済証がない物件は法律違反なので、基本的には購入しないことをおすすめします。
国としても過去において検査済証の交付を受けてない建築物が多数存在していることを把握しています。既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、指定確認検査機関等を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法等を示したガイドラインを平成26年7月に策定・公表しました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html
検査済証の交付を受けていない既存建築物の増改築等をする際には建築当時の建築基準法に適合しているかどうかを確かめることが求められます。当然費用がかかります。そして、法令に適合していなければ、適合するための対策が必要となり、結果また費用がかかります。このようなことを踏まえると、検査済証の交付を受けていない建物については十分な注意が必要になるといえるでしょう。
建築の専門的な知識のない一般の方が良し悪しを判断するのは難しい点もあるかもしれませんが、少なくとも建築途中では次のことについて確認しておくとよいと思います。
行政や民間の建築確認審査機関が建物完成時に完了検査を行います。この検査は目視の検査となりますので、工事中のすべてを確認することができません。そこで、チェックすべきなのは施工会社自体が工事の節目でチェックする制度が整っているかどうか、いわゆる社内検査がされているかが重要です。建物の基礎にコンクリートを流し込む前に鉄筋が適切な間隔で配置されているか、建物が上棟した際には設計図面で指定されている種類の金物が図面どおりの位置に取り付けられているか、防水シートの施工がきちんとされているかなど、建築工事の段階ごとにチェック制度がある施工会社は信頼できます。もしそのようなチェック制度がない施工会社の場合、施工ミスに気付かないままで工事が進んでしまうリスクがあります。
「施工会社にチェック制度があっても、本当に適切に工事がされているか不安」という場合には、施工会社とは利害関係のない第三者の一級建築士などの有資格者に施工途中をチェックしてもらう方法もあります。費用はかかりますが、施工に不安がある場合には役立つでしょう。
専門的な知識はなくても、建築現場を見ることでトラブルが起きやすいかどうかを見極めることはできます。
・整理整頓、清掃がきちんとされているか
現場が汚い、整理整頓がされていない場合には、工事上のトラブルが発生しやすいものです。整理整頓がされていない原因は、工事の段取りの打ち合わせ不足、無理な工程設定、職人の意識の欠如などが考えられます。このような現場では、工事上のミスも起きやすくなります。
・余裕をもって工事を進めているか
時間的な余裕が極端に少ない状況での工事はミスが発生しやすくなります。もともとの工事期間の設定が短い、またはなんらかの理由で工事完成までの時間が短いと、無理をして突貫工事を行うことになります。ミスが多くなりがちなのは当然の帰結です。
・監督から施工図面を元に適切に指示がされているか
図面もなく、現場で打ち合わせをしたうえで建築工事を進めている場合には注意が必要です。「現場合わせ」といって、施工図面などはなく、現場の状況を見ながら工事を進めるケースがあるのです。図面もない口頭だけの指示になるため、指示する側と工事する側とで認識のズレが発生してしまい、間違った工事をしてしまうリスクがあります。
最近ではインターネット上で見かけた、不安を煽るような情報を鵜呑みにして、施工会社を悪人と勘違いして、良好な関係が崩れてしまうこともあります。建築工事のチェックについては、基本的には専門知識のある一級建築士などに依頼したうえで冷静に行うことをおすすめします。
新築一戸建ての引渡しを受けるときを例としてお答えします。通常、一戸建ての引渡しを受ける際には、竣工検査、または内覧会を行います。これは、引渡しを受ける前に、購入者(または施主)が建物をチェックする機会のことをいいます。
チェックポイントは「日常生活上で支障になる不具合がないか」です。扉や窓サッシなどの可動するものがきちんと動くかどうか、設計図面どおりに取り付けられているか、大きな傷や壊れているものがないかをチェックします。
家というものは、工業製品ではなく、1棟ずつ職人などの手作業によって造られるものです。裏を返せば、人為的なミスが多かれ少なかれ発生します。依頼した扉とは異なる種類や色のものが取り付けられていたり、設計図面にある照明が取り付けられていなかったりします。造る側は正しいと思って工事しているわけですから、竣工検査で購入者が気付かなければ誰も間違いに気付かない可能性もあります。だからこそ、自らのチェックが重要になるのです。
建物についてなんらかの不具合が見つかったとしても、直すことができないようなものはほとんどありません。傷があれば補修すればよいし、壊れているのであれば交換すればよいのです。サッシがスムーズに動かないのであれば、調整すれば不具合を解消できます。ただし、建物自体が不同沈下によって傾いたり、本来あるはずの鉄筋が入っていなかったり、という根本的な不具合が見つかったときには、改善するのは大変かもしれません。
竣工検査のタイミングは、購入者にとって引渡し前の最終チェックとなるので、過度に緊張してしまうこともあるかもしれません。しかしながら、新築一戸建てであれば、通常は分譲会社、または施工会社による10年間の契約不適合責任や部位ごとに一定期間のアフターフォローがあります。もし引渡し後に不具合が出たときには、アフターフォローとして定められている箇所と期間を確認したうえで直してもらえばよいのです。予め契約不適合責任で10年間保証される不具合にどのようなものがあるのか、アフターフォローの対象となる不具合について確認しておくとよいでしょう。とはいえ、引渡しを受けた後に引っ越して家具が設置されてから不具合が見つかると、直すのも大変になってしまうことがありますので、不具合は竣工検査で見つけておくことが大事です。
最近では、建物の専門的な知識のある建築士等の資格を持ったプロに、購入者側の立場で竣工検査を手伝ってもらうこともできるようになっています。一般の方は、不具合だと思って指摘した箇所について施工会社側で「これはこの様な理由で問題ありません」といわれたときに、本当にそうなのかどうかを判断することが難しいケースもあります。このようなときに建築知識を持ったプロが自分の立場にいれば、客観的な意見を聞くことができるので安心です。必ずしも必要とはいえませんが、自分だけで竣工検査を行うことに不安があるなら利用を検討してみるのもよいかもしれません。
はい、確かに新築と中古では保証内容が異なりますが、中古には保証が全くないわけではありません。どんな保証があるのか、新築と中古に分けてご説明します。
瑕疵とは、不具合、欠陥をさす専門用語です。「欠陥住宅」というのは「瑕疵住宅」と言い換えられます。専門的には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という法律に基づき、住宅の基本性能にかかわる重要な部分を保証することを、瑕疵担保保証といいます。具体的には、屋根や基礎、土台などの構造耐力上主要な部分や外壁や窓などの開口部からの雨水の侵入を防止する部分についての保証です。
新築の場合は、売主である事業者が契約不適合責任を最低10年間負うことが法律により義務付けられています。たいていの場合は、引渡し時に保証書が発行されて詳しい保証内容が記載されています。どのような場合に保証が受けられるのか具体的な条件を確認しておくとよいでしょう。ポイントは、「保証対象の不具合が保証期間内に発生した場合に、売主(事業者)の責任と負担で修繕する」ということです。それでは、売主である事業者が倒産してしまったら保証がなくなってしまうのでしょうか。
もし、保証期間内に売主である事業者が財務状況の悪化や、倒産などによって瑕疵担保責任を果たすことができなくなってしまったら住宅購入者は困ってしまいます。過去には、瑕疵担保保証期間である10年以内に建物の耐震構造に問題があると発覚したことがありました。しかし、この分譲会社は問題の発覚を原因として経営が悪化し倒産してしまったのです。結果的に、購入者は分譲会社による瑕疵担保責任を果たしてもらうことができませんでした。
このような事件を受けて、平成21年10月以降に引渡される住宅を扱う事業者には、瑕疵担保責任を果たすための資力の確保が義務付けられました。その結果、万が一瑕疵担保保証の期間内に事業者が倒産してしまっても、事業者が供託した保証金から保証を受けたり、住宅瑕疵担保責任保険によって保険法人が保証を引き継いだりする制度ができました。
不動産の売買契約をするときに、契約条項として契約不適合責任の有無について記載することが定められています。契約不適合責任を売主が負担するときには、買う側が契約の目的を達することができない不具合(構造上主要な部分の不具合、雨漏り、シロアリ等の被害)が見つかったときに、売主の責任と負担で修繕することになります。契約不適合責任の期間としては、一般的には3か月程度とすることが多いようです。
中古の取引において、売主が一般個人であり、買主も一般個人、または宅建業者などである場合には、契約不適合責任を売主が負担しない契約とするケースもあります。専門用語で契約不適合責任免責といいます。契約不適合責任免責の場合には、万が一不具合など契約に適合しない不具合等が発見されたとしても、売主は責任を負わないことになります。
中古の取引であっても、宅建業者が売主となる場合には、最低2年間の契約不適合責任を負うことが法律により義務付けられています。宅建業者はプロですから、契約不適合責任免責ということはできないわけです。最近では、中古住宅を宅建業者が買い取り、大規模なリノベーション工事を行ってから売却する、という物件が多く登場してきています。このような場合には、宅建業者が売主となりますので、最低2年間の契約不適合責任があることになります。
中古住宅にも瑕疵保険ができました。資格を持ったプロによる建物検査を受け、決められた基準を満たした住宅については一定期間の瑕疵保険を保証するものです。現状では、中古住宅の取引では、個人が売主であるために契約不適合責任の期間も3か月程度、場合によっては契約不適合責任免責ということも珍しくありませんでした。結果的に、購入者側の心理として「新築は10年間の契約不適合責任期間(瑕疵担保保証)があるから安心。中古を買うのは不安」となっていました。しかし、中古住宅にも瑕疵保険制度が登場したことで、安心して取引ができる状況が整備されてきています。
上記でご説明した瑕疵保証の他にも、地盤を保証する「地盤保証」やシロアリの害について保証する「シロアリ保証」などもあります。住宅の設備にもそれぞれメーカー保証が付けられています。詳細については改めてご説明します。
『アフターサービス基準書』というのは、住宅を購入した場合についてくる売主側のサービス基準を書面にしたものになります。購入した住宅が新築の場合には、アフターサービスがついてくることが多いです。最近では、中古住宅であっても、売主が宅建業者である場合には、アフターサービスをつけていることがあります。アフターサービスの基準は会社ごとに異なるため、詳細について把握しておくことが大切です。
アフターサービスについては、例えば、住宅の設備機器、仕上げ等について不具合箇所、不具合の現象、保証期間などが書面に明確に記載されています。
アフターサービス基準として書面に記載されていても、実際に不具合が発生したときにはアフターサービスに該当するか否かを判断することが難しいケースがあります。というのも、アフターサービス基準には適用除外の条件があるからです。例えば、地震などの天災地変や自然現象を原因とするもの、使用者の不適切な使い方、維持管理を怠ったために発生した不具合については適用除外となります。アフターサービスに該当するかどうかが分からないときには、事業者側の基準で適用するかどうかを判断するケースが一般的ですので、気になる不具合があれば問合わせてみてください。
住宅の引渡し後、売主側で定期的に建物の点検を行うサービスのことを定期点検と呼びます。点検の期間としては、引渡しの3か月後、6か月後、12か月後、24か月後などに行う事業者が多いようです。あくまでも売主側のサービスであり定期点検サービスがない場合もありますので、住宅を購入した際に定期点検サービスの有無を確認しておくとよいでしょう。
定期点検といっても、「事業主側から手配された方がチェックするケース」と「居住者自身が気になる点をチェックするケース」の2とおりがあります。居住者がチェックする定期点検の場合には、不具合箇所を自己申告で知らせることになりますので慎重にチェックする必要があります。もし不具合が発生していても気が付かないまま保証期間が過ぎてしまえば、無償で修繕してもらうことは難しくなってしまうこともありますので注意してください。
入居してから不具合があまりにも多く見つかったときに、建物に対して不信感を持ってしまうことがあります。このようなケースでは、事業者側、施工会社側に説明を求めても心理的に納得するのが難しいこともよくあります。このようなときには、建築士等の資格を持ったプロにインスペクション(建物検査)を実施してもらい、客観的に見てもらうことが有効です。利害関係がないので、実際の建物の状況を正確に把握することができるからです。
定期点検を行う時期、回数、どのような内容の定期点検を行うのかを確認してください。定期点検というのは、売主の不動産会社によるアフターサービスとなりますので、不動産会社によって定期点検の有無、時期、回数、やり方や内容が異なります。
定期点検は、引渡しの3か月後、6か月後、12か月後、24か月後など2年間、回数にすると5回程度行うケースが多いです。新築の場合、雨漏りや主要構造部分の瑕疵については最低10年間の契約不適合責任を売主が負いますが、その他の部分については24か月が保証期間の目安です。
保証期間内に保証した建築会社以外(他のリフォーム業者)で修繕した場合、修繕以降はその箇所は、保証対象外になる場合があります。必ず修繕前に保証がどうなるのか、確認しておきましょう。
定期点検といっても、やり方も内容もさまざまです。アフターサービス部門の担当者がチェックシートを元に一とおり調べてくれるところもあれば、不具合箇所の有無や状況を自己申告制で所定のシートに記入して提出するだけの場合もあります。どちらかといえば、不動産会社の担当者が来てチェックしてくれた方が、不具合かどうか判断がつかない箇所も相談できるので親切かもしれません。もし自己申告制の定期点検を行う場合で、建物の不具合の見極めについて不安があるようであれば、建築士などの専門家に依頼してインスペクションを行ってもらうのもよい方法です。不具合について客観的に把握することができるので、保証期間内の不具合については売主側に無償で補修してもらいやすくなるでしょう。
一言で建物といっても、いろいろな種類があります。主に住宅と言われる建物について説明します。住宅以外については、最後にお伝えします。
主に木造、軽量鉄骨造などの平屋建て、2階建て、3階建ての建物です。高さは3階建て程度の低層住宅であることが多いです。用途としては、自宅用、賃貸用、商業店舗利用などいろいろです。底地所有者と建物所有者が別々で、地代を底地権者(土地所有者)に毎月支払い土地を借りて使用している借地権付戸建てというケースもあります。
主に鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物です。高さは3階建て程度の低層マンションから30階を超えるような高層マンションまであります。分譲マンションの場合、土地に敷地権登記を行い、土地と建物とを一体化することにより、土地と建物を別々に売却することができないようにしています。賃貸用のワンルームマンション、ファミリータイプの多い分譲マンション、商業施設が低層階に入っている複合施設型マンションなど、さまざまなタイプがあります。土地、建物の所有者が単独である場合には収益物件として流通することもあります。
基本的には賃貸に出すことを目的とした建物です。2階建て、3階建てで木造、軽量鉄骨造の建物が主であり、収益を最大限得られるような部屋数、部屋の広さを前提として建築されています。入居者、建物の管理を大家さんが賃貸管理会社に委託することが多いです。賃貸保証会社に建物を一括で貸し出し、賃貸保証会社が転貸して一般に貸し出す仕組みもあります。この場合、家賃保証という形で、入居状況にかかわらず一定の賃料を土地建物の所有者に支払います。
建物の表示に関する登記事項証明書には、「建物の種類」が記載されています。この不動産登記法に基づく建物の種類として、建物の利用用途ごとに37の種類に分けられており、さらにその37の区分に該当しない建物については用途により的確かつ合理的に定めています。どのような種類があるのか、以下に列記します。
居宅・共同住宅・寄宿舎・店舗・料理店・事務所・旅館・工場・倉庫・物置・車庫・校舎・講堂・研究所・病院・診療所・集会所・公会堂・停車場・劇場・映画館・遊技場・競技場・野球場・競馬場・公衆浴場・火葬場・守衛室・茶室・温室・蚕室・便所・鶏舎・酪農舎・給油所・発電所・変電所
百貨店・ホテル・保養所・作業所・納屋・駐車場・体育館・保育園・保育所・教習所・会館
上記のうち、住宅と言われるのは、居宅、共同住宅、寄宿舎の3つです。
建物の種類や構造、個別の建物ごとのメンテナンスの実施の有無にもよるので、一概に何年もつと言うのは難しいです。「建物が何年もつのか」について、ひとつの目安として耐用年数という考え方を用いることが多いです。
木造一戸建ての売却査定の実務においては、耐用年数を22~25年として、築年数が経過するほどに価値が0円に近づくものとして算定されます。これは実際にその建物が何年もつかという明確な基準がないため、税法に基づく財務省令上の耐用年数を参考に設定しています。
同様に鉄筋コンクリート造の住宅の税法に基づく耐用年数は47年となっています。ただし実務上の売却査定の際には、一戸建てと異なりマンションは土地と建物を別々に評価するケースは少なく、取引事例に基づく総額を参考に査定価格を決めることが一般的です。
上記の耐用年数はひとつの目安です。それでは、実際に住宅の寿命はどれくらいなのでしょうか。諸説ありますが、便宜的に建物が解体されるまでの平均年数を用いて、木造30年、鉄筋コンクリート造38年という年数が参考にされるケースが多いようです。ただし、これも実態とはズレがあります。早稲田大学の小松幸夫教授の研究成果によると平成23年時点の建物の寿命として、木造専用住宅が65年となっています。
参考資料:http://www.mlit.go.jp/common/001033889.pdf
平成30年4月1日の宅建業法の改正に建物状況調査の斡旋の有無について記載が義務付けられたように、既存住宅(中古住宅)に対して評価を見直す動きも活発化しています。たとえば、公益財団法人不動産流通推進センターの既存住宅価格査定マニュアルでは、木造住宅であっても、建物の仕様や点検補修の有無によって、耐用年数 100年、75年、50年、40年、30年と区分けしています。今後も建物の耐用年数は税法に基づく耐用年数よりも⾧くなっていくものと思われます。
現在、日本の住宅市場においては、中古住宅の流通を活性化させるべくさまざまな取組が始まっています。新築市場主義であった国内の住宅市場も、スクラップ&ビルドから脱却し、ストック資産である住宅の価値を再評価し、中古住宅の流通量、リフォーム市場を倍増していく計画です。
結局のところ、税務上の耐用年数と建物寿命は異なり、メンテナンスを定期的にしていけば建物は60年以上、100年くらいはもつのではないかと思います。
200年住宅とは、簡単に言うと「200年もつ住宅」のことで、平成19年に元福田首相が提唱した「200年住宅ビジョン」が元になっています。平成26年現在では200年住宅は住宅の長寿命化を目指した「長期優良住宅」という名称に置き換えられています。長期優良住宅とは、国が推進する政策で、「良いモノを長く使う」という基本理念の元に住宅建設、維持管理、流通、資金調達などの各段階で総合的な施策を実施しています。
今まで日本の住宅における解体までの期間は、30年程度と、他の先進国に比べて著しく短いものでした。結果として、住宅を建築しても短期間で解体することになるので、建物は社会的な資産となりにくい状況でした。中古住宅の取引に関しても、築年数が古くなると価値が低くみられることから所有者の維持管理の意識も低く、購入者側も「マイホームを買うなら新築がいい」という方が大多数を占めていました。しかし、平成18年の住生活基本法により、新築供給量重視のフロー政策から既存物件の質を重視するストック政策へ基本方針を大きく変更しました。量から質へ、新築から既存物件の流通量拡大へ変わりつつあるのです。
長期優良住宅の要件は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に定められています。具体的には、建物の耐久性、耐震性が一定基準以上であり、将来的な間取り変更にも耐えられる可変性の確保、定期的なメンテナンスがしやすいことを目指しています。詳しく説明しますと、数世代にわたって構造躯体が使用できること、大規模な地震の後でも必要な補修を行うことで構造躯体を使い続けられること、配管の清掃、点検、補修、交換などを容易に行えるようになっていること、省エネルギー性能が一定の基準を満たしていることが一定以上であること、建築及び維持保全の状況に関する記録の保存が整備されていることなどです。
長期優良住宅は、一般の住宅と比べて建設コストが割高になります。国としては、長期優良住宅を推進するため住宅ローン控除の拡大、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの軽減措置を図っています。また、通常は最長で35年だった住宅ローンの期間を、長期優良住宅については最⾧50年とするフラット50という商品もあります。また補助制度もあり、各種の要件を満たした場合には、数十万円以上の助成金を受けられる場合もあります。
住宅履歴とは、定期的なメンテナンスを行い、その記録を整備する仕組みです。将来的な売却時の資産価値を高めるため、そして計画的な維持管理を可能とするため、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図面や施工工事の情報が確実に蓄積され、いつでも活用できるようになります。
シックハウスとは、建材や家具などに使用される化学物質が住む人に悪い影響を及ぼす住宅のことをいいます。シックハウスを直訳すると「病気の家」という意味で、さまざまな健康被害を引き起こします。
目が痛い、目がチカチカする、気分が悪くなる、頭痛、呼吸が苦しいなどの健康被害が発生するため、その住宅内での生活が困難になってしまいます。シックハウスによる健康被害をシックハウス症候群と呼びます。
住宅建材に使用されるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質の影響、そして最近の住宅の気密性が高くなったために換気の割合が少なくなったこと、そして現代社会において化学物質アレルギーを持つ人が増加傾向にあることが原因と言われています。
建築基準法が改正されて、ホルムアルデヒド等の特定の化学物質が含まれている建材については、どの程度の含有量があるのかを必ず表示しなければならなくなりました。具体的には星の数で表します。最近では対象の有害物質が含まれる割合がもっとも低いフォースター(★★★★)の建材が一般的に使用されています。
化学物質は換気をしなければ室内に残ってしまう傾向があるので、換気も非常に有効です。また、新しい家具などにも化学物質が大量に含まれていることが珍しくありませんので注意が必要です。
シックハウス症候群はすべての人に症状が出るとは限らないので、住宅の問題として特定するのが困難な場合もあります。一部の人に症状が出た場合には、住宅ではなく個人の体質による問題とされてしまい、解決が非常に難しくなることもあるので注意が必要です。
SE工法とは、Engineering for Safety(工学的で安全な工法)という英語の頭文字をとって名付けられた、木造一戸建ての工法のことです。
一言でいうと金物工法であることです。今までは木造一戸建ての弱点であった柱や梁の接合部を特殊な金物を使用することで、耐震性を高めています。その他にも通常木造2階建てでは義務付けられていない構造計算を行うこと、集成材を使用することなどがあります。基本的には、SE工法を採用するためには特定の団体に加盟している工務店が施工を行う必要があります。
現在、木造一戸建ての世界ではSE工法を始めとして、さまざまな工法が登場しています。特徴を詳しくチェックしてみると、工法の名称は異なっていますが、SE工法のような金物工法で施工し、工場でプレカットされた集成材を使用しているものも多く、おおまかには似たり寄ったりという部分はあります。
工法については建築会社によって個別に名称が付けられているので、良し悪しを判断するのが難しいように感じるかもしれません。というのも、建築会社も自社の工法をPRしたいので、自社の工法が一番良いと思わせるような説明をしてくるからです。そのようなときには、住宅性能評価での耐震等級でどの等級に該当するのか比較することをおすすめします。というのも、工法によって耐震性の良し悪しは一概には言えず、実際には個別の建物によって耐震性は異なるからです。したがって、工法の良し悪しを考えることも大事ですが、最終的に個別の建物の耐震性がどうかという観点で工法を選ぶことをおすすめします。
耐火建築物とは建築基準法上の概念であり、一言でいうと「燃えにくい建物にする基準」のことです。地域ごとに燃えにくさの基準が決められています。目的は火災が発生したときに主要構造部の損傷を防ぐことや周りの住宅への延焼を防ぐことです。耐火建築物の一つ下の概念として、準耐火建築物があります。
都市計画法第9条20項で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として、防火地域、準防火地域が定められています。防火地域で建築する建物については建築基準法および同法施行令に基づき、一定以上の燃えにくい材料を使用しなければならないという制限があります。防火地域とは、具体的には都市の中心市街地や駅前、主要幹線道路沿いなどで、大規模な建物が密集しているエリアが指定されています。高層ビルが密集しているため、火災が発生し延焼すると甚大な被害をこうむってしまいます。これを防ぐために、防火地域を指定し、地域内で建築する建物は原則として耐火建築物にしなければなりません。
準防火地域は防火地域よりも規制がゆるい地域です。準耐火建築物とは、準防火地域内でも建築できるレベルの燃えにくい建物のことをさします。具体的には、一般的な木造2階建ての住宅や軽量鉄骨造の建物です。尚、地下の部分を除き、階数が4以上、または延床面積が1,500㎡を超える建築物については、準防火地域でも耐火建築物とする必要があります。
上記の防火地域、準防火地域以外において、特定行政庁から屋根不燃区域と指定を受けている場合があります。これは建築基準法第22条によって規定されているため、「22条区域」と呼ばれています。内容としては、木造住宅の屋根や外壁について延焼の恐れがある部分には燃えにくい材料を使う必要がある、などの基準を定めたものです。
はっきりとした定義はありません。具体的には打ちっぱなしのコンクリート造の建物、空中階段、外構の照明計画など目立った箇所があるとデザイナーズ住宅と言われるのが実状のようです。たいていは物件の宣伝文句として「デザイナーズ住宅」という言葉が使われるだけであって、どの部分がデザイナーズ住宅なのかと質問しても、明確な答えが返ってこないことが少なくありません。
デザイナーズ住宅と言われる建物は、見た目を重視するあまり性能的な問題を抱えていることがあります。建具の細かい収まりを考えない設計図を元に施工するため、雨漏り、結露などのさまざまな問題が生じることがあります。実際にあった例としては、断熱材の施工がされないコンクリートの打ちっぱなし住宅で壁に結露が発生してカビだらけになってしまった物件もあります。デザイナーズ住宅は確かに凝った作りで見栄えもするのですが、見た目だけでなく建物の構造、仕様に問題がないか十分に確認した方がよいでしょう。
省エネ住宅とは、住宅の断熱、気密性能などを高めることで冷暖房機器による消費エネルギーを減らすなど、省エネルギーに配慮した住宅のことをいいます。
断熱とは「熱を断ち切る」という意味です。壁や天井などに断熱材を入れたり、窓のサッシにペアガラスやLow-Eペアガラスなどの断熱性能の高いものを採用したりすることで、外の温度変化から屋内が影響を受けにくくします。
気密性能とは、言い換えると住宅の密封性のことです。建物の隙間が少なく密封性が高いことを気密性が高いといいます。
省エネ住宅のメリットは、主に快適さの向上につながる光熱費の節約、環境配慮、各種税制優遇の3つがあります。
1つ目の快適さの向上につながる光熱費の節約とは、省エネ住宅は冷暖房効率が良いので、冷暖房費を抑えられるうえに室内環境も快適で生活しやすいことです。
2つ目は、冷暖房の使用を抑えて二酸化炭素の排出を減らすことができるので環境にも優しいことです。地球の温暖化を防ぐことにもつながります。
3つ目の各種税制優遇とは、省エネ住宅、低炭素化住宅の基準の建物を新築した場合は住宅ローン控除の額や登録免許税の軽減額を通常よりも増やせることです。
平成11年3月に当時の建設省(現国土交通省)により策定された「次世代省エネルギー基準」は、住宅の断熱性能の向上を目的とした基準です。この基準では、日本を北海道から沖縄までの8つの地域に分け、それぞれの地域の気候特性に応じた断熱性能の基準値が設定されています。これは、寒冷地と温暖地では必要とされる断熱性能が異なるという考えに基づいています。
なお、現在は「次世代省エネルギー基準」という名称は一般的ではなく、「平成28年省エネルギー基準」など、より新しい基準が導入されています。この基準は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づいて定められたもので、建物の断熱性能だけでなく、設備の効率性なども考慮されており、より高い省エネルギー性能が求められています。
建物の内側で断熱するか、外側で断熱するかの違いです。具体的には、木造一戸建ての場合は、屋根の裏側、屋根裏、壁の中などにグラスウールなどの断熱材を施工している住宅が多いです。これは内断熱工法と言われます。コンクリート造のマンションでも、躯体の内側に断熱材を吹き付ける、いわゆる内断熱工法で施工されることが一般的であり、外断熱工法で建築されているマンションは非常に希です。
外断熱のメリットは、建物の外側で断熱するので、外部の温度変化を受けにくくなることです。人間に置き換えてみると、冬にコートを着て寒さをしのぐ方法が外断熱、内側でシャツを着込む方法が内断熱となります。内側に着込むよりも外側からコートを着た方が身体全体を覆うことができるので、寒さ対策になりますよね。建物についても同じように外断熱の方が断熱効果は高まります。
日本以外の主要な先進諸国、例えばドイツ、スウェーデンなどでは住宅は外断熱で造るのが一般的です。特に鉄筋コンクリート造の建物については、外断熱のためコンクリートなどの躯体部分が外部にさらされないことで耐用年数が延び、建物寿命は100年以上と言われています。
一戸建ての場合には、内断熱か外断熱のどちらが良いかについてはそれほどこだわらず、断熱性能そのものの高さを意識すればよいと思います。しかし、鉄筋コンクリート造のマンションについては、断熱効果の観点から見ると外断熱の方が良いです。ただし、現状では技術やコストの問題があり、普及はしていません。外断熱工法が一般的になるにはまだまだ時間がかかりそうです。
建物の屋根にソーラーパネルを設置して太陽光によって発電することができます。その太陽光発電で作った電気を自宅で使用したり、余った電気を売却したりすることで結果的に電気代が安くなるためです。余った電気、すなわち余剰電気を電気会社に買い取ってもらうことを売電(ばいでん)といいます。
平成23年に発生した東日本大震災により電気を供給する原子力発電所が停止し、 電力不足が深刻になりました。国としても電力不足の解消を目的に太陽光発電の普及を推進する政策をとりました。具体的には、太陽光発電で生み出した電気を電気会社が買取る際に、一部を国が負担することで結果的に売電単価が高くなるという制度です。この国の補助金によって売電単価が高くなり、一気に太陽光発電の設備のある住宅が急増しました。
全国で急速に広まった太陽光発電の補助金制度ですが、平成24年以来年々売電価格は安くなっていく傾向にあります。ただし、設備費用(イニシャルコスト)も年々下がっており、太陽光発電で売電できるというメリットを失ったとは一概には言えません。太陽光発電を設置される方は今後の売電価格と設備費用とのバランスを確認することが必要です。
太陽光発電の最大の魅力は、停電時でも一定の電気量を確保できることです。停電が解消するまでにどの程度時間がかかるか分かりません。しかし、私たちの日常生活には電気がなければ成り立たないものがたくさんあります。照明、冷蔵庫、給湯器、テレビ、冷暖房機器などは生活には欠かせないものです。太陽光発電で自宅の電気量をまかなうことができれば、万が一のときにも安心できるのではないでしょうか。
自宅の建替えや新たに土地を購入してから新築するときに、二世帯住宅を建てたいという方が増えています。背景としては、相続税対策、二世帯住宅を建築するうえでのコスト削減、共同で助け合う暮らしがあります。二世帯住宅のメリットとデメリットを簡単に整理して解説します。
メリットの1つ目は相続税対策になることです。相続発生時に被相続人と同居していた場合、小規模宅地等の特例を使うことができれば、被相続人が所有していた自宅用の土地の評価が最大で80%減額されます。平成27年から相続税の基礎控除の引き下げなどによって相続税の課税対象となるケースが増え、平成26年以前に相続が発生し相続税の支払い負担がなかった方でも、相続税の支払い対象となるケースが増えました。被相続人の自宅敷地の評価が高ければ高いほど小規模宅地等の特例の効果が高くなります。
2つ目のメリットは、土地取得費用や建築資金を抑えられることです。二世帯住宅を建てる方の中には、両親が所有している土地、または土地の一部を利用する方がいます。この場合、土地の取得費用がかからなくなりますので、その分を建物の建築資金に回すことができます。また、建築するときにも2つの建物を建築するよりも、1つの建物を建築した方が建築費用は安くすることができます。
3つ目のメリットは、共同で暮らすことができる安心感です。両親も高齢になってくると、一人ではできないことも増えてきますし、一人暮らしになってしまうといざ体調が悪くなったときでも気付く人がいなくなってしまいます。そんなときに子世代が同居していれば、毎日顔を合わすことができるので体調が悪くなっても迅速に対応できるようになります。また子世代にとっても、孫の世話を助けてもらうことができます。
二世帯住宅のデメリットは3つあります。1つ目は、売却しにくいことです。住宅を購入する方のうち、二世帯住宅限定で探している方は少数派です。そのため、いざ売却しようとしても買い手が付きづらくなります。場合によっては、販売価格を下げなければならないこともあります。
2つ目のデメリットは、一緒に暮らす両親などと仲が悪くなっても毎日顔を合わせることになる点です。血のつながった親子であれば、まだ我慢できることだとしても、義理の両親と何十年も長期的に一緒に暮らすことになるとストレスが溜まりやすくなるでしょう。
3つ目のデメリットは、同居している両親と子ども、その他に相続人となる兄弟姉妹達と遺産トラブルになってしまう可能性があることです。具体的には、被相続人の資産の大部分が二世帯住宅の土地であり、他に相続人たちで分ける資産がほとんどない場合、不公平な相続になってしまう可能性があることです。トラブルが発展してしまうと、血縁者間の関係が悪化することもあります。こうなってしまうと、相続対策のための二世帯住宅がトラブルの元となってしまいます。
上記のデメリットを踏まえたうえで事前に対策を立てることが重要です。例えば、二世帯住宅が売りにくいのであれば、将来的に賃貸に出せるような間取りとすることを視野に入れておくのもよいでしょう。また、一緒に暮らす人同士がストレスを感じないようにプライバシーに配慮した間取りにする、具体的には玄関を2つにして、トイレやバスルームやキッチンなどの水回りも2つ造るのか、それとも共用にするのか、暮らし方に合わせて決めておくことも大切です。最後に、相続時に相続人間で揉めないように、将来的に相続が発生したときにどのように相続財産を分けるのか、生命保険などの活用も視野に入れて準備を進めておくことが重要です。