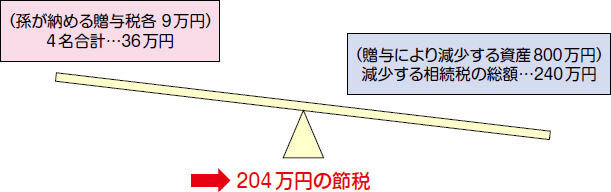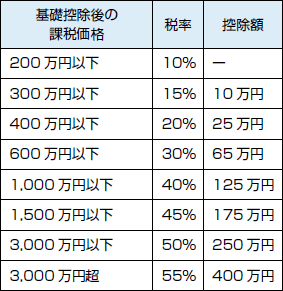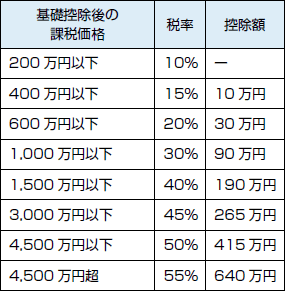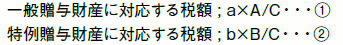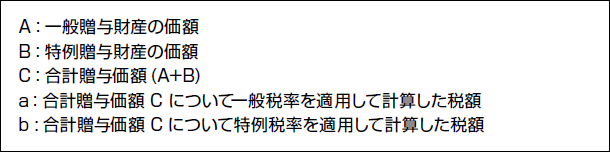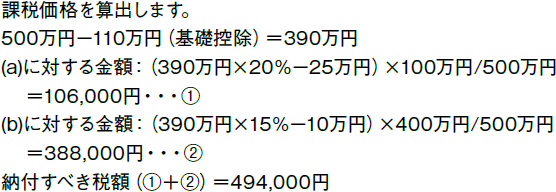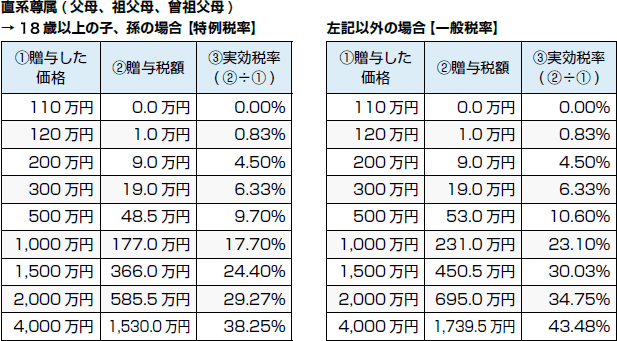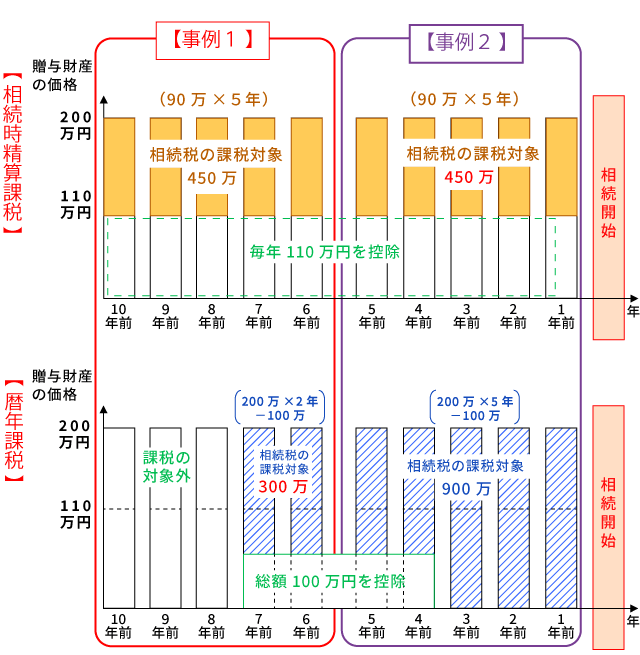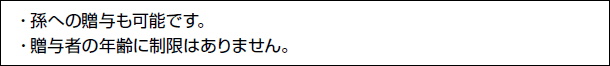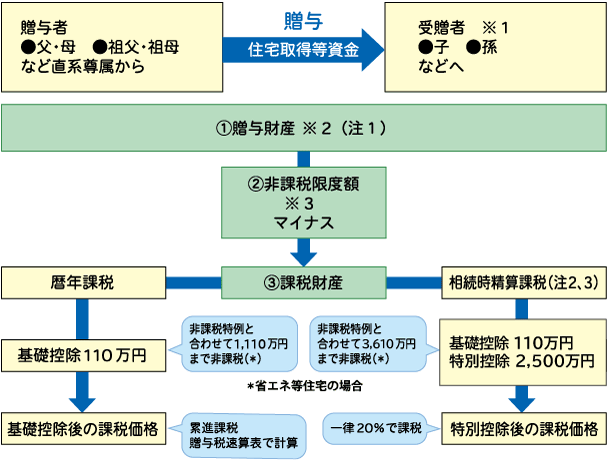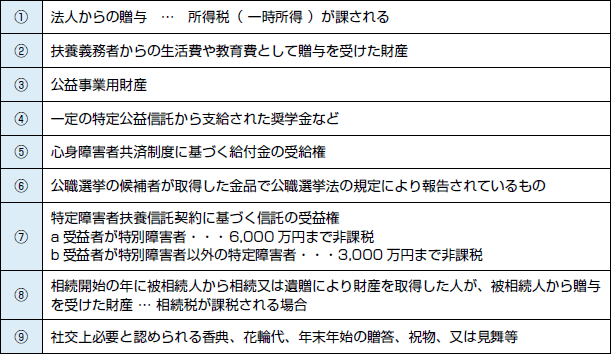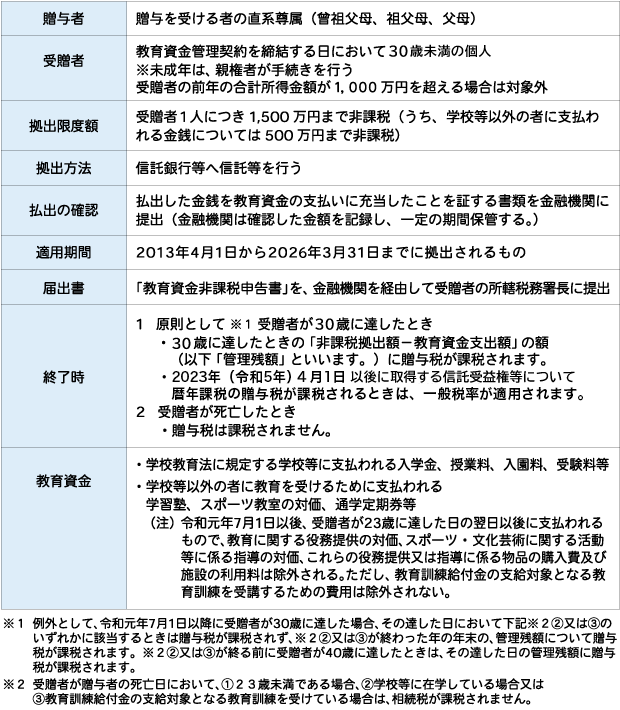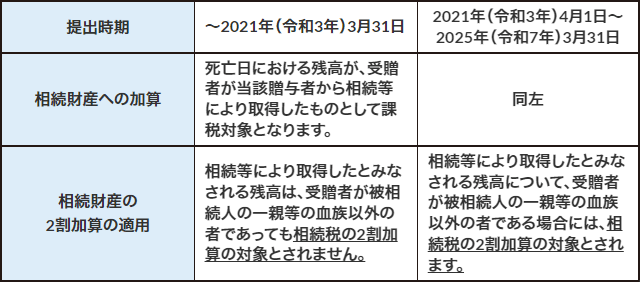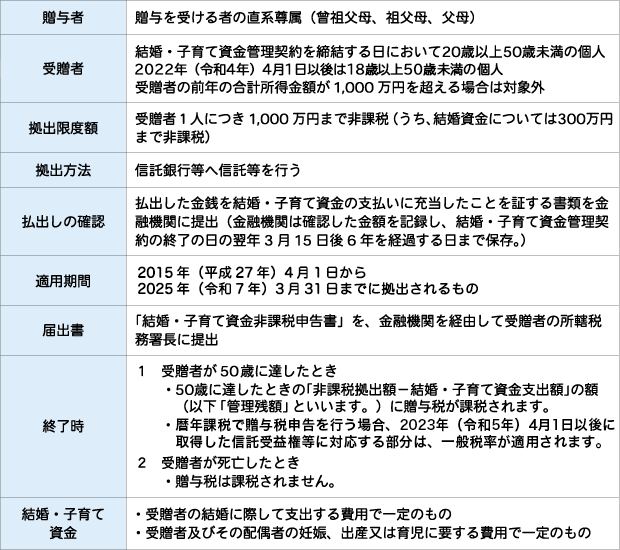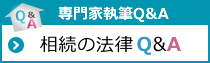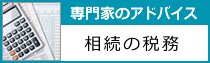相続税は一般的に増税になったといわれていますが、特例の拡大や創設などが行われており、工夫次第では相続税や贈与税の節税が合法的にできます。合理的で無理のない節税を解説しています。
贈与税の基礎知識
贈与税の基本的なしくみ
贈与税の計算のしくみ
贈与税の主な特例
贈与税は、個人から贈与を受けた者(原則として個人)に対して課税される税金です。贈与税の課税がなければ、生前に財産を妻子などにすべて贈与して相続税を回避することができます。相続税を回避するために行われる贈与に対し課税するので相続税の補完税といわれるのです。
一般社団法人・財団法人など(以下「一般社団法人等」といいます。)を使った相続税の回避の方法はないと考えてよいでしょう。一般社団法人等には、非営利型の法人と営利型の法人があります。非営利型の法人でも特定の一族に実質支配されている場合には、その法人を個人とみなして贈与税を課税する仕組みがあります。営利型の法人に対し個人が財産を贈与した場合は、原則として法人税が課税されます。
また、2018年(平成30年)4月1日以後においては、課税されないための要件を一時的に満たした上で一般社団法人等に贈与し、贈与後に一般社団法人等の私的支配を確立するなどして相続税を回避しようとする方法を防止するため、一般社団法人等に対する課税の見直しが行われました。
結果、一般社団法人等の理事(理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。)が死亡した場合で、一定の要件に該当する一般社団法人等に相続税が課税されることになりました。但し、同日前に設立された一般社団法人等については、2021年(令和3年)4月1日以後に発生した理事の相続について適用されます。
贈与税は相続税の補完税としての性格を有していますが、相続税の税率が贈与税の税率より高い場合は、生前に贈与をした方が税負担は少なくてすみます。贈与する財産や金額などをよく検討し、上手に制度や特例を活用すれば、より効果的に相続税の節税を図ることができます。
単純な例でご説明しましょう。資産家Aさんが4人の孫に現金を200万円ずつ800万円贈与した場合、贈与税は一人当たり9万円((200万円-110万円)×10%)、4人合計で36万円です。Aさんは5億5,000万円ほどの財産を有する資産家です。配偶者は先立ち、相続人は子2人です。もしAさんが亡くなるとおおよそ1億7,400万円ほどの相続税が課税されます。相続税額を遺産の額(課税価格)で割ったものを実効税率といいます。Aさんの実効税率は30%程です(1億7,400万円÷5億5,000万円≒30%)。贈与により減少する800万円に30%をかけると相続税が240万円減少することがわかりますので、贈与税との差額204万円の税金が節約できたといえます。
そのとおりです。5億5,000万円→5億4,200万円と800万円課税価格が減少すると、相続税の累進税率では45%の層の中で800万円減少します。税率の高い層で財産が減少する結果、相続税の納税額は1億7,460万円→1億7,100万円と360万円減少します(800万円×45%=360万円)。
実務的には、高額の財産を有する人ほど暦年贈与による相続税の節税効果は高いのです。ただし、相続開始前3~7年以内(相続開始時期によって異なります。)に被相続人から贈与を受けた金額については相続財産に加算する必要があり、前述の効果を得られなくなります。したがって、たくさん財産を保有している人は、早期に、税理士とよく相談して毎年子や孫に贈与を行うと、時の経過とともに相当効果的な節税ができる可能性があります。
特例贈与財産とは、財産の贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産をいいます。一般贈与財産とは、特例贈与財産以外の財産(配偶者や兄弟姉妹からの贈与、未成年者に対する贈与など)をいいます。
2種類の税率表があります。速算表で示すと次のとおりです。
【一般贈与財産用】(一般税率)
図表21 は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、父母から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
【特例贈与財産用】(特例税率)
図表22 は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「その年の1月1日において18歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父から妻が受ける贈与等には使用できません)。
1月1日から12月31日の間に、贈与により一般贈与財産(a)100万円と特例贈与財産(b)400万円、合計500万円を取得した場合の贈与税の計算は次のとおりです。
受贈者Aが1月1日から12月31日の間に受けた贈与財産の合計額が贈与税の基礎控除110万円を超えるときは、翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告と納税をしなければなりません。
Aが複数の人から贈与を受けた場合でも、1月1日から12月31日までの間に受けた財産の合計額が110万円を超えるときは贈与税の申告が必要です。
相続時精算課税とは、原則として贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価。ただし、令和6年1月1日以後の贈与財産については、贈与を受けた年分ごとにその贈与財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
※相続税精算課税に係る基礎控除額については、Q 相続時精算課税を選択した贈与者A(特定贈与者)が亡くなりました。参照
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、まず相続時精算課税に係る基礎控除額(1年あたり最大110万円)を控除し、さらに複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注1) 相続時精算課税に係る贈与と暦年課税に係る贈与の両方がある場合は、それぞれの贈与について相続時精算課税に係る基礎控除額110万円及び暦年課税の基礎控除額110万円の控除をすることができます。
なお、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与については、相続時精算課税の贈与が110万円の基礎控除以下であれば贈与税の申告をする必要はありませんが、その場合であっても初めて相続時精算課税の贈与を受ける場合は、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
(注2) 2024年(令和6年)1月1日以後に相続時精算課税適用者が贈与により取得した一定の土地又は建物が贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価格へ加算する価額は、贈与時の価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額になります。
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、次のとおり計算します。
① 相続時精算課税の適用を受けた価額から、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与を受けた財産の価額のうち、年110万円の基礎控除額を控除した額の合計額を計算します。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、原則として贈与時の価額です。
② 相続や遺贈により取得した財産の価額と上記①の価額の合計額を基に相続税額を計算します。
③ 既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
メリット、デメリットは、次のとおりです。
(1) メリット
① 贈与者の死亡の時まで通算で2,500万円の贈与税の特別控除額が使え、2,500万円までなら贈与税の負担なく贈与を受けることができます。
② 贈与を受けた財産を相続財産に加算する価額は、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与分については年110万円の基礎控除額を控除した後の価額であり、かつ、過去の贈与を受けた時の価額です。したがって、年110万円以下の贈与であれば相続財産に加算されず、加算される場合であっても贈与を受けた財産が値上がりすると節税効果があります。
③ 贈与を受けた財産から生じる収益は、受贈者が受け取ることになるため、所得税率の高い贈与者から低い受贈者へ財産を移転した場合、所得税の節税効果があります。
④ 相続時精算課税制度適用者が、特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物について、その贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、2024年(令和6年)1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価格へ加算する価額は、贈与時の価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額になります。
(2) デメリット
① この制度の適用後、選択した贈与者からの贈与については、相続開始前3年以上前の贈与であっても全て相続税の課税対象とされます。
② この制度を選択すると、選択した贈与者からの贈与について、暦年課税方式は適用できなくなります。
③ 贈与を受けた財産の価額は贈与した時の価値に凍結され、将来相続が開始した時には相続時の評価額ではなく贈与時の評価額で課税されますので、贈与した物が値下がりすると増税効果が生じてしまいます。
④ 小規模宅地等の特例の対象となる土地等や物納ができる土地等は、相続又は遺贈により取得したものであることが要件です。相続時精算課税で贈与を受けた財産は、贈与により取得した財産なので、課されるのは相続税でも、小規模宅地等の特例は使えませんし、物納もできません。
⑤ 相続税の計算上、孫は祖父母の一親等の血族や配偶者ではないため、相続時精算課税の受贈者になることができる年齢要件を満たした孫に対する贈与は、相続税の二割加算の対象となります。
次の2パターンの比較で明らかなように、生前贈与の開始時期によって加算額は大きく異なることとなります。
【事例1】相続開始10年前から5年間で毎年200万贈与した場合
【事例2】相続開始5年前から亡くなる直前まで毎年200万贈与した場合
このように、生前贈与を始める時期などによって「相続時精算課税の贈与」又は「暦年課税の贈与」のいずれが有利であるかは変わりますが、「暦年課税の贈与」は生前贈与の時期が早ければ早いほど、相続税の課税対象外とすることができます。
このため、相続税対策は早めに、かつ計画的に取り組む必要があります。
次のとおりです。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・内縁期間は含みません。戸籍上の婚姻期間が20年以上あることが必要です。
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・ 夫婦で現在住んでいる家の敷地だけを贈与した場合にも最高2,000万円まで控除できます。
・ 贈与を受けた配偶者は登録免許税や不動産取得税が課税され、贈与後の固定資産税も受贈者が負担すべき租税公課となります。
・ 将来、贈与を受けた家を譲渡するときに、土地だけでなく家屋の持分も有している場合は、譲渡所得に係る居住用の特別控除(最高3,000万円)を受けることが可能です。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
・ 購入や建築資金の贈与を受けた場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに国内で住むための家を取得する必要があります(その敷地の上にある住宅に居住することが必要ですが、敷地だけの取得も可)。金銭贈与を行う場合は、取得時期について注意が必要です。
(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
(注)この特例を受ける場合は、税額が0になる場合であっても贈与税の申告が必要です。ご注意ください。
まずご自宅の敷地の相続税評価額を算定します。測量図があれば用意し、測量図がない場合は、ご自宅の間口を測り、だいたいの地形が分かる書類を用意し税理士に評価額の算定を依頼します。
税理士がご自宅の評価額を算定後、全体が2,000万円を超える場合は、2,000万円に相当する持分を算出します(税理士は、相続税の評価額を算定するために、路線価地域では、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成します。)。
次に税理士が算定した持分に基づき、司法書士に贈与登記を依頼します。
そして贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を受贈者である妻が行います。
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 贈与契約書、登記事項証明書など居住用不動産を取得したことを証する書類
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書など)が必要となります。
2024年(令和6年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、受贈者1人についての非課税限度額は、住宅用家屋が省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円となります。
原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の居住用家屋を取得等し、かつ、居住の用に供する必要があります。
(注1) 2024年(令和6年)1月1日以後の贈与について既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
(注2) 省エネ等住宅の範囲は、以下のいずれかに適合するものとして、一定の書類により証明されたものです。
●耐震住宅・・・耐震等級2以上又は免震建築物に該当する住宅(柱・屋根の接合部強化、基礎の強化等)
●エコ住宅・・・断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅(ZEH強化外皮基準に適合する程度、かつ、照明や冷暖房設備の省エネ性能が高い住宅等)
●バリアフリー住宅・・・高齢者等配慮対策等級3以上の住宅(手すりの設置、床の段差が小さい等)
ただし、2024年(令和6年)1月1日以後に贈与を受けて住宅の新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得する場合において、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ、次のいずれかに該当するときは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用家屋とみなされます。
イ 2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けていること
ロ 2024年(令和6年)6月30日以前に建築されたもの
なお、2009年(平成21年)分から2023年(令和5年)分において、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けている場合には、2024年(令和6年)分以降の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません。
●受贈者:18歳以上の子や孫で合計所得金額2,000万円以下(新築等した住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)である人
●贈与者:受贈者(詳細はQ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けられる人(受贈者)はどのような人ですか。参照)の直系尊属(年齢制限なし)
●暦年贈与適用者と相続時精算課税適用者の双方が利用可能
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
① 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)
② 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないが、一定の要件を満たす者
A 日本国籍を有している者で、次のいずれかに該当する者
a 贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある者
b 贈与前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがない者(贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)
B 日本国籍を有していない者(贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)
*一時居住者、外国人贈与者及び非居住贈与者については、Q 一時居住者、外国人贈与者及び非居住贈与者とはどのような人ですか。を参照
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
*直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円(新築等した住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円)以下であること。
一時居住者とは、贈与の時において在留資格を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
外国人贈与者とは、①贈与の時において在留資格を有する人で、日本国内に住所を有していた贈与者及び②贈与の時において日本国内に住所を有していなかった人で、贈与前10年以内において日本国内に住所を有していたことがある人のうち日本国籍を有していなかった贈与者をいいます。
非居住贈与者とは、贈与の時において日本国内に住所を有していなかった人で、贈与前10年以内においても日本国内に住所を有していたことがない又は贈与前10年以内に日本国内に住所を有していても日本国籍を有していなかった贈与者をいいます。
住宅取得等資金とは、贈与を受ける人が自宅を新築若しくは取得又は自宅の増改築や大規模修繕などの対価に充てるための金銭をいいます。
なお、自宅の新築若しくは取得又はその増改築等には、次のものも含まれます。
① その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
② 自宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
ただし、受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例の適用を受けることはできません。受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者とは、次の者をいいます。
(1) 受贈者の配偶者及び直系血族
(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの
(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
次のとおりです。
1.取得する家屋の要件
特例の対象となる居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が2つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる1つの家屋に限ります。
(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。
受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であるときは、前記床面積の下限が40㎡以上となります。
(2) 購入する家屋が中古の場合は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたものであること。
② 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「建設住宅性能評価書の写し」又は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」により証明されたものであること。
③ ①及び②のいずれにも該当しない家屋の場合で、その家屋の取得の日までに同日以降に耐震改修工事を行うことについて所定の手続きをし、かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき、一定の書類で証明されたものであること
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
2.増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有する自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
(2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
(3) 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡(受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡)以上240㎡以下であること。
(4) 増改築等に係る工事が、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
直系尊属から住宅取得等資金等の贈与を受けた場合の非課税特例における住宅取得等資金とは、原則として、贈与を受ける人が自宅を新築若しくは取得又は自宅の増改築等の対価に充てるための金銭をいいますが、①その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得②住宅用の家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得も含まれます。土地単独の取得は対象となりません。必ず受贈者は建物を取得しなければならないことに注意してください。
できます。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例適用後の残額について、暦年課税又は相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)が適用できるほか、相続時精算課税についてはさらに特別控除(2,500万円)も適用できます。なお相続時精算課税に係る特別控除(2,500万円)の適用は、60歳以上の父母や祖父母からの贈与に限られますが、受贈資金で18歳以上の子や孫が家を購入する場合は、贈与者が60歳未満でも可能です。各制度の併用関係は、次の図のとおりです。
(注1) 原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する必要があります。床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋が対象。受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であるときは、前記床面積の下限が40㎡以上となります。
(注2) 相続時精算課税を選択した場合、相続時に他の相続財産と合わせて相続税を計算し税額の精算をする必要があります。
※1 Q 直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けられる人(受贈者)はどのような人ですか。参照
※2 下記参照
次のとおりです。
2026年(令和8年)12月31日までに、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた18歳以上の子や孫が、次の(1)又は(2)のいずれかの条件を満たすときは、贈与者である父母や祖父母の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税(特別控除2,500万円)を選択することができます。
(1) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を一定の家屋の新築又は取得のための対価に充てて新築又は取得をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
(2) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てて増改築等をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
(注)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。
次の要件の全てを満たす受贈者が相続時精算課選択の特例の適用を受けることができます。なお、Q 直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けられる人(受贈者)はどのような人ですか。との違いは、贈与を受けた年の所得制限がないことです。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
① 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)
② 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないが、一定の要件を満たす者
A 日本国籍を有している者で、次のいずれかに該当する者
a 贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある者
b 贈与前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがない者(贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)
B 日本国籍を有していない者(贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)
*一時居住者、外国人贈与者及び非居住贈与者については、Q 一時居住者、外国人贈与者及び非居住贈与者とはどのような人ですか。を参照
(2) 贈与者の直系卑属である推定相続人である子又は孫であること。
(3) 贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上であること。
住宅取得等資金の範囲は次のとおりです。
住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいい、「Q 直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税特例を受けられる住宅取得等資金の範囲を教えてください。」の内容と同じです。
取得や増改築をする家屋の要件は下記の点を除き住宅取得等資金の非課税制度(Q 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が取得や増改築をする家屋はどのような家屋でなければならないのでしょうか。参照)と同様です。
◎住宅取得等資金の非課税制度との違い
住宅取得等資金の非課税制度の対象となる家屋は、床面積(登記簿面積)が床面積50㎡(合計所得金額1,000万円以下のときは、40㎡)以上240㎡以下でなければなりませんが、相続時精算課税制度の特例の対象となる家屋は、所得制限や家屋の床面積の上限がなく、床面積40㎡以上です。
相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、受贈者や贈与者の戸籍謄本・戸籍の附票、登記事項証明書など一定の書類を添付して納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
相続時精算課税選択届出書の提出を忘れると精算課税の適用を受けることができなくなります(期限内提出が要件です。)。気を付けましょう。
次のような贈与や財産については、贈与税は課税されません。
例えば、祖父母が孫の大学入学金などの学費を負担しても、孫に贈与税は課税されません。そのため、多額の相続税の負担が見込まれる場合などは、祖父母が直接学費を負担してあげる方が税制上は有利といえます。
* 2013年(平成25年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までの間に、子や孫など直系卑属の教育資金の支払いに充てる為に金銭等を拠出して信託銀行などに信託などを行った場合には1,500万円まで贈与税を非課税とする措置が設けられています(Q 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例について説明してください。参照)。
* 2015年(平成27年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に、20歳(2022年(令和4年)4月1日以後は18歳)以上50歳未満の子や孫などの将来の結婚・子育て資金の支払いに充てるために、直系尊属(祖父母や父母)が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行、証券会社などの金融機関に信託等をした場合、贈与を受ける人1人について1,000万円(結婚費用については、300万円)までの金銭について贈与税を非課税とする措置が設けられています(Q 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例について説明してください。参照)。
2013年(平成25年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)が子や孫などの教育資金に充てるために金銭等を拠出し、信託銀行、銀行、証券会社などの金融機関に信託等をした場合に、贈与を受ける者1人につき1,500万円までの金額について贈与税を課税しない制度です。なお、贈与を受ける者の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税特例を受けることができません。
相続税法は、扶養義務者からの生活費又は教育費の贈与で、通常必要なものと認められるものについては、必要な都度直接これらの用に充てるものに限り、贈与税を非課税としています。生活費又は教育費の名目で取得した財産を受贈者が預金した場合などは、必要な都度、必要な額を負担するものではないので、贈与税が課税されるのが相続税法の規定です。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例は、教育資金として前払(一括贈与)した金銭等について、金融機関が管理することを前提に1,500万円まで非課税とするものです。
この制度を利用し贈与された財産については、教育資金に充てるために金銭等を拠出して金融機関に信託等をした時期により、贈与者の死亡した時の残高に対する相続税の課税が以下のように違いますので、注意が必要です。受贈者がこの特例により取得したものとみなされる財産以外に、相続又は遺贈による財産を取得しない場合には、相続開始前の一定の期間内(3~7年)の生前贈与加算の対象にはなりません。
なお、相続税が課税される場合、受贈者が法定相続人以外の孫であるときは、相続税の二割加算の対象となります。
2015年(平成27年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までの間に、個人(18歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金の支払いに充てるために直系尊属(父母や祖父母)が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行、証券会社などの金融機関に信託等をした場合に、贈与を受ける者1人につき1,000万円(結婚費用については300万円)までの金額について贈与税を課税しない制度です。なお、贈与を受ける者の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税特例を受けることができません。
相続税法は、扶養義務者からの生活費又は教育費の贈与で、通常必要と認められるものについては、必要な都度直接これらの費用に充てられるものは贈与税を非課税としています。
この特例は、結婚・子育て資金として一括贈与した金銭等につき1,000万円(結婚については300万円)まで非課税とするものですが、贈与者が死亡した時に残高があれば、残高を相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
ただし、相続又は遺贈により取得したとみなされる残高は、2021年(令和3年)3月31日以前に贈与を受けた部分については、受贈者が被相続人の一親等の血族以外の者であっても相続税の2割加算の対象とされません。また、受贈者がこのみなし分以外に相続又は遺贈による財産を取得しない場合には、相続開始前の一定期間内(3~7年)の生前贈与加算の対象にはなりません。