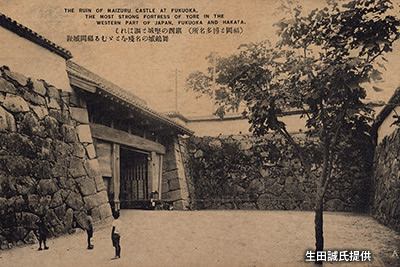「香椎宮(かしいぐう)」は、社伝では200(仲哀天皇9)年に神功皇后が祠を建て、夫である第14代仲哀天皇の神霊を祀ったことに始まるとされ、724(神亀元)年、神功皇后の神霊も祀られ、この両宮を併せて「香椎廟」と呼ばれるようになったといわれる。現在の本殿は江戸後期の1801(享和元)年、第10代福岡藩主・黒田斉清により再建され、「明治維新」後は官幣大社の「香椎宮」となった。写真は明治後期の「香椎宮」。左奥に見える楼門は1903(明治36)年に建立されたもので、手前右の線路は1904(明治37)年に開通した博多湾鉄道(現・JR香椎線)。【画像は明治後期】
「博多湾」に沿って広がる福岡・博多は、九州有数の商業・工業都市であるばかりでなく、国内外から多くの人が集まる日本有数の観光都市の要素も持つ。古くはその重要性から、周辺に「大宰府」「鴻臚館(こうろかん)」が置かれた日本外交の拠点であり、その後は商人が活躍する港町・博多が誕生した。江戸時代にはその西側に黒田氏の城下町・福岡が生まれ、東西の2つの街が競い合うように発展した。「明治維新」後、両者は合併して県庁所在地の福岡市となり、現在は博多区と中央区にあたる地域になっている。その中で、JRの駅は今も「博多駅」を名乗るなど、2つの地名は併存し、市民の間に浸透している。また、この街を彩る季節の祭りは熱く、特産品や食品は全国に通用するブランドも多い。