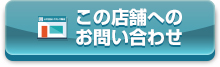営業日記、地域の情報・出来事 一覧
- 全73件中 36~40件を表示
- <前へ |
- ... |
- 6 |
- 7 |
- 8 |
- 9 |
- 10 |
- ... |
- 次へ>
日々営業日記
地下室は容積率が緩和される?~容積率の不算入措置について~
2017/06/02
みなさんこんにちは!荻窪センターの龍(りゅう)です!
突然ですが、
地下室がある住宅って、非常に贅沢な家ですよね。
地下室と言うこともあり、採光の面から考えるとそこで生活するのはあまりオススメはしませんが、あまり使わない物を仕舞う収納として、また趣味の部屋として、機能してくれる点が期待されます。
そんな地下室についてなのですが、実は容積率に対し一部不算入になるのです!
今日は、その地下室の容積率不算入の話と、地下室の定義についてみなさんにご紹介します。
まずは本題から。
建築基準法では、指定された条件を満たすものにつき、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として、延べ面積に算入しません。「住宅の地階に係る容積率算定上の特例(法52条2項、3項)」
つまり、100㎡の大きさの土地で、建蔽率・容積率がそれぞれ50%・100%と指定されている場合につき、100㎡のうち33.3㎡までの大きさの地下室であれば、容積率に算入されないと言う事です。
この場合、おおよそ10坪くらいの大きさの地下室が丸々作れると言う事ですね!
ただし、それには以下の条件を満たさなければなりません。
~容積率不算入の条件~
・住宅の用途に供する地階であること。
・地階の天井が地盤面からの高さ1m以下にあること。
この条件を満たすものであれば、地下室として認められ、通常の平屋や二階建てで建築するのに比べ大きな家が建てられると言う事です。
ご留意いただく点として、地下室を作ると言うことは、それに伴い地下室のない住宅に比べ予算が大幅に上がってしまう点があります。
その点については、建築を検討している工務店やメーカーに相談して、どれくらいの費用がかかるのかにつき確認する事をオススメ致します。
いかがでしたか?夢のマイホーム建築に、機能性や遊び心を加える地下室・・・ご検討されてみるのもありかと思います!
以上、荻窪センターの龍でした。次回もお楽しみに!!!
日々営業日記
不動産における数値表示のいろは
2017/06/01
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍です!
本日も不動産豆知識のご紹介をさせていただきます!
新聞をご覧になる際に、不動産の折込広告が入っている事はよくありますよね。
弊社でも、現地見学会の開催や新規物件のご紹介に伴い、新聞への折り込み広告を実施いたしております。
そうした中、不動産の概要を見てみると「リビング○○帖!」であったり、「△△駅まで徒歩□分!」と言うような広告の見出しをご覧になると思います。
そこで一つの疑問・・・1帖や1坪は何㎡なのかという点と、徒歩1分は何mなのでしょうか?
今回は、そんな不動産の数値表示について記載いたします。
~大きさを表す表記について~
1帖:大きさは1.62㎡です。(※)畳1枚分の大きさとイメージしていただければ分かりやすいかと思います。
1坪:大きさは3.30578㎡です。畳2枚分の大きさがこれに該当いたします。(※)
~長さを表す表記について~
徒歩1分:不動産の広告における徒歩1分当たりの距離は、80mで換算しています。つまり、徒歩5分であれば、80m×5=400mと言った感じでしょうか?
1間:1間は1.81818メートルです。一般的に普及している畳(中京間)の長いほうの1辺の長さになります。
(※)・・・1帖の大きさは、一般的に1.62㎡で算出する場合と、1.65㎡で算出する場合の2通りがあり、このブログでの1帖の表記については、1.62mを採用いたしております。理由として、中京間の大きさは910mm×1820mmで、1.65㎡での算出ですが、それを900mm・1800mmとし、900mm×1800mm=1.62㎡で算出しているためです。
また、これは余談であり、不動産の数値表記とは少し異なるのですが、塀などに利用されるコンクリートブロックの大きさは、20cm×40cmの大きさで、側溝に使用されるL字溝の長辺の長さは60cmが一般的な大きさになっております。
これについては、土地の四方に関し、概ねの一辺の長さを確認する際に便利になる知識ですが、弊社では、メジャー等を利用ししっかり測らせて頂きます!
「10メートル以上あるようなメジャーがないんだけど、だいたいの土地の奥行きが知りたいなあ」や、「奥行きと間口(道路に土地が面している長さ)を知りたいけど、わざわざメジャー買ってまで知りたいとは思わないなあ」といった際に、おおよそどれくらいあるのかという確認をする際にこれを思い出して、測ってみてはいかがでしょうか?
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
日々営業日記
どっちに住む?~マンション高層階と低層階~
2017/05/30
みなさんこんにちは!荻窪センターの龍(りゅう)です。
荻窪センターが担当している杉並区は、山手線の内側など、都心でも中枢部にあたる地域に比べ、全体的に見ると住宅街が多い地域となります。
しかし、そんな杉並区にも、駅前や青梅街道沿い、環状8号線沿いと中央自動車道沿いなどには10階建を超えるマンションが立ち並ぶような地域があります。
そこで、マンションに住む事を考えると、低層階のマンションを選ぶのか、高層階のマンションを選ぶのか…これはお客様それぞれ考えがあられてお選びになると思いますが、それぞれについてどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
今回は、高層階に住む事・低層階に住む事に対するメリットとデメリットについて解説させていただきます!!!
~高層階について~
1.メリット
・眺望がいい点
・周囲に高い建物が無いと、人の目を気にする必要がない点
・蚊など、虫の侵入が少ない点
・採光について、外から入る光を遮られる事がほとんどない(前提として周囲に高い建物が無い事が条件となります)点
・窓を閉めれば騒音が少ない点
2.デメリット
・価格が高い点
・通勤時間帯のエレベーター待ちの時間が長い点
・地震の際に低層階に比べ揺れが大きい点
・お子様を迂闊にバルコニーに出せない点
・人によりますが、高層階が体質に合わない事がある点
・虫は来なくても、鳩やカラスが来る可能性がある点
高層階の特徴はこのようなところです。では、低層階はどうでしょうか?
~低層階について~
1.メリット
・高層階に比べ安い点
・エレベーターを使わずとも階段の利用で対応できる点
・地震の際に高層階に比べ揺れない点
・高層階に比べ非難等がしやすい点
2.デメリット
・物件により湿度が高くカビ対策が必要になる場合がある点
・虫が来る可能性が高いという点
・1階は防犯面について心配があり、内部が丸見えにならぬ様カーテンを締め切って 生活しなくてはならない場合がある点
・震災時は1階が倒壊する可能性もある点
低層階についてはこのような点が特徴として挙げられます。
いかがでしたでしょうか?マンションの高層階・低層階どちらにも良いところがあり、悪いところもあります。
最も重要な事は、上に挙げたメリット・デメリットを考慮したうえで、皆様の生活にどちらが適しているのか?また、デメリットが耐えられるもの、もしくは対策を講じればデメリットに感じられないものなのか?だと思います。
皆様の、そうした条件の取捨選択を行ううえでの一助になれば幸いです。
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
日々営業日記
リフォームとリノベーション、何が違うの?
2017/05/29
皆さんこんにちは!荻窪センターの龍(りゅう)です。
本日も暑いですね・・・。風邪が治っていない状況でのこの蒸し暑さはなかなか厳しいものですが、いち早く治せるように養生いたします。
皆さんも季節の変わり目の風邪にはお気をつけてくださいね。
さて、本日のテーマですが、「リフォームとリノベーションの違いについて」を解説させていただきます。
中古マンションや中古戸建の広告を見ると、「新規リフォーム済」という文字が躍るものもあれば、「新規リノベーション済」との文字もあったり・・・。
ん?この二つは何がどう違うの?とお思いになられる方も少なくないと思います。
実際、リフォームを行った物件も、リノベーションを行った物件も、遜色なく内部が真新しく綺麗なものになっている事が多いです。
では、何が違うのでしょうか?以下に解説します。
~リフォーム~
リフォームは、古くなった設備や内装を新しくしたり、間取りを変えたりすることを指します。「住まいの改修」全般を表す言葉として最もよく見る言葉ではないでしょうか?
ちょっとしたクロスの張り替えや、古くなった設備の取替えから大がかりな改修や増築まで何でも「リフォーム」と呼ばれていますが、強いて言えば、老朽化したものを新築の状態に戻すというニュアンスで使われる言葉です。
~リノベーション~
リノベーションは、古い建物のよさを活かしながら、給排水・電気・ガスの配管なども全面的に刷新し、新築時以上に性能を向上させたり、住まい手の好みのデザインや間取りに変えたりすることにより、中古住宅に「新たな付加価値」を生み出すことです。
最近では、住宅購入の新しい手法として、中古マンションや一戸建てを購入し、大がかりな改修を行うことを総称して「リノベーション」と呼んでいるケースが多いです。
実は、上記2つには明確に「ここが違う!」と言える定義がないのですが、上記のようなイメージだとお考えいただければと思います。
それに伴い、売主様がどちらの表現を好んでお使いになられるかと言う要因もあります。ただし、どちらにせよ、お部屋を新築時のように綺麗にした状態、即入居可能という状態で皆様にご提供すると言う事には変わりありませんね。
私が物件を見てきた中では、一概には言えないものの、築年数が20年・30年経過しているようなマンションでリノベーションが実施され、築年数が10年くらいのマンションでリフォームが行われているように感じます。
いかがでしたでしょうか?今回のブログで、リフォームを行った物件・リノベーションを行った物件の違いを判断していただければと思います。
以上、荻窪センターの龍でした!次回もお楽しみに!
日々営業日記
地区計画って何?~地域に根ざした街づくり~
2017/05/28
皆さんこんにちは! 荻窪センターの龍(りゅう)でございます。
今回も私のブログをご覧の皆様に、不動産に関するお役立ち豆知識をお届けします!
今回のテーマは、「地区計画について」
皆さんは、建物を建てる際に都市計画による様々な制限が建築物に加えられている事をご存知でしょうか?
例えば、依然ご紹介した「用途地域」による制限や、敷地の最低限度などがそれに該当します。
このような都市計画上の制限により、建てられる建物の棲み分けを行い、皆さんの住みよい環境を提供しようとしているわけです。
それでは、「地区計画」とはいったい何なのでしょうか?
地区計画は、非常に簡単に言うと「特定の地域に根ざした更に細かい都市計画」と言ったところでしょうか?
つまり、特定の地域の特性や課題にあわせた公園・道路の配置を行い、住環境をより良いものにするという考え方から来ているものです。
ちなみに、地区計画においては建物に対する制限が都市計画上の制限よりも厳しいものとなる事がよくあります。
例えば、建ぺい率・容積率をそれぞれ50%・100%と指定している地域において、それぞれを40%・80%に指定するなどが分かりやすいと思います。
他にも、建物の高さの制限を厳しくしたり、建物の色彩についての制限などもあったりします。
じゃあ、その制限を守らないとどうなるの?ということについてですが、以下の通りです。
地区計画の区域内における建築については、建築着工の30日前までに、各自治体(区町村)に届出しなくてはなりません。
各自治体は「建築制限条例」を定め、建築に関する制限につき条例化し、建築基準法と連携する形を取っています。
そのため、制限の内容が建物を建てる際の建築確認の審査事項になり、守っていないと建築は出来ません。
その届出によるチェックを経て、晴れて着工となるわけですね。
地区計画の定めのある地域に住まう事は、住環境的な面から見ると非常に良いと思われます。
しかし、上述の通り建物に対する制限が厳しいので、地区計画が定められている地域の土地をご購入される際は、検討している建築プランが入るのか否かと言うところに関し確認し、吟味しなくてはなりません。
いかがでしたでしょうか?皆様の物件選びの基準のひとつとなれば幸いです。
以上、荻窪センターの龍でした。次回もお楽しみに!
三井住友トラスト不動産 名古屋コンサルティング営業センターでは愛知県を中心とした中部圏の投資・事業用物件を数多く取り揃えております。中部圏エリアでの投資・事業用物件のご相談は名古屋コンサルティング営業センターまでお気軽にお寄せください。