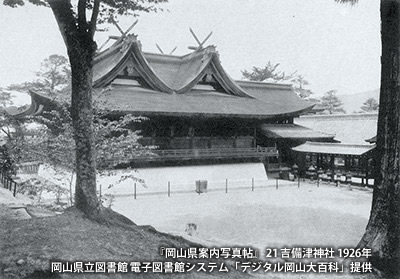古代「吉備国」は、大和、筑紫、出雲と並ぶ古代日本の四大王国の一つとされる。古墳時代前期、「ヤマト王権(大和朝廷)」の第十代 崇神天皇は「彦五十狭芹彦命(ひこいさせりひこのみこと)」を吉備へ派遣し対立する豪族を征伐し平定したとされ、これが「桃太郎伝説」の元になっているともいわれる。「彦五十狭芹彦命」は第七代 孝霊天皇の皇子で、のちの「大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)」(以下「吉備津彦」)と同一人物とされる。征伐の際は「吉備の中山」に陣を構えたといわれる。「吉備の中山」は吉備の中心となる山で、現在、山上に残る前方後円墳「中山茶臼山古墳」は「吉備津彦」の墓とされている。
MAP __(吉備の中山)
「吉備国」は689(持統天皇3)年発布となる日本最初の律令「飛鳥浄御原令」で「備前国」「備中国」「備後国」に分割され、さらに713(和銅6)年に「備前国」の内陸部が「美作国」として分割された。分国の理由は「吉備国」の強大な勢力を弱体化させるためだったとも考えられている。現在の岡山市内においては、「吉備の中山」を分割する形で、東側が「備前国」、西側が「備中国」となった。