

不動産を中心とした資産活用及び相続対策について、税理士のアドバイスです。
~必ずチェックしましょう~ 相続税の増税に備えてNo.3
1 前回のおさらい
前回までのお話しは、次のとおりでした。
自宅の小規模宅地の計算の特例は、亡くなられた方の自宅の敷地を配偶者又は同居の親族が相続すると330㎡(平成26年末までに相続が開始した場合は240㎡)まで、税金の対象となる価格(課税価格)を8割減額して相続税を計算することができるという特例です。
減額割合が8割ということは、自宅の土地の相続税評価額が5,000万円の場合なら、課税価格は4,000万円減額され、税金の対象となる財産額は1,000万円でよいということです。
これだけ大きく変わってくると、この特例を適用できるか否かで相続税が大幅に違ってくるので、相続が開始するまえに、現状で特例が使えるのかを確認しておくことは重要です。もし、使えない場合には、使えるように対策を考えてみるということも、自衛の意味での節税としては重要なことです。
事例分けをすると次のとおりです。
(1) 配偶者がいる場合には、配偶者が取得すると特例を使えるから一安心です。
(2) 配偶者がいない場合でも、同居の法定相続人がいればその人が相続すると使えます。
(3) 配偶者がいない場合に、同居している人が法定相続人以外の親族ならば、自宅の敷地をその親族に遺贈すると使えるようになります(法定相続人ではない親族に取得してもらうためには、遺言をしたためておくことが必要です。)。
(4) 問題は、現在、お一人住まいの方の場合です。このケースでも、自宅の敷地が被相続人の所有であった場合は、相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者が所有している家屋に居住したことがない人が相続又は遺贈により取得すると特例が使えます。
※お一人で住んでいる方は、自宅を持たない子ども(法定相続人)がいるかを確認しておくことが重要です。もし子ども(法定相続人)全員が自宅を所有している場合には、なんらかの対策を考える余地があります。
2 特例の整理
自宅の80%減額特例は複雑なので、教科書的に要件を整理してみましょう。
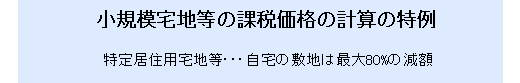
【 被相続人の自宅の場合 】
被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、配偶者や同居の親族などが相続等により取得した場合、その宅地等の評価額を80%減額することができます。
特例を適用できる面積は、最大で330㎡(平成26年までに相続が開始した場合は240㎡)までとなっています。
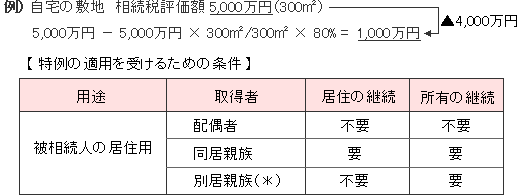
*別居親族については、
(1) 配偶者も同居の法定相続人もいない場合に、
(2) 相続開始前3年以内に持ち家に居住していない者が取得する場合に限られます。
持ち家とは、日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋をいい、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。なお、その親族が日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有しない場合はこの特例の適用はありません。
法定相続人とは、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人です。
居住継続と所有継続の期間は、原則として、ともに相続税の申告期限までです。
3 相続又は遺贈で取得した亡くなられた方の自宅の敷地を売却する場合の注意点
被相続人のご自宅を取得されたのが、配偶者ならば、すぐに売ってしまっても80%減額特例を受けることが可能です。ところが、同居の親族、たとえば同居していた長女が相続した場合には、亡くなられてから10か月を超える日まで、売却してはいけないだけでなく、転居してもいけないのです。うっかり売ってしまったというだけでなく、うっかり引越してしまったということもないように、気を付けましょう。
4 老人ホームに入居しているCさんの場合
これまでにお話ししたケースは、いずれも被相続人の生活の本拠地が自宅の不動産であると言える場合です。亡くなられた方の知人や友人にお尋ねすると、「ああ、彼は亡くなる直前まであの家に住んでいたよ!」という答えが返ってくる場合です。
では、老人ホームで亡くなられた場合はどうでしょうか。老人ホームに入居するときに、それまで住んでいた自宅を売ってしまっている場合は、当然のことながら、遺産の中に「自宅の敷地といえる不動産があるか」ということを検討する余地はないのですが、「老人ホームに入居する直前まで住んでいた自宅を空き家のまま所有して亡くなった場合」は、ちょっと複雑です。
Cさん(88)は都市部に自宅甲(土地建物)を所有していましたが、奥さんに先立たれ一人住まいになりました。彼は、まだまだ元気でなに不自由なく暮らしていたのですが、男所帯ではなにかと不便なので、老人ホームに引っ越しました。数年が経過したある朝、老人ホームの一室で永眠しているのを隣部屋の知人が見つけました。自宅甲はCさんが老人ホームに転居後、引き続き空き家でした。
自宅甲の敷地は80%減額特例の対象になるでしょうか。
次の二つの要件を満たしていると、自宅甲は80%減額対象となります。
(1) Cさんが亡くなった時に要介護認定などを受けていたこと。
(2) 自宅甲は、他の用途に転用されたり、新たに入居した人がいないこと。
(注:上の二要件は、平成26年1月1日以降に相続が開始した場合の基準です。)
この要件に照らし合わせると「前の晩まであんなに元気だったのに」と老人ホームの方が嘆かれるようなケースならば、自宅甲の土地は、80%減額特例の対象にならないのです。
亡くなる直前に介護が全く不要であった場合は、自宅甲の土地は、80%減額の対象とならず、亡くなる直前に介護が必要な状態にあったなら、自宅甲の土地は、80%減額の対象となるのです。
不思議な法律です。ある程度財産を持ち、元気な状態で老人ホームに入居され、拙文をご覧いただいている方がいらっしゃったら、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談してみるのも一つの方法かもしれません。
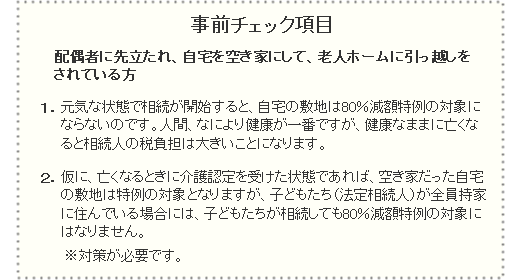
次回は、地価の高い地域で開業医を営んでいるドクターDのお話しです。
田中 耕司Kouji Tanaka税理士
JTMI税理士法人日本税務総研 https://tax365management.com/
JTMI税理士法人日本税務総研/相続支援ナビ https://souzoku.jtmi.jp/taxprime/
税理士法人日本税務総研 代表 大阪国税局・国税不服審判所、住友信託銀行(現三井住友信託銀行)勤務を経て、平成17年より現職。上場企業や中小企業の会計実務、不服審査実務にも通じた資産税の専門家。著書に『相続・贈与・遺贈の税務』(中央経済社)他。







