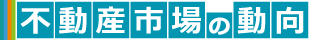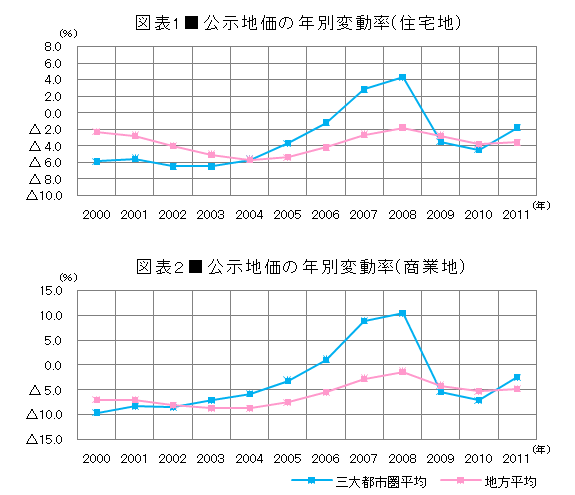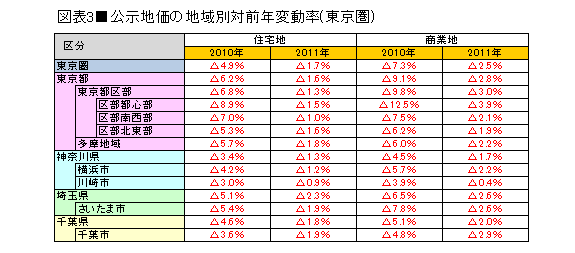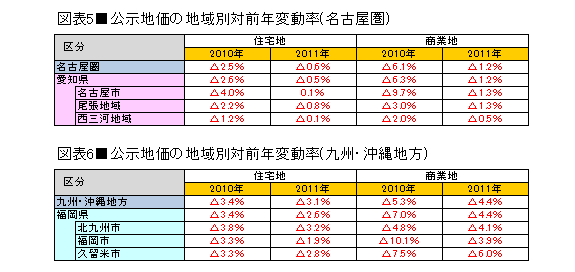公示地価から見通す2011年の不動産市況
大都市圏では下落幅が大きく縮小 下落が続く地方圏との差が開く傾向
国土交通省から発表された2011年の公示地価(用語解説参照)をみると、大都市圏と地方圏との差が広がっていることが分かります。三大都市圏の平均では住宅地が前年比マイナス1.8%と、昨年の同マイナス4.5%から下落幅が大きく縮小しました。商業地も同様の結果となっています。これに対し、地方平均は住宅地が昨年の同マイナス3.8%から今年は同マイナス3.6%へと、下落幅はわずかな縮小でした。商業地も下落幅の縮小は0.5ポイントにとどまっています。(図表1・2)
2008年秋のリーマン・ショック以降、地価の下落が続くなかで、大都市圏、とりわけ住宅地で地価が下落基調から転換する動きが見られるようです。同省では「住宅ローン減税・低金利・贈与税非課税枠拡大等の政策効果(用語解説参照)や住宅の値ごろ感の醸成により、住宅地の需要が高まった」ことが背景にあるとみています。
大都市圏と地方圏とで異なる動きになっている点について、東京カンテイ市場調査部上席主任研究員の中山登志朗氏は次のように分析しています。
「土地の利用価値の高いエリアは地価の下落幅が縮小し、そうでないエリアは下落が続いているということでしょう。利用価値が高いとは利便性が高いということでもあり、それは賃料の高さに現れます。賃料の高いエリアは人気が高く、住んでみたいと思う人が多いので、地価の上昇を見込んだ投資的な動きも反映されやすいといえます」
(図表1、図表2)
東京圏は住宅地に上昇地点が続出 商業地ではスカイツリー効果も
エリア別に公示地価の動きをみていきましょう。まず東京圏は全体で住宅地が前年比マイナス1.7%、商業地が同マイナス2.5%と、いずれも昨年に比べて大幅に下落幅が縮小しました。昨年は下落幅が大きかった東京都の区部都心部や区部南西部でも、今年は住宅地が1%台の下落率となっています。特に中央区は全体として同プラス3.5%と上昇に転じているなど、23区の住宅地では11地点が上昇しており、いずれも中央区と港区に分布しています。「中央区は月島・勝どき地区に超高層マンションが2棟完成しており、マンション市況回復の象徴的な地域。港区の白金・高輪地区は地価下落による値ごろ感から需要の回復が見られる」と、国土交通省では指摘しています。
また多摩地区でも、武蔵野市や府中市では下落幅が0.9%と1%を切りました。神奈川県では武蔵小杉駅前再開発の進む川崎市中原区で0.1%の上昇となるなど、川崎市と横浜市の18地点で地価が上昇に転じています。このほか埼玉県さいたま市で1地点、千葉県市川市と浦安市で各19地点ずつ、同じく成田市と鎌ヶ谷市で各1地点ずつ、それぞれ地価が上昇しました。
一方、商業地では東京都足立区と墨田区で1地点ずつ上昇に転じています。足立区は大学のキャンパス移転が予定されている北千住駅前が、墨田区はスカイツリー効果で観光客が増加した押上駅前が、それぞれ上昇地点です。ほかに駅前の大型商業施設が好調な川崎駅周辺など、川崎市内でも6地点が上昇に転じました。(図表3)
「都区部では需要が回復しつつあるマンションの開発が活発化していることが、市況を牽引しています。利便性が高く開発に適した広い土地は競争入札で価格が押し上げられ、周辺の地価にも波及する形です。ただし、湾岸エリアなどでは地震による液状化の影響を受けており、今後は安全性に対するニーズが高まることも予測されます。また都心部でも南青山地区など投資需要が強かった一部のエリアは、海外の投資家などがまだ市場に戻っていないこともあり、地価の下落に歯止めがかかっていない状況です」(中山氏)
また多摩地区でも、武蔵野市や府中市では下落幅が0.9%と1%を切りました。神奈川県では武蔵小杉駅前再開発の進む川崎市中原区で0.1%の上昇となるなど、川崎市と横浜市の18地点で地価が上昇に転じています。このほか埼玉県さいたま市で1地点、千葉県市川市と浦安市で各19地点ずつ、同じく成田市と鎌ヶ谷市で各1地点ずつ、それぞれ地価が上昇しました。
一方、商業地では東京都足立区と墨田区で1地点ずつ上昇に転じています。足立区は大学のキャンパス移転が予定されている北千住駅前が、墨田区はスカイツリー効果で観光客が増加した押上駅前が、それぞれ上昇地点です。ほかに駅前の大型商業施設が好調な川崎駅周辺など、川崎市内でも6地点が上昇に転じました。(図表3)
「都区部では需要が回復しつつあるマンションの開発が活発化していることが、市況を牽引しています。利便性が高く開発に適した広い土地は競争入札で価格が押し上げられ、周辺の地価にも波及する形です。ただし、湾岸エリアなどでは地震による液状化の影響を受けており、今後は安全性に対するニーズが高まることも予測されます。また都心部でも南青山地区など投資需要が強かった一部のエリアは、海外の投資家などがまだ市場に戻っていないこともあり、地価の下落に歯止めがかかっていない状況です」(中山氏)
下落傾向が鈍化しつつある大阪圏 中心部や住宅地で下げ止まりの動き
大阪圏は住宅地が前年比マイナス2.4%と、2%台の下落率となっている地区が目立ちますが、大阪市中心6区や神戸市などでは下落幅が1%台に縮小しています。大阪府の住宅地で地価が上昇に転じた地点はありませんが、福島区では「都心近接の優位性を背景に、マンションについても成約率・成約単価の回復が見られる」(同省)ことから、地価が0.0%と横ばいとなっています。また兵庫県では根強い住宅需要のある西宮市で同マイナス1.7%と、下落幅が昨年のマイナス5.9%から大幅に縮小しました。芦屋市では全線開通した山手幹線の周辺で2地点が上昇に転じています。(図表4)
一方、商業地は大阪圏全体で同マイナス3.6%と、前年より下落幅が大幅に縮小したものの、住宅地と比べると下落傾向は依然として続いているようです。そんななか、京都市では中京区や下京区、東山区といった高度商業地を中心に6地点が上昇に転じました。「教育環境の良い京都市中心部では商業地でも住宅需要が根強く、マンションの販売価格は上昇局面にある」(同省)とのことです。
「大阪圏では住宅地の下落傾向が鈍化しつつありますが、全体としてはまだ下げ止まったとはいえない状況です。横ばいから上昇に転じつつあるのは、大阪市中心部のタワーマンションの分譲が活発なエリアや、住宅需要の根強い阪神間や北摂エリアの一部にとどまっています。また梅田北ヤードの再開発が進む大阪駅周辺は昨年は2ケタの下落率となりましたが、計画の進捗に伴って復調の兆しも見えてきました」(中山氏)
一方、商業地は大阪圏全体で同マイナス3.6%と、前年より下落幅が大幅に縮小したものの、住宅地と比べると下落傾向は依然として続いているようです。そんななか、京都市では中京区や下京区、東山区といった高度商業地を中心に6地点が上昇に転じました。「教育環境の良い京都市中心部では商業地でも住宅需要が根強く、マンションの販売価格は上昇局面にある」(同省)とのことです。
「大阪圏では住宅地の下落傾向が鈍化しつつありますが、全体としてはまだ下げ止まったとはいえない状況です。横ばいから上昇に転じつつあるのは、大阪市中心部のタワーマンションの分譲が活発なエリアや、住宅需要の根強い阪神間や北摂エリアの一部にとどまっています。また梅田北ヤードの再開発が進む大阪駅周辺は昨年は2ケタの下落率となりましたが、計画の進捗に伴って復調の兆しも見えてきました」(中山氏)
名古屋圏の住宅地はほぼ横ばい 新幹線開業に沸く九州エリア
大都市圏の中でも地価下げ止まりの傾向が顕著にみられるのが名古屋圏です。住宅地全体では前年比マイナス0.6%とほぼ横ばい圏となっており、名古屋市では同プラス0.1%の上昇に転じています。名古屋市の住宅地では「戸建を中心にデベロッパーの用地取得が積極的となり」(同省)、30地点で上昇しました。そのうち19地点が、地下鉄や国道302号などインフラ整備が進んだ緑区です。また西三河地区も堅調で、刈谷市で18地点、安城市で13地点が上昇しています。(図表5)
「名古屋市では東部の住宅地エリアで地価が下げ止まりから上昇に転じています。特に地下鉄桜通線の延伸効果で住宅地開発が進み、地価を下支えしました。地下鉄の延伸は商業地の地価にも影響しており、下落幅の縮小や反転上昇の動きが見られます」(中山氏)
このほか特徴的な動きとなっているのが福岡県です。県全体の住宅地の下落率は昨年のマイナス3.4%から今年はマイナス2.6%に低下し、福岡市はマイナス1.9%とさらに下落幅が小さくなっています。「市中心部及びその隣接区において、戸建住宅、マンションの需要が徐々に回復傾向にある」というのが同省の見方です。また同市博多地区では商業地の下落率が昨年のマイナス13.9%からマイナス2.6%に大幅に低下しました。今年3月の九州新幹線全線開業に伴い、新博多駅ビルが開業するなど発展が期待されています。(図表6)
「九州新幹線では終着の鹿児島中央駅周辺でも、商業地で上昇地点が出ています。東南アジアや中国・韓国からの観光客も活発に流入しており、沿線のターミナル駅周辺では今後も地価は下げ止まりから上昇への動きが続くでしょう」(中山氏)
「名古屋市では東部の住宅地エリアで地価が下げ止まりから上昇に転じています。特に地下鉄桜通線の延伸効果で住宅地開発が進み、地価を下支えしました。地下鉄の延伸は商業地の地価にも影響しており、下落幅の縮小や反転上昇の動きが見られます」(中山氏)
このほか特徴的な動きとなっているのが福岡県です。県全体の住宅地の下落率は昨年のマイナス3.4%から今年はマイナス2.6%に低下し、福岡市はマイナス1.9%とさらに下落幅が小さくなっています。「市中心部及びその隣接区において、戸建住宅、マンションの需要が徐々に回復傾向にある」というのが同省の見方です。また同市博多地区では商業地の下落率が昨年のマイナス13.9%からマイナス2.6%に大幅に低下しました。今年3月の九州新幹線全線開業に伴い、新博多駅ビルが開業するなど発展が期待されています。(図表6)
「九州新幹線では終着の鹿児島中央駅周辺でも、商業地で上昇地点が出ています。東南アジアや中国・韓国からの観光客も活発に流入しており、沿線のターミナル駅周辺では今後も地価は下げ止まりから上昇への動きが続くでしょう」(中山氏)
こうしてみると、大都市圏の中心部やその周辺の住宅地、さらに一部地方のターミナル駅周辺などでは、不動産売買の活性化とともに地価が反転上昇する動きが強まりそうです。「震災の影響は不透明な面もありますが、減税や低金利などの後押しは引き続き期待できます。立地条件が良く、値ごろ感の強まったマンションや一戸建ての購入に適した状況が、2011年後半も続くと考えられるでしょう」と、中山氏も予測しています。
用語解説
●公示地価
- 全国の不動産鑑定士が毎年、標準的な土地(標準地)の1月1日時点の地価を調べ、国土交通省が取りまとめて発表しているもの。官民の不動産取引の指標として広く活用されている。今回は全国で2万6000地点の標準地が対象となった。
●政策効果
- 現在導入されている代表的な住宅政策としては、10年間にわたり最大400万円の税控除が受けられる住宅ローン減税、親や祖父母からの住宅資金援助が1000万円まで非課税となる贈与税の特例、一定基準を満たす住宅を対象にフラット35の当初10年間の金利が1%引き下げられるフラット35Sが挙げられる。このほか今年の年末までに着工した住宅を対象に、30万円相当のポイントが交付される住宅エコポイントも実施中だ
(データ提供:東京カンテイ)
※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。