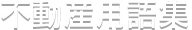場合により「違法建築物」とも言われる。
関連法規や条例およびそれに基づく許可等の条件等に違反している建築物を指すが、特に建築基準法の法目的が、同法第1条に掲げられているように、建築物に関する「最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護」を図ることであることからして、違反に対しては、厳しい措置が定められている。
建築基準法は、個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する安全確保のための技術基準として建築基準法の第2章(第19条~第41条)に置かれている規定(単体規定)と、建築物の集団であるまちや都市において要求される安全かつ合理的な土地利用、環境の向上のために建築物の秩序を確保するための基準として同法の第3章(第41条の2~第68条の26)に置かれている規定(集団規定)があるが、これらの規定に違反するものは、いずれも建築基準法違反という意味での違反建築物となる。
特定行政庁は、建築基準法令等に違反した建築物の建築主、工事の請負人、現場管理者、または建築物もしくは建築物の敷地の所有者、管理者、占有者に対して、工事の施工の停止のほか、除却、移転、増改築、修繕、使用禁止等の必要な是正措置を命ずることができる(同法第9条第1項)。是正措置が履行されない場合には、行政代執行の対象となる(同条第12項)が、その場合にも、特則により、より速やかな代執行や是正が可能である。
なお、建築後に建築基準法令等が改正され、新しい法規に適合しなくなった場合や、都市計画上の区域が変更されたために規制に適合しなくなった場合は、経過措置として建築物の存続を許される(既存不適格建築物、同法第3条第2項)。しかし、この場合でも、改築・増築や移転等の際には、全面的に改正後の建築基準法令等が適用されるほか、損傷、腐食等により放置すれば保安上危険である場合や、衛生上有害となる場合および公益上著しく支障がある場合には、指導、助言および勧告、さらには命令がなされる場合があり(同法第9条の4、第10条および第11条)、最終的には違反の是正が求められる。
そのほか、消防法の規定に違反する場合も、違反建築物とされる場合がある。
消防法施行令では、病院、学校、劇場、ホテル、飲食店、事務所、地下街等の主に不特定多数の人が出入りする施設を「防火対象物」と位置付け、これらに対し、必要な内装や設備について定めている。これらの規定に違反した場合には、消防署長等による指導や是正命令の対象となるほか、命令に違反したり、違反状態を放置して火災による死傷者が出た場合には、刑事事件として捜査され重い罰則が課せられるほか、民事上も損害賠償の対象となる。
宅地建物取引業法第47条第1号では、宅地建物取引業者が、業務に関して重要な事実について故意にこれを告げず、または不実のことを告げる行為を禁止している。また、建築基準法第9条の3は、当該違反建築物の設計者や工事請負人等と並んで、宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者についても、特定行政庁に当該業者を監督する国土交通大臣または都道府県知事に通報することを義務付けており、通報を受けた大臣および知事は、免許の取消し、業務の停止処分その他必要な措置を講ずるものとされ、違反建築物の取引への関与については、重い処分が用意されている。
違法建築物
建築基準法をはじめとする関連法規に違反している建築物をいう。具体的にある法律の特定の条項に違反しているという意味では、「違反建築物」の方が正確な用語であると思われ、法律における用語(例えば建築基準法第9条見出し)や、行政機関等の使用例ではむしろ「違反建築物」の方が一般的である。
一方で、正確に違反条項を明らかにせずに建築物の違法性を問題にする場合などには、「違法建築物」との用語が用いられることもある。
特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できる。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求めることができる。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。 遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。 その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
単体規定(建築基準法における~)
個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する安全確保のための技術基準として建築基準法の第2章(第19条~第41条)に置かれている規定。
「構造強度」「採光、通風」「防火、避難」「室内空気環境」その他の安全性など、多様な観点から建築物の安全性について仕様または性能面で遵守すべき技術基準を定めている。具体的な技術基準や設計の安全性等を確認・検証するための数値の計算方法についての多くは、国土交通大臣の定める告示に委任されている。
集団規定(建築基準法における~)
建築物の集団であるまちや都市において要求される安全かつ合理的な土地利用、環境の向上のために建築物の秩序を確保するための基準として建築基準法の第3章(第41条の2~第68条の26)に置かれている規定。
建築物の敷地と道路との関係、用途制限および形態制限を柱として、市街地の整備改善に資する建築規制により構成されている。集団規定の適用範囲は、都市計画区域または準都市計画区域に限定される。
特定行政庁
建築基準行政において、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長を、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。 人口が25万人以上の市の市長は原則として特定行政庁であるほか、それ以外の市町村長も建築主事を置くことによって特定行政庁となる。 建築主事は建築確認等の業務を行なうが、違反建築物に対する措置等は特定行政庁の業務とされている。
敷地
建築物のある土地のことを「敷地」という。
なお、同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。 例えば、ある人の所有地の上に「住宅」と「物置」が別々に建っている場合は、この2つは用途上不可分であるので、別々の敷地上に建てたと主張することはできない、ということである。
ところで、建築基準法では「敷地」が衛生的で安全であるように、次のようなルールを設定しているので注意したい(建築基準法19条)。
1.敷地は、道より高くなければならない(ただし排水や防湿の措置を取れば可) 2.敷地が、湿潤な土地や出水の多い土地であるときは、盛り土や地盤の改良を行なう。 3.敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組み(下水道など)をしなければならない。 4.崖崩れの被害にあう恐れがあるときは、擁壁(ようへき)の設置などをしなければならない。
管理者
管理者とは、分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者全員の代表者として、建物および敷地等の管理を実行する者のことである。
通常の場合、管理組合の理事長がこの「管理者」である。マンション管理会社はここでいう「管理者」ではない(ただし管理者は必ずしも管理組合の理事長である必要はなく、区分所有者以外の第三者でもよい)。
管理者は、通常の場合、管理規約の定めに従って、管理組合の理事会において、理事の互選により選ばれる(ただし区分所有法(第25条)上は別の選任方法でもよい)。
管理者は、区分所有者全員の代表者として、集会で決議された事項を実行し、また管理規約において与えられた職務権限を行使することができる(区分所有法第26条)。
管理者の職務としては次のものを挙げることができる。
1.集会(管理組合の総会)の招集・議事運営・議事録作成 (区分所有法第34条・第41条・第42条)
2.管理規約の保管と閲覧への対応(区分所有法第33条)
3.義務違反者に対する訴訟の提起(区分所有法第57条から第60条)
4.そのほか管理規約・使用細則で管理者の職務とされた事項(理事会の運営・日常的な業務の執行など)
都市計画
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。
具体的には都市計画とは次の1.から11.のことである。
1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2.都市再開発方針等(同法第7条の2)
3.区域区分(同法第7条)
4.地域地区(同法第8条)
5.促進区域(同法第10条の2)
6.遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7.被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8.都市施設(同法第11条)
9.市街地開発事業(同法第12条)
10.市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11.地区計画等(同法第12条の4)
注:
・上記1.から11.の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8.の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。
・上記4.の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
・上記1.から11.の都市計画は都道府県または市町村が定める(詳しくは都市計画の決定主体へ)。
既存不適格建築物
事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物のこと。
建築基準法第3条第2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点ですでに工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないという特例を設けている。 この規定により、事実上違法な状態であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼んでいる。 なお既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要がある。
また、建築基準法第10条では、特定行政庁は、既存不適格建築物であっても、それが著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認められる場合には、相当の猶予期限を設けて、所有者等に建築物の除却等を命令することができるとされている。この規定により特定行政庁の権限において、著しく老朽化した既存不適格建築物を撤去すること等が可能となっている。
消防法
火災の予防・警戒・鎮圧や、火災等の災害を軽減するために必要な措置を定めた法律。1948(昭和23)年に制定された。
消防法が定める火災予防のための主な措置は、(1)消防機関による立入検査、措置命令等、(2)住宅用火災警報器の設置・維持、(3)一定の建物における防火管理者の選任、消防計画の作成・届出、訓練の実施等、(4)一定の建物についての消火設備、警報設備、避難設備等の設置・維持、(5)一定の防炎品の検定等である。また、消火活動のために消防機関が即時に強制できる権限(緊急通行、土地や水利の使用、立入制限等)なども定められている。
なお、火災予防のためには、消防法のほか、建築基準法による措置が重要である。
宅地建物取引業法
宅地建物取引の営業に関して、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を定めた法律。1952年に制定された。
この法律に定められている主な内容は、宅地建物取引を営業する者に対する免許制度のほか、宅地建物取引士制度、営業保証金制度、業務を実施する場合の禁止・遵守事項などである。これによって、宅地建物取引業務の適正な運営、宅地および建物の取引の公正の確保および宅地建物取引業の健全な発達の促進を図ることとされている。
宅地建物取引業者
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。
宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。
宅地建物取引業
宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行なう」ことである(法第2条第2号)。 ここで「宅地建物の取引」と「業として行なう」とは具体的には次の意味である。 1.「宅地建物の取引」とは次の1)および2)を指している。 1)宅地建物の売買・交換 2)宅地建物の売買・交換・貸借の媒介・代理 上記1.の1)では「宅地建物の貸借」が除外されている。このため、自ら貸主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されているので、宅地建物取引業の免許を取得する必要がない。 またここでいう「宅地」とは、宅地建物取引業法上の宅地を指す(詳しくは「宅地(宅地建物取引業法における~)」を参照のこと)。 2.「業として行なう」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行と見ることができる程度に行なう状態」を指す。具体的な判断基準は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の「第2条第2号関係」に記載されているが、主な考え方は次のとおりである。 1)取引の対象者 広く一般の者を対象に取引を行なおうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。 2)取引の反復継続性 反復継続的に取引を行なおうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行なおうとするものは事業性が低い。
関連用語
-
違法建築物


-
建築基準法をはじめとする関連法規に違反している建築物をいう。具体的にある法律の特定の条項に違反しているという意味では、「違反建築物」の方が正確な用語であると思われ、法律における用語(例えば建築基準法第9条見出し)や、行政機関等の使用例ではむしろ「違反建築物」の方が一般的である。
一方で、正確に違反条項を明らかにせずに建築物の違法性を問題にする場合などには、「違法建築物」との用語が用いられることもある。
特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できる。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求めることができる。
-
建築物


-
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。