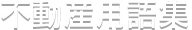剛性とは外力に対する変形のしにくさを表しており、建築基準法における「許容応力度計算」では、多層階を有する建築物において、各階ごとに剛性が違えば、剛性が低い(変形しやすい)階の変形が大きくなり、この階に損傷が集中することによって、建築物の破損や倒壊に結び付きやすくなることから、各階ごとの剛性ができるだけ均等であることを求めている。
このため、各階の剛性の平均値に対する当該階の剛性の割合(層間変形角の数値の逆数の、全階にわたる平均値に対する当該階の値の比)を剛性率とし、それができるだけ各階において平均値に近く(剛性率=1に近づけるのが理想)、各階ごとの剛性率のばらつきがないよう、「各階の剛性率がそれぞれ10分の6以上であること」と定めている(同法施行令第82条の6)。
外力
建築物や構造物の躯体の外部からかかる力。具体的には地震動、風圧、積雪による荷重など。
建築基準法施行令第83条第1項では、「建築物に作用する荷重及び外力」として、「固定荷重」「積載荷重」「積雪荷重」「風圧力」「地震力」を掲げ、さらに同条第2項で「建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない」としている。荷重と外力については、ほぼ同じものであると認識されていると考えられるが、例えば、建築物自体やその部分の重量に起因すると見られる固定荷重や積載荷重については、「外力」というよりは「荷重」の方がふさわしいと考えられる。一方、建築物を構成する各材料の立場からは、外力=荷重としてほぼ同一視される。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。 遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。 その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
道路(建築基準法上の~)
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。 ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。
1.建築基準法第42条第1項の道路 建築基準法第42条第1項では次の1)~3)を「道路」と定義している。 この1)~3)の道路はすべて幅が4m以上である。 1)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路 2)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道 3)特定行政庁から指定を受けた私道 2.建築基準法第42条第2項の道路 建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。
このように建築基準法では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても一定の要件をみたせば道路となり得ることとしている。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。