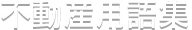建築物の建築等に関する申請および確認について定めた、建築基準法第6条第1項および構造耐力について定めた第20条第1項は、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により抜本的に改正された。これにより、高さ60m以下の建築物のうち、平屋かつ延面積200平方メートル以下の建築物以外の建築物(一定規模以上の建築物)は、構造によらず、また、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等内であるかこれらの区域外であるかに関わらず、構造規定および省エネ基準の審査が必要になった。具体的には、木造2階建て住宅や木造の200平方メートル超の平屋建て住宅について、新制度では、構造関係規定等の図書や省エネ関連の図書が必要となる。これらの小規模な建築物は、改正前の同項第4号に該当するため、「4号物件」と呼ばれ、確認申請書の図書の一部の提出が省略可能であった(「4号特例」)が、改正法により省略は認められなくなった。
改正法は2025(令和7)年4月より施行されている。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。 遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。 その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
構造耐力
建築物には、自重(建築物そのものの重さ)、積載荷重(人間・家具・設備の重さ)、積雪という垂直方向の力がかかり、また地震力・風圧力という水平方向の力がかかる。 これらの垂直方向・水平方向の力に対して、建築物が垂直方向の力を支え、水平方向の力による変形に対抗することができるということを「構造耐力」と呼んでいる。 また、特に水平方向の力による変形に対抗することができるということを「水平耐力」と呼んでいる。 この水平耐力を備えるように筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁は「耐力壁」と呼ばれている。 建築基準法では、すべての建築物が十分な構造耐力を備えるように、詳しい技術的な基準を設けている(建築基準法第20条第1項、建築基準法施行令第36条から第80条の3まで)。 また、木造3階建てなどの建築物については十分な構造耐力を持つことをチェックするために、設計段階で構造計算を行なうことを義務付けている(建築基準法第20条第1項第2号、建築基準法施行令第81条から第99条まで)。
平屋(フラットハウス)
地上階層が1階だけの建物。フラットハウスは和製英語で、英語ではone-storied building(ワン ストーリード ビルディング)、one-story house(ワン ストーリー ハウス)などという。
都市計画区域
原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域。 原則として都道府県が指定する。
1.都市計画区域の指定の要件 都市計画区域は次の2種類のケースにおいて指定される(都市計画法第5条第1項、第2項)。 1)市または一定要件を満たす町村の中心市街地を含み、自然条件、社会的条件等を勘案して一体の都市として総合的に整備開発保全する必要がある場合 2)新たに住居都市、工業都市その他都市として開発保全する必要がある区域 1)は、すでに市町村に中心市街地が形成されている場合に、その市町村の中心市街地を含んで一体的に整備・開発・保全すべき区域を「都市計画区域」として指定するものである(※1)。なお、1)の「一定要件を満たす町村」については都市計画法施行令第2条で「原則として町村の人口が1万人以上」などの要件が定められている。 2)は、新規に住居都市・工業都市などを建設する場合を指している。 (※1)都市計画区域は、必要があるときは市町村の区域を越えて指定することができる(都市計画法第5条第1項後段)。また、都市計画区域は2以上の都府県にまたがって指定することもできる。この場合には、指定権者が国土交通大臣となる(都市計画法第5条第4項)。 2.都市計画区域の指定の方法 原則として都道府県が指定する(詳しくは都市計画区域の指定へ)。 3.都市計画区域の指定の効果 都市計画区域に指定されると、必要に応じて区域区分が行なわれ(※2)、さまざまな都市計画が決定され、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行される。また開発許可制度が施行されるので、自由な土地造成が制限される。 (※2)区域区分とは、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することである。ただし、区域区分はすべての都市計画区域で行なわれるわけではなく、区域区分がされていない都市計画区域も多数存在する。このような区域区分がされていない都市計画区域は「区域区分が定められていない都市計画区域」と呼ばれる。 4.準都市計画区域について 都市計画区域を指定すべき要件(上記1.の1)または2))を満たしていない土地の区域であっても、将来的に市街化が見込まれる場合には、市町村はその土地の区域を「準都市計画区域」に指定することができる。準都市計画区域では、必要に応じて用途地域などを定めることができ、開発許可制度が施行されるので、無秩序な開発を規制することが可能となる(詳しくは準都市計画区域へ)。
準都市計画区域
都市計画区域外の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域。都道府県が指定する。
1.準都市計画区域の趣旨
都市計画区域を指定するためには一定の要件を満たすことが必要であるが、その要件を満たしていない区域であっても、将来的に市街化が見込まれる場合には、土地利用をあらかじめ規制しておくことが望ましい。その必要に応えるために、2000(平成12)年に創設されたのが「準都市計画区域」の制度である。
2.準都市計画区域の指定の要件
次の要件のすべてを満たす場合に、指定することができる。
1)都市計画区域外の土地であること
2)相当数の住居等の建築・敷地の造成等が現に行なわれ、または行なわれると見込まれること
3)そのまま放置すれば将来における都市としての整備開発保全に支障が生ずる恐れがあること
3.準都市計画区域の指定の方法
都道府県が指定する(指定の手続きについては「準都市計画区域の指定」を参照)。
4.準都市計画区域の指定の効果
準都市計画区域においては、次のような土地利用の規制が適用される。
1)次の地域地区を定めることができる。
「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「特定用途制限地域」「景観地区」「風致地区」「緑地保全地域」「伝統的建造物群保存地区」
2)開発許可制度が適用される。この結果、原則として開発面積が3,000平方メートルを超える宅地造成について都道府県知事(または市長)の許可が必要となる(「開発許可」を参照)。
3)建物等の新築や増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)する場合には、事前に建築確認を受けなけらばならない。この場合には、都市計画区域内と同様の基準が適用される(「建築確認」を参照)。
準景観地区
都市計画区域および準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために指定される区域をいう。
指定は、相当数の建築物の建築が行なわれて現に良好な景観が形成されている一定の区域について、市町村が行なう。また、準景観地区内においては、条例で、建築物または工作物や開発行為等について、一定の規制がなされる。
指定や規制の手続き、基準などは、景観法に規定されている。
省エネ基準
建築物の使用によって消費されるエネルギー量に基づいて性能を評価する場合に、その基準となる性能をいう。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づいて定められている。法令上の用語は「建築物エネルギー消費性能基準」である。 省エネ基準は、(A)一次エネルギー消費量に関する基準、(B)外皮熱性能に関する基準の二つから構成されている。 (A)一次エネルギー消費量に関する基準 すべての建物についての基準で、一定の条件のもとで算出した、空調、照明、換気、給湯等の諸設備のエネルギー消費量および太陽光発電設備等によるエネルギーの創出量 (B)外皮熱性能に関する基準 住宅についての基準で、一定の条件のもとで算出した、外壁や窓の外皮平均熱貫流率(単位外皮面積・単位温度当たりの熱損失量)および冷房期の平均日射熱取得率(単位外皮面積当たりの単位日射強度に対する日射熱取得量の割合)であって、地域の区分に応じて定める (注:非住宅建築物についても外皮熱性能に関する基準が定められているが、これは、建築物省エネ法上の「建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)」とはされていない。) 省エネ基準は、建築物省エネ法による次のような規制、指導、表示などにおいて、その判定、指示、認定等の基準となっている。 (1)適合義務 すべての住宅・非住宅建築物は、新築時等に、一次エネルギー消費量に関する省エネ基準に適合しなければならず、基準不適合の場合には、建築確認を受けることができない。 (2)エネルギー消費性能の表示 建築物の所有者は、その建築物が省エネ基準に適合することの認定を受け、その旨を表示する。 なお、建築物のエネルギー消費性能に関する基準には、省エネ基準のほか、次のものがある。 ア)住宅トップランナー基準 住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅・分譲マンション・賃貸アパートの省エネ性能を誘導する際に適用する基準 イ)誘導基準 省エネ性能向上計画の認定を受けて容積率の特例を受ける際の基準
木造
建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。
木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されている。
関連用語
-
エネルギー消費性能の表示


-
建築物の所有者が、その所有する建築物について、省エネ基準に適合する旨の認定を受け、エネルギー消費性能を表示することをいう。建築物省エネ法に基づく制度で、2016年4月1日から施行。
省エネ性能の表示は、当該建物の設計、一次エネルギー消費量の基準、一次エネルギー消費量からの削減率、両者の関係図、省エネ基準への適合などを記載することによって行なう。BELSはその評価のしくみのひとつである。
-
2号物件


-
かつての建築基準法第20条第1項第2号及び第3号においては、高さ60m以下の建築物のうち、比較的大規模なものを第2号、中規模なものを第3号、小規模なものを第4号に区分。このうち第2号では、
・木造建築物で高さが13m、もしくは軒の高さが9mを超えるもの
・鉄骨造の建築物で地上4階建て以上のもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造で高さが20m超60m以下であるもの
等の建築物について、限界耐力計算または保有水平耐力計算等の構造計算を必要としていた。しかし、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により建築基準法が抜本的に改正され、60m以下の建築物は、新たに「新2号物件」「新3号物件」等に規定され、規制内容が再編成されている。