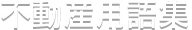民法176条に「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」とあり、不動産取引においても、登記や代金の支払い、物件の引渡しなどの行為はあるとしても、所有権そのものは契約時に移転するという解釈が一般的である。しかし、売主の代金支払請求権を担保したいとの事情などから、所有権移転時期を、代金支払い時や、物件引き渡し時とする特約が結ばれることも行なわれている。
一方、割賦販売法第7条では、割賦販売契約においては、「~全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。」と定められているが、宅地建物取引業法においては、消費者保護の観点から、宅地建物取引業者が売主となる売買について、代金の10分の3を超える額の支払いを受けるまでに登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない等、宅地建物取引業者側の所有権留保を禁じている(宅地建物取引業法第43条)。業者が買主の債務を保証する場合も同様である。
引渡し
物を支配する権能(占有権)を相手に移転すること。売買や賃貸借によって生じる民法上の概念である。現実に占有状態を実現することだけでなく、占有を移転する旨の意思表示も引渡しとされる。 引渡しを受けることは、動産に関する物権譲渡の対抗要件とされている。一方、不動産に関する物権譲渡の対抗要件は登記であって引き渡されることではないが、引渡しを受けることは、譲渡された事実を確定する上で重要な行為である。 建物の引渡しは、通常、鍵を渡すことによって行なわれる。 土地の引渡しは、建物付きであるか更地であるかによって費用の負担や手続きが異なる。たとえば、建物付きの土地を更地で引渡す場合には、引渡し前に、建物を解体し、埋蔵物を確認し、建物の滅失を登記するなどの作業が必要となる。一方、現況での引渡しであればこれらの手続きは不要である。いずれの場合も、引渡しを受けたら占有の事実を示す標識等を設置することが望ましい。
所有権
法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利をいう。
物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。
近代市民社会の成立を支える経済的な基盤の一つは、「所有権の絶対性」であるといわれている。だが逆に、「所有権は義務を負う」とも考えられており、その絶対性は理念的なものに過ぎない。
土地所有権は、法令の制限内においてその上下に及ぶとされている。その一方で、隣接する土地との関係により権利が制限・拡張されることがあり、また、都市計画などの公共の必要による制限を受ける。さらには、私有財産は、正当な補償の下に公共のために用いることが認められており(土地収用はその例である)、これも所有権に対する制約の一つである。
売主
不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。 また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。 この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。
宅地建物取引業法
宅地建物取引の営業に関して、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を定めた法律。1952年に制定された。
この法律に定められている主な内容は、宅地建物取引を営業する者に対する免許制度のほか、宅地建物取引士制度、営業保証金制度、業務を実施する場合の禁止・遵守事項などである。これによって、宅地建物取引業務の適正な運営、宅地および建物の取引の公正の確保および宅地建物取引業の健全な発達の促進を図ることとされている。
宅地建物取引業者
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。
宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。