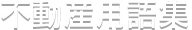宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。
この報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者と宅地建物取引業者の間で約定されるものである。
またこの報酬の額の上限は、宅地建物取引業法第46条に基づき国土交通大臣が告示で定めるものとされており、宅地建物取引業者はその告示の規定を超えて報酬を受けてはならない、という制限がある。
このような宅地建物取引業法の規定を受けて「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号、いわゆる「報酬告示」)が定められている。
報酬額の制限の概要は以下の1~9の通りである。
なお、喫緊の課題とされる空き家等未利用不動産の流通促進のため、「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、令和6(2024)年6月に本報酬告示が改正されたところである。
これまで、低廉な空き家については「400万円以下」とし、「現地調査等に要する費用に相当する額」として、売買等の媒介では「18万円の1.1倍」を上限として受け取ることができるとしていたが、改正告示では、低廉な空家等の対象を「800万円以下」に拡大し、「費用を勘案した報酬」として「30万円の1.1倍」を受け取ることができるとして、上限額を引き上げた。また、「長期の空家等の貸借の媒介」等について、新たに特例を新設した。告示は、令和6年6月国土交通省告示第949号によって改正され、7月1日に施行された。
1.報酬が発生する場合
宅地建物取引業者の媒介または代理により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる。しかし、宅地建物取引業者自らが売主または貸主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売主または貸主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買主または借主に報酬を請求することはできない。
また、この報酬は成功報酬と解釈されており、原則として売買・交換・貸借が媒介または代理により成立した場合にのみ報酬請求権が発生するとされている(標準媒介契約約款の規定等による)。
2.売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次の通りである(報酬告示第二)。
1)売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5%+これに対する消費税額
2)200万円を超え400万円以下の部分について…4%+これに対する消費税額
3)400万円を超える部分について…3%+これに対する消費税額
例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が、1,000万円の場合には、200万円の5%、(200万円から400万円までの)200万円の4%、(400万円から1,000万円までの)600万円の3%に、それぞれに対する消費税額を加えた額である39.6万円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただし、この額には報酬に係る消費税相当額を含む)。
3.交換の媒介における報酬額の上限
交換の媒介の場合には、交換する宅地建物の価額に差があるときは、いずれか高い方を「交換に係る宅地建物の価額(ただし、建物に係る消費税額を除外する)」とする(報酬告示第二)。
例えば、A社がX氏と媒介契約を結んでX氏所有の800万円(消費税額を除外後)の宅地建物を媒介し、B社がY氏と媒介契約を結んでY氏所有の1,000万円(消費税額を除外後)の宅地建物を媒介して交換が成立したとすれば、A社の報酬額の上限は800万円でなく、1,000万円をもとに計算する。(ただし、この額には報酬に係る消費税相当額を含む)。
4.貸借の媒介の場合
宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者双方から受けることのできる報酬の上限は、合計で借賃(借賃に係る消費税額を除外する)の1月分+これに対する消費税額である(この額には報酬に係る消費税相当額を含む)。ただし、居住の用に供する建物の賃貸借については、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬は、媒介依頼の際に当該依頼者の承諾を得ている場合を除いて、借賃の1月分の0.5倍+これに対する消費税額以内でなければならない(報酬告示第四)。
なお、宅地または非居住用の建物(店舗・事務所など)の賃貸借において、権利金が授受されるときは、その権利金の額を上記2.の「売買に係る代金の額」とみなして、売買の媒介の場合と同様に報酬額の上限を算出することが可能である(報酬告示第六)。
5.代理の場合
売買・交換の代理において、宅地建物取引業者が依頼者から受けることのできる報酬額の上限は、上記2.3.の2倍である(報酬告示第三)。ただし、宅地建物取引業者が取引の相手方からも報酬を受ける場合には、その報酬額と代理の依頼者から受ける報酬額の合計額も上記2.3.の2倍以内に収まらなければならない。
賃借の代理においては、依頼者から受け取ることのできる報酬額の上限は借賃の1月分+これに対する消費税額であり、取引の相手方からも媒介等の報酬を得る場合には、両者からの報酬の合計額はこの額を超えてはならない(報酬告示第五)。
なお、双方代理は、民法で原則として禁止されていることに注意が必要である。
6. 低廉な空家等の売買・交換に関する特例
代金の額が800万円以下の宅地建物(低廉な空家等)の取引の媒介に当たっては、依頼者たる売主または交換を行う者から受ける報酬について、当該媒介に要する費用を勘案して上記2.3.の原則を超えて報酬を受けることができる。ただし、報酬額は30万円+これに対する消費税額を超えてはならない。(報酬告示第七)。
また、代理に当たって依頼者から受ける報酬の額(当該売買又は交換の相手方からも報酬を受ける場合には、それも含めた合計額)は、上記の2倍を超えてはならない。(報酬告示第八)
7. 長期の空家等の貸借に関する特例
現に長期間にわたって居住の用、事業の用などに供されておらず、又は将来にわたって利用されることが困難とみられる宅地建物(長期の空家等)の貸借の媒介に関して受けることのできる報酬額の合計額は、借主から受ける報酬の額が借賃の1ヵ月分の1.1倍(居住の用に供する場合は借主の承諾を得ている場合を除き0.55倍)に相当する金額以内である場合に限り、1ヵ月分の2.2倍を超えない範囲で報酬を受けることができる(報酬告示第九)。
また、長期の空家等の貸借の代理の場合には、依頼者である貸主から受けることのできる報酬額は、借賃の1ヵ月分の2.2倍以内である。貸借の相手方からも報酬を受ける場合には、その報酬額と代理の依頼者から受ける報酬額の合計額(借主から受ける報酬額が借り賃の1ヵ月分の1.1倍以内である場合に限る)も同様に1ヵ月分の2.2倍を超えてはならない。
8.複数の宅地建物取引業者の関与
9. 特別の依頼に係る広告費用
宅地建物の売買・交換・貸借の媒介・代理に関しては、上記の1〜8によるほか報酬を受け取ってはならないが、依頼者が特別に依頼した広告の料金に相当する額については、この限りではない(報酬告示第十一)。
10. 媒介業務以外の不動産取引に関連する業務に係る報酬について
空き家・空き室等の所有者等のニーズに対応して行う業務またはいわゆる不動産コンサルティング業務など、媒介以外の関連業務を行う場合には、媒介業務に係る報酬とは別に当該媒介以外の関連業務に係る報酬を受けることができるが、この場合にも、あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど、報酬額の明確化を図ること。