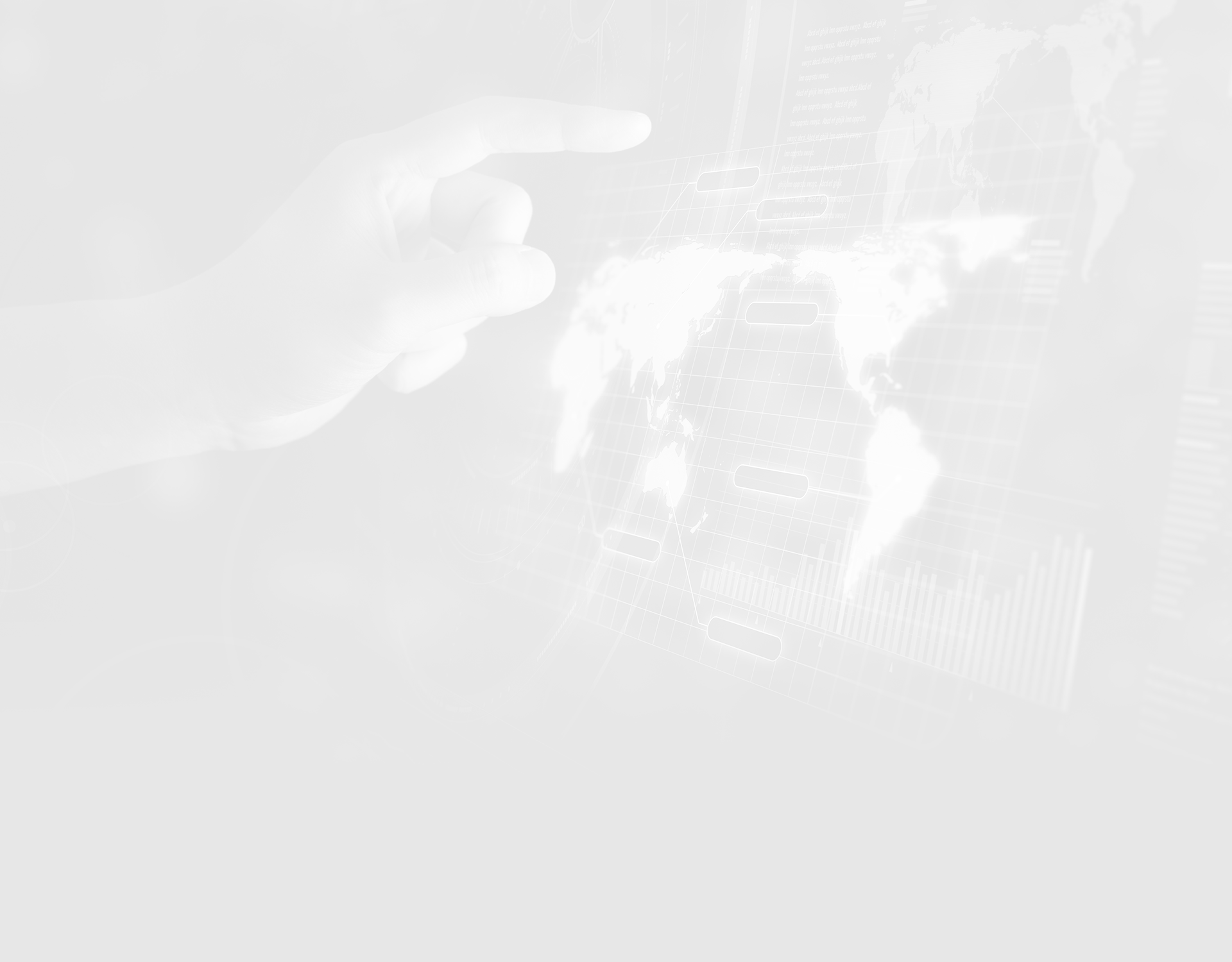家庭を持つ現地人の持ち家率は9割!
その理由は……?

「大人未来ラボ」シーズン3の第2回目では、各国の住宅事情をレポート。過去2シーズン同様、日本では想像もつかないようなルールやシステムがあるのでしょうか? ヨーロッパ、北米、南米、南アジア、東アジア、東南アジアの7カ国にお住いの皆さんに聞いてみました。
国民の「持ち家率」が9割を超える国は?
最初に、皆さんのお住いの国・地域における世帯ごとの「持ち家と貸家の比率」について、公的な数値や感覚値でお答えいただきました。
持ち家率が70%~それ以上と回答があった国は、スペイン、シンガポール、台湾です。
「HDB制度があるため、ローカル(現地人)の持ち家率は9割を超えるともいわれています。外国人の場合は、不動産を購入するには多くの条件をクリアしなければならないので、ほとんどが賃貸です(シンガポール)
HDBとは、Housing & Development Boardの略で、「住宅開発庁」と訳され、公共住宅の供給を担う、シンガポールの法定機関のこと。シンガポールが自治権を得た直後の1960年にスラム街や不法占拠住宅を一掃するために設立され、当初は低所得者層に賃貸住宅を供給し、その後は持ち家を持ちやすい制度に改められたそうです。それで、90%を超える世帯の人が家を持てるというのは、ちょっとうらやましいですね。
「私は外国人が多いエリアに住んでいるため、賃貸物件も多く、持ち家の比率は7~8割ぐらいに感じます」(台湾)
持ち家率が高い国でも、やはり外国人は賃貸住宅に住んでいることが多いようです。
持ち家と賃貸の比率がほぼ半々と思われるのが、アメリカ、カナダの北米の2カ国。
「ダウンタウンでは賃貸が多く、少し郊外へ行くと持ち家が多い印象です。近年では、外国籍富裕層による不動産購入や投資で不動産価格が高騰し、地元民には持ち家は手の届きにくいものになってしまいました」(カナダ)
持ち家率が不明だったパキスタンを除くと、今回調査した国・地域のなかで最も持ち家率が低いのはブラジルでした。
「持ち家率は40%未満です。2016年のサンパウロ市役所の報告によれば、人口約1,200万人の同市では35万8,000以上の世帯が自分の家を持っていません」(ブラジル)
ちなみに、日本の持ち家率は61.7%(2013年)*1。今回調査した国・地域との比較では、中間あたりに位置することになります。
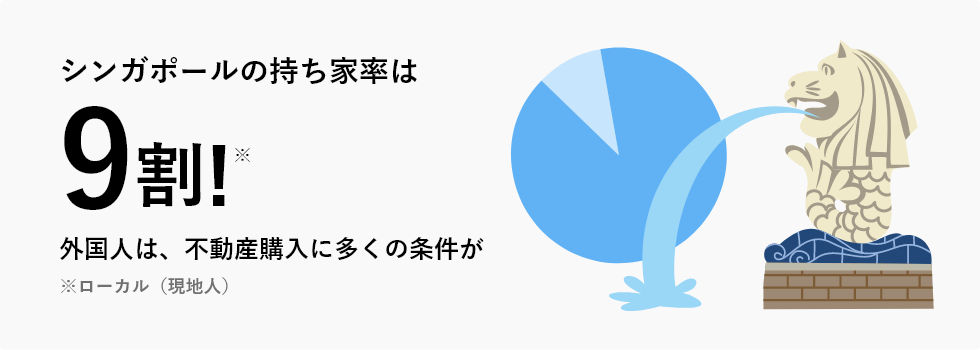
国土が大きければ、住宅もやっぱり広い?
一般的な持ち家の延べ面積についても、聞いてみましょう。
最も広かったのがアメリカで、約242平方メートル(2,600平方フィート)です。ほかに、200平方メートル台の数字があげられた国がカナダです。
「戸建てであれば、平均して160 ~200平方メートルくらいだと思います。マンションなら、1LDKで55平方メートル、2LDKで75平方メートル、3LDKで90平方メートルくらいが一般的でしょうか」(カナダ)
続いて、150平方メートルに届いたのは、ブラジル、パキスタンの2カ国。もっとも、パキスタンについては、在留邦人の住宅に限っての話です。
「それぞれの家の経済格差によって住宅の延べ面積にも大きな差があるため、一概にはいえないものの、一軒家なら100~150平方メートル程度、マンションなら60~120平方メートル程度でしょうか」(ブラジル)
「一般的な在留邦人の住宅は、150平方メートルぐらいですね」(パキスタン)
過去2シーズンの調査でヨーロッパなどでは持ち家の延べ面積が100平方メートル前後の国も少なくありませんでしたが、今回同程度の広さに該当したのはシンガポールだけでした。
「古いものと新しいもので広さがかなり違いますが、HDBの住宅は100平方メートルほどでしょうか。富裕層向けのコンドミニアムについては、広さに際限がないので、なんともいえません」(シンガポール)
やはり、国土が広大な国ほど、持ち家の延べ面積も大きいよう。ご参考までに、日本の持ち家の延べ面積は122.3平方メートル(2013年)*1、都道府県別では東京都の持ち家の延べ面積90.7平方メートル(2013年)*1が最小となっています。
独身なら間借りが当たり前のシンガポール
持ち家だけでなく、貸家についても知りたいですよね。一般的な貸家の賃料は、いくらぐらいなのでしょう? 金額は、特に注記がある場合を除いて、1カ月分の賃料です。
「3LDKで約105,705円(900ユーロ)が平均的な賃料です」(スペイン)
この広さでこの賃料なら、スペインに住んでみたくなりますね!
「ポートランド中心地のワンルーム、キッチン・バス付き(スタジオアパート)で、105,390円(1,000USドル)を超えるくらいです」(アメリカ)
日本の主要都市並みといったところでしょうか。
「エリアによって大きく異なるものの、ダウンタウンエリアなら2〜3LDK(75平方メートル前後)で174,614円(2,200CAドル)からになります。郊外でも、3LDKで158,740~198,425円(2,000~2,500CAドル)くらいが相場です。新しい建物やきれいな内装の貸家は、家賃がさらに高くなります」(カナダ)
「居住地域によって、家賃の相場にも大きな差があります。中流層向けの地域であれば、築20年、80平方メートルほどのマンションで約63,950円(2,500レアル)+共益費約17,906円(700レアル)。富裕層向けの地域であれば、同じ広さでも、約179,060円(7,000レアル)+共益費約20,464~25,580円(800~1,000レアル)という物件も」(ブラジル)
「150平方メートルの4LDK程度で、約158,085~210,780円(1,500~2,000USドル)です」(パキスタン)
こちらは、外国人あるいは富裕層向けですね。
「99.17~165.28平方メートル(30〜50坪)で約167,500~234,500円(5万〜7万台湾元)が、平均的な相場だといわれています」(台湾)
「場所によっても差がありますが、オーチャード(シンガポールの中心地)に近いコンドミニアムなら3ベッドルームで400,000円を超えます。2ベッドルームでも、200,000円を下回ることはありません。HDBで1ユニット借りる場合でも、200,000円前後はかかります。家賃がとにかく高いので、独身者は間借りをすることが多いです」(シンガポール)
日本でも若者がシェアハウスをするケースがありますが、シンガポールでは独身者は間借りをするのが普通だとは……。東京以上の家賃の高さが、よく伝わってきます。
カナダでは、不動産仲介手数料はかからない
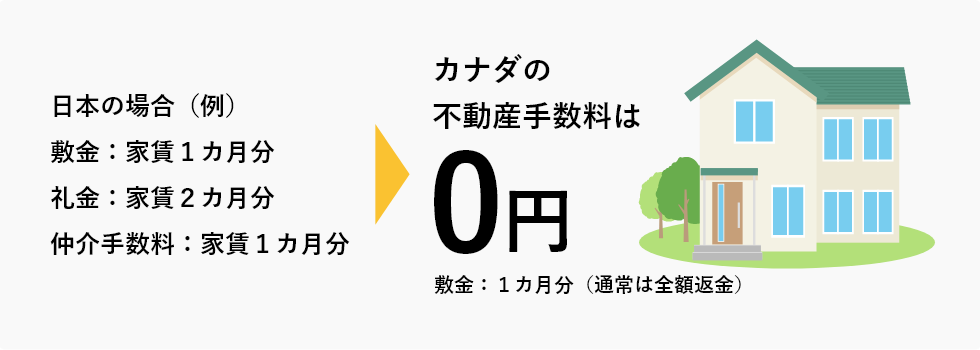
保証金、不動産仲介手数料など、住宅の賃貸にかかわるルールについても、尋ねてみました。
敷金や保証金、不動産仲介手数料など、日本とよく似たルールがあると回答があったのが、スペイン、ブラジル、台湾、シンガポールです。
「最初に、家賃数カ月分を保証金として支払わなければなりません。不動産仲介料もあります。その内容は、不動産業者や家主によりさまざまです。引っ越す際には、家の傷み具合などによって、保証金からその修繕費を引いた金額が返金されます」(スペイン)
「家を借りる場合、不動産を所有する人を保証人として署名をもらうのが一般的です。保証人が立てられないときには、家賃の数カ月分(通常3カ月分)を敷金として前払いすることもあります。契約書に定められた期限(通常、退去の1カ月前)までに契約解除を申し出れば、違約金は発生しません」(ブラジル)
「一般的に、保証金は家賃の2カ月分です。不動産仲介手数料については、1カ月の賃料の70%が上限とされています」(台湾)
「通常、手付金が家賃の1カ月分、2年契約なら敷金(デポジット)が家賃の2~3カ月分です。仲介手数料は、家賃の金額や契約期間によって変わります」(シンガポール)
賃貸にかかわるルールはあるものの、厳密ではなく、交渉の余地なども大きいと回答があったのは、アメリカ、パキスタンの2カ国。
カナダは、ほかの国とは少々趣が異なります。
「不動産会社を利用せず、ネットや新聞、張り紙などを頼りにオーナーに直接連絡をして契約を結ぶのが主流なので、不動産仲介料はかかりません。保証金もありませんが、前に住んでいた賃貸住宅のオーナーの紹介状が必要です。敷金は概ね家賃の1カ月分で、大きなダメージを与えることなどがなく普通に住んでいて、きちんと掃除をすれば、大抵の場合は退去時に全額が戻ってきます」(カナダ)
ここが◎ここが△。各国別お住いの地域の住宅事情
「バルセロナにはさまざまな地区があり、それぞれ特色があるので、お好みで住む場所を選べます。街はそれほど大きくありませんが、地下鉄や電車、バスがすべてそろい、交通の便はいいです。車道に自転車が走行するためのスペースが設けられており、自転車で移動することもできます。短所は、住居(マンション)が密集していて、緑豊かな公園が少ないこと。地区によっては、大気汚染や騒音問題、治安面が気になるところもあります」(スペイン)
「サンフランシスコ、LA、シアトル、NYなどの都市に比べて、ポートランドは物価が安いこともあり、人口が急激に増えたため、不動産価格が高騰し、安価な住宅が不足しています。ジェントリフィケーション(都市再開発)も進みました」(アメリカ)
「賃貸の場合は、初期費用が敷金と最初の月の家賃だけで済むのがよい点です。ただ、オーナーと直接契約を結ぶことになるので、対応が良かったり悪かったり、快適に住めるかどうかはオーナー次第のところがあります。カナダ人が集まれば、決まって話題にあがるのが不動産価格の高騰。多くのバンクーバー市民が家を買えずに州外へ出てしまい、人口流出などが問題になっています」(カナダ)
「サンパウロには日本人や日系人が多く、小規模ながら日本食を取り扱う食料品店もあって、日本人も現地人もお互いに違和感を覚えず、日本の地方都市に暮らしているようで過ごしやすいです。私が住んでいるところは、長年家族で住み続けている一軒家が多い地域で、雰囲気も落ち着いています」(ブラジル)
「大理石造りの家が多く、床が硬いので、物を落とすと、すぐ壊れてしまいます。同様の理由で、子どもの転倒にも注意が必要です。夏場は大理石が熱をもち、ハマム(トルコ式の風呂)のようなサウナ状態になる一方、冬は底冷えします。日本では考えられないほどの広い庭があるのは良いところです」(パキスタン)
「ほかのものと比較しても、不動産の価格は非常に高いと感じます。台北の中心部には古い物件が多く、家の造りも日本のものと比べると大雑把な印象。上の階の物音が響くため、修理が必要となることなどがひんぱんにあります。中心部から少し離れると新しいマンションも数多くできており、日本人も住みやすい物件が多いようです」(台湾)
「HDBとコンドミニアムでは、ずいぶん環境に差があります。コンドミニアムは、プールやジムなどのファシリティやセキュリティが充実しており、とても快適です。一方、HDBは、エレベーターが止まらない階などがあり、ファシリティもほとんどありません。特に不便なのは、洗濯物を干す場所がないこと。多くの場合には乾燥機を使用しますが、乾燥機がなければ家の窓辺などに干すしかないので大変です。そのほかに、各ベッドルームにトイレとバスがついていて、その掃除もかなりの負担。そのため、メイドさんを雇う人も多いです」(シンガポール)
各国の住宅事情には、日本と似ているところもあれば、まったく異なるところもあるようです。「ここなら住めそう」、「ここに住んでみたい!」と思える国はありましたか? 海外への移住も将来の選択肢の一つとお考えなら、実際にお住いの皆さんからのレポートを参考にしてみてはいかがでしょう。
※ 為替レートは2019年8月24日時点のものです。
<取材協力>
スペイン(バルセロナ)秦 真紀子、アメリカ(ポートランド)東 リカ、カナダ(バンクーバー)ハインリクス 可奈子、ブラジル(サンパウロ)大浦 智子、パキスタン(イスラマバード)篠原 尚子、台湾(台北)酒井 裕子、シンガポール(シンガポール)稲嶺 恭子
*1 「社会生活統計指標-都道府県の指標-2019」(総務省統計局)